「焼酎の炭酸割りは好きだけど、太るのが心配…」と感じていませんか。
すっきりとした飲み口で人気の焼酎炭酸割りですが、ダイエット中は特にカロリーや糖質が気になります。
この記事では、焼酎炭酸割りが太るとされる本当の原因を深掘りします。
具体的には、カロリーや糖質の詳細、そして他のお酒とのカロリー比較を通じて、その実態を明らかにします。
また、ダイエット中に焼酎炭酸割りはありかなしか、という疑問にもお答えします。
太る飲み方と太りにくい飲み方の違いを理解し、夜寝る前に飲むと太るのか、飲むなら何時までが適切か、といった具体的な時間帯の知識も大切です。
さらに、飲み過ぎると体に悪いのかという健康面の不安や、つい飲み過ぎて止まらなくなる際の対処法にも触れます。
この記事を最後まで読めば、太りにくい飲み方のコツを掴み、ダイエット中におすすめの焼酎3選も知ることができます。
もう失敗や後悔をせず、賢く焼酎を楽しむための知識を身につけましょう。
- 焼酎炭酸割りが太ると言われる原因と実際のカロリー・糖質量
- ビールや日本酒など他のお酒と比べた際のカロリーの違い
- ダイエット中でも楽しめる太りにくい飲み方や注意すべき点
- 体への影響を考慮した適量とダイエット中におすすめの焼酎銘柄
焼酎炭酸割りで太る?カロリーと原因を解説

- 焼酎炭酸割りの太る原因とは?
- 焼酎のカロリー・糖質はどのくらい?
- 他のお酒とのカロリー比較でわかること
- カロリーを消費するための運動量の目安
- 焼酎炭酸割りはダイエット中にあり?
焼酎炭酸割りの太る原因とは?
焼酎炭酸割りそのものが直接的に太るというより、太る原因は主に「飲み方」と「一緒に食べるおつまみ」にあると考えられます。焼酎は糖質を含まないため、お酒の中では太りにくいとされていますが、いくつかの要因が重なることで体重増加につながる可能性があります。
アルコールの働きと食欲増進
アルコールを摂取すると、肝臓はアルコールの分解を最優先で行います。このため、一緒に食べた食事に含まれる脂質や糖質の分解は後回しにされてしまいます。分解されずに残ったエネルギー源は、体脂肪として蓄積されやすくなるのです。特に、アルコールと脂質の多い食事を組み合わせると、脂肪の蓄積が促進される傾向があります。
また、アルコールには食欲を増進させる働きがあることも指摘されています。お酒を飲むと、つい味の濃いものや揚げ物など、高カロリーなものが食べたくなるのはこのためです。焼酎炭酸割りを楽しみながら、から揚げやフライドポテトなどをたくさん食べてしまえば、摂取カロリーが消費カロリーを大幅に上回り、結果として太る原因となります。
割るものによるカロリー・糖質の追加
焼酎炭酸割りは、焼酎を無糖の炭酸水で割るのが基本です。しかし、甘いサイダーやジュースで割ってしまうと、割り材に含まれる糖質やカロリーがそのまま加算されます。例えば、コーラやジンジャーエールで割った場合、1杯あたりのカロリーは大幅に増加し、糖質も摂取することになります。
このように、焼酎自体に糖質がなくても、割り方次第で高カロリー・高糖質な飲み物になってしまう点には注意が必要です。焼酎炭酸割りで太るのを避けたいのであれば、焼酎そのものよりも、飲み方や食事内容に気を配ることが大切になります。

焼酎のせいやないんやで。一緒に食べるもんとか、飲み方次第でどないにでもなるんやから、あんまり気にせんときや〜。
焼酎のカロリー・糖質はどのくらい?
焼酎のカロリーと糖質について正しく理解することは、太るのを防ぐための第一歩です。焼酎は「糖質ゼロ」という特徴がありますが、「カロリーゼロ」ではない点を押さえておく必要があります。
焼酎の糖質がゼロである理由
焼酎は、芋や麦、米などを原料としていますが、製造過程で行われる「蒸留」という工程で糖質が取り除かれます。蒸留とは、アルコール分を一度蒸発させてから再び液体に戻して抽出する方法です。糖質は蒸発しないため、この過程で除去され、完成した焼酎には糖質がほとんど含まれなくなるのです。
これは、ビールや日本酒、ワインといった「醸造酒」との大きな違いです。醸造酒は原料を発酵させて造るため、糖質が残ります。糖質制限を意識している方にとって、焼酎が選びやすいお酒とされるのはこのためです。
焼酎のカロリーの内訳
焼酎にカロリーが存在するのは、アルコール自体にエネルギーがあるからです。アルコールは1gあたり約7.1kcalのエネルギーを持つとされています。したがって、アルコール度数が高いお酒ほど、同じ量で比較した場合のカロリーは高くなる傾向にあります。
文部科学省の「日本食品標準成分表」によると、焼酎100mlあたりのカロリーは以下のようになっています。
- 甲類焼酎(アルコール度数35%の場合): 約206kcal
- 乙類焼酎(本格焼酎、アルコール度数25%の場合): 約146kcal
甲類焼酎は連続式蒸留という方法で造られ、より純度の高いアルコールが抽出されるため、一般的に乙類焼酎よりもカロリーが高くなります。
エンプティカロリーの正しい解釈
アルコールのカロリーは「エンプティカロリー」と呼ばれることがあります。これは「栄養素が空っぽ(エンプティ)」という意味であり、カロリーがないという意味ではありません。ビタミンやミネラルなどの栄養素をほとんど含まず、カロリーだけが存在する状態を指します。
また、アルコールのカロリーは他の栄養素よりも優先的に熱として消費されやすく、体内に蓄積されにくいという性質があります。しかし、これは「飲んでも太らない」ということではありません。前述の通り、アルコールの分解中は他の栄養素の代謝が滞るため、一緒に食べたもののカロリーが脂肪として蓄積されやすくなります。
以上のことから、焼酎は糖質ゼロですがカロリーはしっかり存在し、飲み過ぎれば太る可能性があると理解しておくことが大切です。



糖質ゼロやからって油断はあかんで!カロリーはあるんやからな。でも、ちゃんと知っとけば怖くないで、ええ勉強になったわ。
他のお酒とのカロリー比較でわかること


焼酎炭酸割りが太りやすいかどうかを判断するために、他のお酒とカロリーを比較してみましょう。100mlあたりのカロリーだけを見ると、焼酎は他のお酒よりも高カロリーに見えることがありますが、実際の飲用シーンを考慮すると見え方が変わってきます。
100mlあたりのカロリー比較
まず、文部科学省の「日本食品標準成分表」を参考に、代表的なお酒の100mlあたりのカロリーを見てみましょう。
| お酒の種類 | カロリー(100mlあたり) | 糖質(100mlあたり) |
| 焼酎(乙類・25度) | 約146 kcal | 0 g |
|---|---|---|
| 焼酎(甲類・35度) | 約206 kcal | 0 g |
| ビール(淡色) | 約40 kcal | 約3.1 g |
| 日本酒(純米酒) | 約103 kcal | 約3.6 g |
| ワイン(赤) | 約68 kcal | 約1.5 g |
| ワイン(白) | 約75 kcal | 約2.0 g |
| ウイスキー(40度) | 約237 kcal | 0 g |
この表を見ると、焼酎(乙類)のカロリーはビールやワインよりも高く、日本酒に近い数値であることがわかります。ウイスキーのようなさらに度数の高い蒸留酒は、より高カロリーです。
1杯あたりの実質的な摂取カロリー
しかし、この比較だけで「焼酎は太りやすい」と判断するのは早計です。なぜなら、お酒は種類によって1杯の量や飲み方が異なるからです。
- ビール: 中ジョッキ1杯(約400ml)で約160kcalになります。ごくごくと飲みやすいため、杯数が重なりがちです。
- 日本酒: 1合(180ml)で約185kcalです。比較的ゆっくり飲むことが多いですが、ビール同様に糖質が含まれます。
- 焼酎炭酸割り: 焼酎(乙類)60mlを炭酸水で割った場合、焼酎分のカロリーは約88kcalです。ビールの中ジョッキと比べて、1杯あたりのカロリーは半分近くに抑えられます。
焼酎はアルコール度数が高いため、水、お湯、炭酸水などで割って飲むのが一般的です。そのため、1杯あたりのアルコール摂取量とカロリーを調整しやすいという利点があります。
一方で、ビールや日本酒は割らずにそのまま飲むことが多く、口当たりの良さからつい飲み過ぎてしまう傾向にあります。結果として、総摂取カロリーが焼酎炭酸割りを上回ってしまうケースは少なくありません。
これらのことから、焼酎は100mlあたりの数値では高めに見えますが、実際の飲み方である「割りもの」を考慮すると、1杯あたりのカロリーは他のお酒より低く抑えることが可能です。つまり、飲み方を工夫すれば、他のお酒よりも太りにくい選択肢となり得るのです。



なんや、比べてみたら焼酎がめっちゃ悪者ってわけでもないんやな!むしろ飲み方次第で優等生やんか。
カロリーを消費するための運動量の目安
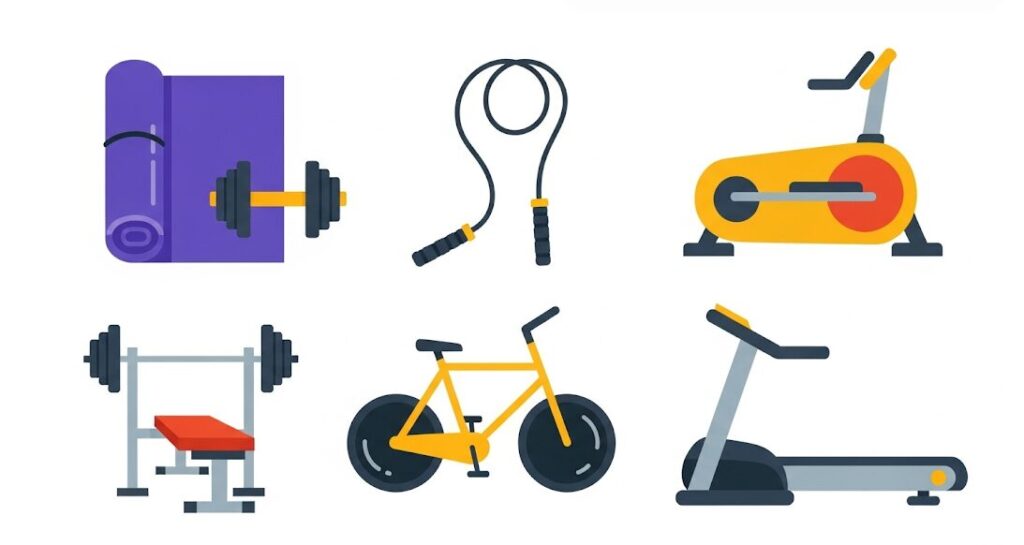
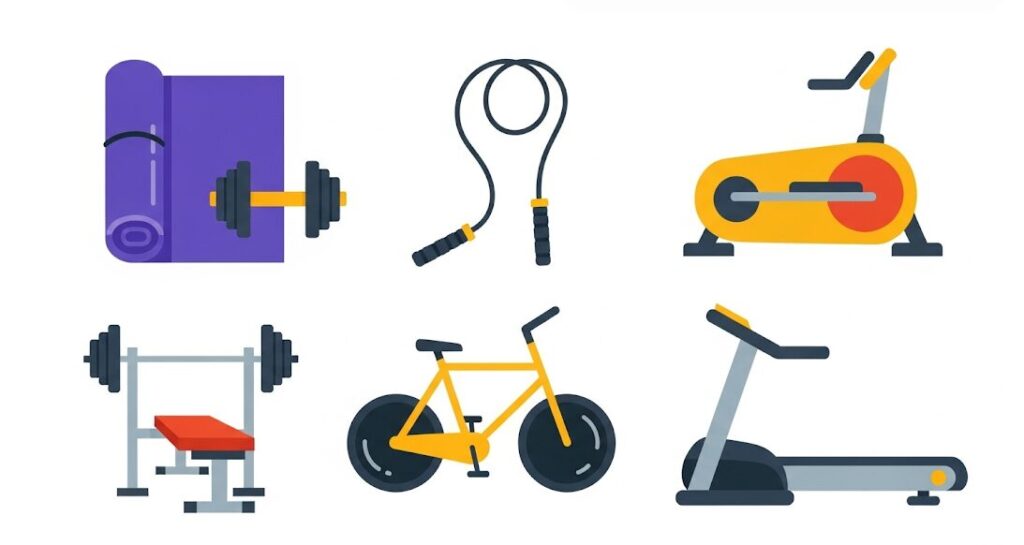
焼酎炭酸割り1杯分のカロリーがどのくらいの運動量に相当するのかを知っておくと、飲み過ぎの抑止力になり、健康管理の意識も高まります。ここでは、具体的な運動に換算して見ていきましょう。
焼酎炭酸割り1杯のカロリー
前述の通り、一般的な焼酎炭酸割り1杯(乙類焼酎60ml使用)のカロリーは、およそ85〜90kcalです。これは、ご飯お茶碗に軽く半分(約50g)程度のカロリーに相当します。お酒1杯と考えると決して低くはありませんが、このカロリーを消費するにはどのくらいの運動が必要なのでしょうか。
消費カロリーを計算する方法
運動による消費カロリーは、以下の式で概算できます。
消費カロリー(kcal) = METs × 運動時間(h) × 体重(kg) × 1.05
METs(メッツ)とは、運動強度の単位で、安静時を1とした場合にその何倍のエネルギーを消費するかを示す活動量の指標です。
85kcalを消費するための運動時間(体重60kgの場合)
体重60kgの人が約85kcalを消費するために必要な運動時間の目安を、いくつかの活動で計算してみましょう。
| 活動内容 | METs | 必要な運動時間 |
| ウォーキング(普通歩行) | 3.0 | 約27分 |
|---|---|---|
| ジョギング | 7.0 | 約12分 |
| サイクリング(軽いペース) | 4.0 | 約20分 |
| ヨガ | 2.5 | 約32分 |
| 軽い筋力トレーニング | 3.5 | 約23分 |
| 掃除機をかける | 3.3 | 約24分 |
| 階段の上り下り | 4.0 | 約20分 |
このように、焼酎炭酸割りをたった1杯飲むだけで、そのカロリーを消費するには20分以上のウォーキングが必要になることが分かります。もし3杯飲んだとしたら、その消費には1時間半近いウォーキングが必要になる計算です。
もちろん、これはあくまで目安の数値です。基礎代謝や筋肉量によって個人の消費カロリーは変動します。しかし、お酒を飲む際には、これだけのカロリーを摂取しているという意識を持つことが大切です。日々の活動量と摂取カロリーのバランスを考え、飲み過ぎてしまった日は少し長めに歩くなど、意識的に体を動かす工夫を取り入れると良いでしょう。



うわっ、一杯でこないに歩かなあかんのか…。でも、こうやって分かると、明日はちょっと頑張って歩こうかなって思えるからええな!
焼酎炭酸割りはダイエット中にあり?


ダイエット中にお酒を完全に断つのはストレスが溜まる、という方も多いはずです。そこで「焼酎炭酸割りはダイエット中に飲んでも良いのか?」という疑問が生まれます。結論から言うと、飲み方や量を工夫すれば「あり」と言えます。
ダイエット中に焼酎が向いている理由
焼酎が他のお酒と比べてダイエット中に適しているとされる理由は、主にその成分と種類にあります。
- 糖質ゼロ・プリン体ゼロ前述の通り、焼酎は蒸留の過程で糖質が除去されるため、糖質ゼロです。血糖値の急上昇を招きにくく、インスリンの過剰分泌を抑えられるため、脂肪がつきにくいというメリットがあります。また、痛風の原因となるプリン体も含まれていないため、健康を気遣う方にも適しています。
- 蒸留酒であることウイスキーやジン、ウォッカなどと同じ蒸留酒である焼酎は、ビールや日本酒などの醸造酒に比べて太りにくいとされています。これは糖質が含まれない点が大きな要因です。ダイエット中は、醸造酒よりも蒸留酒を選ぶのが賢明な選択と考えられます。
- 血栓予防効果の可能性一部の研究では、本格焼酎(乙類焼酎)に含まれる香り成分などには、血栓を溶かす酵素「プラスミン」を活性化させる効果がある可能性が示唆されています。もちろん、これは適量を守った場合の話であり、飲み過ぎは逆効果ですが、健康面でのポジティブな情報も存在します。
ダイエット中の注意点
ただし、ダイエット中に焼酎炭酸割りを飲む際には、いくつかの注意点を守る必要があります。
- 適量を厳守する: カロリーがある以上、飲み過ぎは禁物です。厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」は1日平均純アルコールで約20gです。これはアルコール度数25度の焼酎であれば約100mlに相当します。水割りや炭酸割りで1〜2杯程度が目安となります。
- 割り材を選ぶ: 甘いジュースやサイダーで割るのは避け、無糖の炭酸水、水、お湯、または無糖のお茶(ウーロン茶、緑茶など)を選びましょう。
- おつまみを工夫する: 揚げ物や高脂質なものは避け、冷奴、枝豆、刺身、野菜スティックなど、低カロリー・高たんぱく質なおつまみを選んでください。
したがって、焼酎炭酸割りは、糖質を気にせず楽しめるという点でダイエットの味方になり得ます。しかし、それはあくまで正しい知識を持って、量や飲み方をコントロールすることが大前提です。無計画に飲んでしまえば、どんなお酒でも太る原因になることを忘れないようにしましょう。



ダイエット中でも飲めるなんて、最高やんか!工夫次第で楽しめるんやから、ストレス溜めんと、うまいこと付き合っていこな。
焼酎炭酸割りで太るのを防ぐ飲み方と選び方


- 太る飲み方・太りにくい飲み方の違い
- 夜寝る前に飲むと太る?何時までOK?
- つい飲み過ぎて止まらなくなる対処法
- 飲み過ぎると体に悪い?適量を知ろう
- ダイエット中のおすすめ焼酎3選を紹介
太る飲み方・太りにくい飲み方の違い
同じ焼酎炭酸割りでも、飲み方の工夫一つで太りやすさは大きく変わります。ここでは、体重増加につながりやすい「太る飲み方」と、それを避けるための「太りにくい飲み方」の具体的な違いを解説します。
太る飲み方の特徴
無意識に続けているかもしれない、太りやすい飲み方にはいくつかの共通点があります。
- 甘い割り材を使う: コーラやジンジャーエール、フルーツジュースなど、糖分を多く含むもので割ると、焼酎の「糖質ゼロ」という利点が失われます。これにより、摂取カロリーと糖質量が大幅に増加し、血糖値も上がりやすくなります。市販の甘い缶チューハイも同様です。
- 濃い割合で飲む: 焼酎の割合が多い、いわゆる「濃いめ」の炭酸割りは、アルコール度数が高くなると同時に摂取カロリーも増えます。アルコールの作用で満腹中枢が麻痺し、おつまみを食べ過ぎる原因にもなります。
- 空腹時に飲む: 空腹の状態でお酒を飲むと、アルコールの吸収が速まり、血糖値が急激に変動しやすくなります。これは体に負担をかけるだけでなく、脂肪の蓄積を促す可能性があります。
- ハイペースで飲む: 短時間で何杯も飲むと、肝臓でのアルコール分解が追いつかず、体への負担が大きくなります。また、総摂取カロリーが短時間で増えるため、エネルギーとして消費しきれず脂肪になりやすいです。
太りにくい飲み方の工夫
一方で、少しの工夫で太りにくい飲み方を実践できます。
- 無糖の割り材を選ぶ: 最も基本となるのが、割り材を無糖のものにすることです。無糖の炭酸水、水、お湯、緑茶、ウーロン茶などがおすすめです。これらはカロリーがほとんどなく、焼酎本来の風味も楽しめます。
- 焼酎は乙類(本格焼酎)を選ぶ: 甲類焼酎よりも乙類焼酎の方が、一般的にカロリーが低い傾向にあります。また、芋や麦などの原料由来の豊かな香りや味わいは、少量でも満足感を得やすく、結果として飲み過ぎを防ぐことにもつながります。
- 食事と一緒にゆっくり楽しむ: 何かお腹に入れてから飲むことで、アルコールの吸収を穏やかにできます。食事と一緒に、会話を楽しみながらゆっくりとしたペースで飲むことを心がけましょう。
- チェイサー(水)を用意する: お酒の合間に水を飲むことで、アルコールの血中濃度の上昇を緩やかにし、脱水症状を防ぎます。また、お腹が膨れるため、自然とお酒の量を減らす効果も期待できます。
これらの点を意識するだけで、焼酎炭酸割りはダイエット中でも楽しめる味方になります。太るかどうかは、飲み手の知識と工夫次第と言えるでしょう。



なるほどなあ、割り材ひとつでこないに変わるんか。これからは無糖一択やな!ちょっとしたことで変わるんやから、試してみる価値あるで。
夜寝る前に飲むと太る?何時までOK?


「一日の終わりにリラックスしたい」と、寝る前に焼酎炭酸割りを飲む習慣がある方もいるかもしれません。しかし、この「寝酒」は、体重増加や睡眠の質に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。
寝る前の飲酒が太りやすい理由
夜、特に就寝直前の飲酒が太りやすいとされるのには、明確な理由があります。
- 代謝の低下: 睡眠中は、体を休息させるために基礎代謝が日中の活動時よりも低下します。このタイミングでカロリーを摂取すると、エネルギーとして消費されにくく、余った分が効率的に脂肪として体内に蓄積されてしまうのです。
- 肝臓への負担: 肝臓はアルコールの分解だけでなく、糖や脂肪の代謝も担っています。夜遅くに飲酒すると、睡眠中も肝臓はアルコールの分解作業で働き続けることになります。これにより、本来行われるべき脂肪の代謝が妨げられ、脂肪が蓄積しやすくなります。
- 成長ホルモンの分泌抑制: 睡眠中に分泌される成長ホルモンには、脂肪を分解する働きがあります。しかし、アルコールを摂取すると、この成長ホルモンの分泌が抑制されることが分かっています。結果として、脂肪が燃焼されにくい状態になってしまいます。
睡眠の質への悪影響
寝酒をすると寝つきが良くなるように感じることがありますが、これはアルコールの作用で脳の働きが一時的に鈍っているだけです。実際には、アルコールが分解される過程で発生するアセトアルデヒドという物質が交感神経を刺激し、脳を覚醒させてしまいます。
これにより、眠りが浅くなったり、夜中に目が覚めやすくなったりと、睡眠の質は著しく低下します。質の悪い睡眠は、食欲をコントロールするホルモンのバランスを乱し、翌日の過食につながることもあるため、ダイエットの観点からも避けるべきです。
飲むなら何時までが理想か
では、夕食時にお酒を楽しむ場合、何時までに飲み終えるのが良いのでしょうか。
一般的に、アルコールが体内で分解・処理される時間を考慮すると、就寝する3時間前までには飲酒を終えるのが理想的とされています。例えば、夜12時に寝る人であれば、夜9時までには飲み終えるのが目安です。
これにより、肝臓への負担を軽減し、睡眠の質への影響を最小限に抑えることができます。夜遅くに飲み会などがある場合は、量を控えめにする、アルコール度数の低いものを選ぶなどの工夫が求められます。



あぶなー!寝る前に飲むとこやったわ。太るだけやのうて、眠りも浅くなるんか。ええことないやんけ!はよ飲んで、はよ寝るに限るな!
つい飲み過ぎて止まらなくなる対処法
「今日は1杯だけ」と決めていたのに、気づけば何杯も飲んでしまった、という経験は誰にでもあるかもしれません。焼酎炭酸割りは口当たりが良いため、特に飲み過ぎてしまいがちです。ここでは、つい止まらなくなるのを防ぐための具体的な対処法を紹介します。
飲む前の準備と環境づくり
飲み始める前の少しの工夫が、飲み過ぎを防ぐ鍵となります。
- 飲む量をあらかじめ決めておく: 「今日は2杯まで」というように、具体的な上限を自分で決めておきます。ボトルから直接注ぐのではなく、決めた量だけをカラフェなどに移しておくと、視覚的に残量が分かり、セーブしやすくなります。
- 食事を先にある程度済ませておく: 空腹状態で飲み始めると、アルコールの吸収が速く、酔いが回りやすくなります。また、お腹を満たそうとしてお酒のペースも上がりがちです。先に野菜やたんぱく質中心の食事を摂っておくことで、食欲と飲酒ペースの両方を落ち着かせることができます。
- チェイサーを必ず用意する: 焼酎炭酸割りのグラスの横に、必ず水の入ったグラス(チェイサー)を置きましょう。「お酒を一口飲んだら、水を一口飲む」というルールを徹底するだけで、飲むペースが自然と落ち、脱水予防にもなります。
飲んでいる最中の工夫
飲んでいる最中にも、意識的にできることがあります。
- ゆっくり味わって飲む: 焼酎の香りや炭酸の刺激を五感で楽しむように、一杯をじっくりと味わいましょう。特に本格焼酎(乙類)は、原料ごとの豊かな香りがあります。香りを楽しむことに集中すると、飲むペースを自然と落とすことができます。
- 会話や他の活動に集中する: 一人での晩酌は、手持ち無沙汰からついグラスに手が伸びがちです。誰かと会話をしたり、映画を観たり、音楽を聴いたりしながら、お酒を「主役」ではなく「脇役」に位置づけることで、飲むことへの集中を分散させることができます。
- 低アルコール度数で楽しむ: いつもよりも焼酎の量を減らし、炭酸水を多めに入れる「薄めの炭酸割り」を作るのも有効です。飲む行為そのものを楽しみつつ、アルコールの総摂取量を抑えることができます。
これらの対処法は、意志の力だけに頼るのではなく、仕組みで飲み過ぎを防ぐためのものです。自分に合った方法をいくつか組み合わせて、無理なく適量を守る習慣を身につけていきましょう。



わかるわ〜、ついつい飲み過ぎてまうよな。でも、こないな対策があったんやな。これなら無理せずできそうや。これからは水も相棒やで!
飲み過ぎると体に悪い?適量を知ろう
焼酎炭酸割りがいくら糖質ゼロで太りにくいとされていても、アルコールである以上、飲み過ぎは体に様々な悪影響を及ぼします。健康的に長くお酒を楽しむためには、「適量」を知り、それを守ることが何よりも大切です。
アルコールの過剰摂取がもたらすリスク
アルコールを飲み過ぎると、以下のような健康上のリスクが高まることが知られています。
- 肝臓への負担: 肝臓はアルコール分解の中心的な役割を担っています。過剰な飲酒が続くと、肝臓に脂肪が溜まる「脂肪肝」を引き起こし、悪化すると「アルコール性肝炎」や「肝硬変」、さらには「肝がん」へと進行する可能性があります。
- 生活習慣病のリスク上昇: 中性脂肪の増加、高血圧、血糖値の乱れなどを引き起こし、脂質異常症や糖尿病、心疾患、脳卒中といった生活習慣病のリスクを高めます。
- 脳への影響: 長期的な大量飲酒は、脳の萎縮や認知機能の低下を招くことがあります。また、アルコール依存症という精神疾患につながる危険性もはらんでいます。
- 消化器官へのダメージ: アルコールは胃や腸の粘膜を刺激し、胃炎や胃潰瘍、逆流性食道炎などの原因となることがあります。
「節度ある適度な飲酒」とは
厚生労働省が推進する「健康日本21」では、「節度ある適度な飲酒」として、1日あたりの純アルコール摂取量を約20g程度としています。これは、各種お酒に換算すると以下の量が目安となります。
| お酒の種類 | 目安量 |
| 焼酎(25度) | 約100ml |
|---|---|
| ビール(5度) | 中びん1本(500ml) |
| 日本酒(15度) | 1合(180ml) |
| ワイン(12度) | グラス2杯弱(約200ml) |
| ウイスキー(40度) | ダブル1杯(60ml) |
焼酎であれば、100mlが1日の適量ということになります。これは、一般的な居酒屋で提供される焼酎の水割りや炭酸割りで、およそ1杯から2杯に相当します。もちろん、これはアルコールを毎日摂取する場合の平均値であり、体質やその日のコンディションによっても適量は変わります。女性や高齢者、アルコールの分解能力が低い人は、これよりも少ない量が推奨されます。
「お酒は百薬の長」と言われることもありますが、それはあくまで「適量」を守った場合の話です。飲み過ぎれば、どんなお酒も「毒」になり得ます。自分の体と向き合い、健康を第一に考えた飲酒を心がけることが重要です。
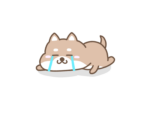
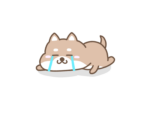
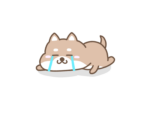
やっぱり飲み過ぎはあかんなあ。体に悪いって分かってても、なかなかやめられへん時もあるし…。でも、自分の体を大事にするためにも、この「適量」はちゃんと覚えとかなあかんな。
ダイエット中のおすすめ焼酎3選を紹介


ダイエット中に焼酎炭酸割りを楽しむなら、どの焼酎を選ぶかも大切なポイントです。ここでは、カロリーが比較的低く、豊かな風味で満足感も得やすい「乙類焼酎(本格焼酎)」の中から、特におすすめの銘柄を3つ紹介します。
① 黒霧島(芋焼酎)
宮崎県の霧島酒造が造る「黒霧島」は、全国的に最も広く知られている芋焼酎の一つです。スーパーやコンビニでも手軽に入手できるのが魅力です。
黒麹仕込みならではの、とろりとした甘みとキリっとした後切れが特徴で、芋焼酎特有のクセが強すぎないため、芋焼酎初心者の方にも飲みやすいと評判です。炭酸で割ると、芋のふくよかな香りが立ち上りながらも、味わいは非常にすっきりとします。霧島酒造の公式サイトでも「黒ッキリボール」として推奨されており、その相性の良さは折り紙付きです。和洋中どんな料理にも合わせやすく、食中酒としても万能です。
② いいちこNEO(麦焼酎)
「下町のナポレオン」の愛称で親しまれる「いいちこ」で有名な、大分県の三和酒類が「炭酸割りのために開発した」という新しいタイプの麦焼酎が「いいちこNEO」です。
この焼酎は、独自の酵母を使用することで、青リンゴや南国のフルーツを思わせる華やかでフルーティーな香りを実現しています。従来の麦焼酎のイメージを覆すような爽やかな香りは、炭酸との相性が抜群です。焼酎の独特な風味が苦手な方や、普段あまり焼酎を飲まない方でも、まるで新しいカクテルのように楽しむことができます。ボトルデザインもおしゃれで、家飲みの気分を上げてくれる一本です。
③ 亀甲宮焼酎(キンミヤ焼酎)(甲類焼酎)
三重県の宮崎本店が製造する「亀甲宮焼酎」、通称「キンミヤ」は、乙類ではなく甲類焼酎ですが、そのクリアな味わいから炭酸割りのベースとして絶大な人気を誇ります。
甲類焼酎はクセがないのが特徴ですが、キンミヤはほのかに甘みを感じるまろやかな口当たりで、他の甲類焼酎とは一線を画す品質です。どんな割り材とも喧嘩せず、素材の味を最大限に引き立ててくれます。無糖の炭酸水で割るだけで、シンプルながらも奥深い、どこか懐かしい味わいの焼酎ハイボールが完成します。価格がリーズナブルな点も、日常的に楽しむお酒として嬉しいポイントです。
これらの焼酎は、それぞれ異なる個性を持っています。自分の好みやその日の気分に合わせて選び、賢く美味しく焼酎炭酸割りを楽しみましょう。



へぇ〜、こないな種類があるんやな。どれも美味そうやんか!今度スーパー行ったら探してみよ。ダイエット中でも選ぶ楽しみがあるってええなあ。
焼酎炭酸割りで太るかは飲み方次第
この記事では、焼酎炭酸割りと体重増加の関係について、多角的に解説してきました。最後に、太らずに楽しむための重要なポイントをまとめます。
- 焼酎炭酸割りが太る直接的な原因は焼酎自体ではない
- 太る主な原因は高カロリーなおつまみの食べ過ぎにある
- アルコールは食欲を増進させ脂質の代謝を後回しにする
- 焼酎は蒸留酒のため糖質もプリン体もゼロである
- カロリーはアルコール分に由来するためゼロではない
- 乙類焼酎は甲類焼酎よりカロリーが低い傾向がある
- 1杯あたりのカロリーはビールや日本酒より低く抑えやすい
- 太る飲み方は甘いジュースなどで割る飲み方である
- 太りにくい飲み方は無糖の炭酸水やお茶で割るのが基本
- 夜寝る直前の飲酒は脂肪が蓄積しやすいため避けるべき
- 飲酒は就寝の3時間前までに終えるのが理想
- 飲み過ぎを防ぐにはチェイサーの水を一緒に飲むのが有効
- 厚生労働省が示す1日の適量は純アルコールで約20g
- これは25度の焼酎で約100ml(1〜2杯)に相当する
- 飲み方と量を工夫すればダイエット中でも楽しむことは可能



結局は、ぜーんぶ自分次第ってことやな!正しい知識があれば、我慢せんでもええんや。これからも美味しく、賢く、焼酎を楽しんでいこか!


・メンタルを整える本を紹介-1.png)






