とろりとした濃厚な口当たりと、お米の優しい甘みが魅力のにごり酒。
その美味しさから、つい盃が進んでしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、その一方で「にごり酒は太る」という噂を耳にして、飲むのをためらってしまうこともあるかもしれません。
実際のところ、にごり酒は太るのか、その太る原因はどこにあるのでしょうか。
この記事では、にごり酒のカロリーや糖質について、他のお酒とのカロリー比較を交えながら詳しく掘り下げます。
また、にごり酒のカロリーを消費するための運動量や、そもそもダイエット中にありなのか、飲み過ぎると体に悪いのか、そして夜寝る前に飲むと太るのか、飲むなら何時までが良いのか、といった様々な疑問にお答えします。
さらに、知らず知らずのうちに実践しているかもしれない太る飲み方と、今日から始められる太りにくい飲み方の具体的なポイント、美味しさのあまり止まらなくなる場合の対処法、そしてダイエット中のおすすめお酒3選まで、網羅的に解説していきます。
この記事を読めば、にごり酒と上手に付き合いながら、健康的にお酒を楽しむための知識が身につくはずです。
- にごり酒が太りやすいとされる具体的な理由
- 他のお酒と比べたカロリーと糖質の位置づけ
- ダイエット中ににごり酒と上手に付き合う方法
- 太りにくい飲み方とおすすめの代替酒
にごり酒は太る?カロリーや糖質が原因か解説

- にごり酒の太る原因はもろみにあり
- にごり酒のカロリー・糖質はどれくらい?
- 他のお酒とのカロリー比較で見る立ち位置
- にごり酒のカロリーを消費するための運動量
- 飲み過ぎると体に悪い?肝臓への負担も
にごり酒の太る原因はもろみにあり
にごり酒が太りやすいと言われる最も大きな理由は、その製造方法に由来する「もろみ」の存在にあるとされています。
一般的な日本酒、いわゆる「清酒」は、発酵が終わったもろみを布袋などに入れて搾り、透明な液体部分だけを取り出したお酒です。この工程で、お米の固形分である「酒粕」と液体が分離されます。
一方、にごり酒は、この搾る工程を意図的に粗くしたり、搾った後の透明な液体に、もろみの一部をあえて混ぜ戻したりして造られます。そのため、瓶の底に白く沈殿している部分、これが「もろみ」であり、栄養素が豊富に含まれているのです。
もろみには、米由来の糖質やでんぷん、タンパク質、アミノ酸、ビタミンといった栄養成分がそのまま残っています。これが、にごり酒特有の濃厚な味わいや甘み、とろりとした食感を生み出す源泉です。しかし、これらの栄養成分は、そのままカロリーや糖質の高さに直結します。つまり、にごり酒を飲むことは、透明な日本酒を飲むことに加えて、栄養価の高い「お米の成分」を一緒に摂取していることと同じ意味合いを持つのです。
このように考えると、にごり酒が他の日本酒に比べてカロリーや糖質が高くなるのは自然なことであり、これが「太りやすい」と言われる直接的な原因と考えられます。

なるほどな~、あのもろみが美味しさの秘訣で、カロリーの源でもあるんやな。理由が分かるとスッキリするわ!
にごり酒のカロリー・糖質はどれくらい?


にごり酒の具体的なカロリーと糖質は、一般的な日本酒(清酒)と比較して高い数値を示す傾向にあります。
製品によって差はありますが、一般的な純米酒などの清酒が100mlあたり約105kcal、糖質が約4.5gとされているのに対し、にごり酒は100mlあたり120kcalから160kcal程度、糖質は6gから10g程度になるという情報が見られます。中には、1合(180ml)あたり約300kcalに達するとされる製品もあり、これは清酒の1.5倍近い数値です。
この差を分かりやすくするために、他のお酒とも比較してみましょう。
| 種類 | カロリー(100mlあたり目安) | 糖質(100mlあたり目安) |
| にごり酒 | 約120~160 kcal | 約6.0~10.0 g |
| 一般的な日本酒(純米酒) | 約105 kcal | 約4.5 g |
| ビール(淡色) | 約40 kcal | 約3.1 g |
| 焼酎(乙類) | 約146 kcal | 0 g |
このように、にごり酒はアルコール飲料の中でもカロリー、糖質ともに上位に位置することが分かります。特に、糖質に関しては、同じ日本酒である清酒よりもかなり多くの量を含んでいる点を意識しておくことが大切です。ダイエットや健康管理で糖質を気にしている方は、この数値を念頭に置いて飲む量を調整する必要があります。



うわ、数字で見ると結構あるんやな!でも、こうやってちゃんと知っとくことが大事やんな。知らんまま飲むより絶対ええわ!
他のお酒とのカロリー比較で見る立ち位置


にごり酒のカロリーと糖質は、他の様々なアルコール飲料と比較しても、特に注意が必要なレベルにあると言えます。
まず、ビールやワインといった「醸造酒」の仲間と比較してみましょう。文部科学省の食品成分データベースによると、ビール(淡色)のカロリーは100mlあたり約40kcal、赤ワインは約68kcalとされています。これらと比較すると、100mlあたり120kcal以上あるにごり酒のカロリーは、2倍から3倍以上となり、突出して高いことが明確です。
次に、焼酎やウイスキーといった「蒸留酒」と比較します。焼酎(乙類)は100mlあたり約146kcal、ウイスキーは同約225kcalと、アルコール度数の高さに比例してカロリーも高くなります。一見すると、にごり酒よりカロリーが高いように見えますが、ここで最も大きな違いとなるのが「糖質」の有無です。
蒸留酒は、醸造したお酒を一度蒸発させ、アルコール分などを冷却して再び液体に戻す工程(蒸留)を経ています。この過程で原料由来の糖質は除去されるため、焼酎やウイスキーの糖質は0gです。
一方で、にごり酒は醸造酒であり、前述の通りもろみの成分が豊富に残っているため、高いカロリーに加えて多量の糖質も含まれています。以上の点を踏まえると、にごり酒は「高カロリーかつ高糖質」という、ダイエットにおいては最も警戒すべき特性を持ったお酒であると位置づけられます。
| 種類 | 製造法 | カロリー(100mlあたり) | 糖質(100mlあたり) |
| にごり酒 | 醸造酒 | 約120~160 kcal | 約6.0~10.0 g |
| ビール | 醸造酒 | 約40 kcal | 約3.1 g |
| ワイン(赤) | 醸造酒 | 約68 kcal | 約1.5 g |
| 焼酎 | 蒸留酒 | 約146 kcal | 0 g |
| ウイスキー | 蒸留酒 | 約225 kcal | 0 g |
このように、他のお酒と比較することで、にごり酒が持つ特性がより鮮明になります。お酒を選ぶ際には、カロリーだけでなく、糖質の量にも注目することが健康的な選択の鍵となります。



こうやって比べてもらうと、にごり酒の立ち位置がよう分かるわ。焼酎とかは糖質ゼロなんか~。賢い飲み方考えるきっかけになるな!
にごり酒のカロリーを消費するための運動量
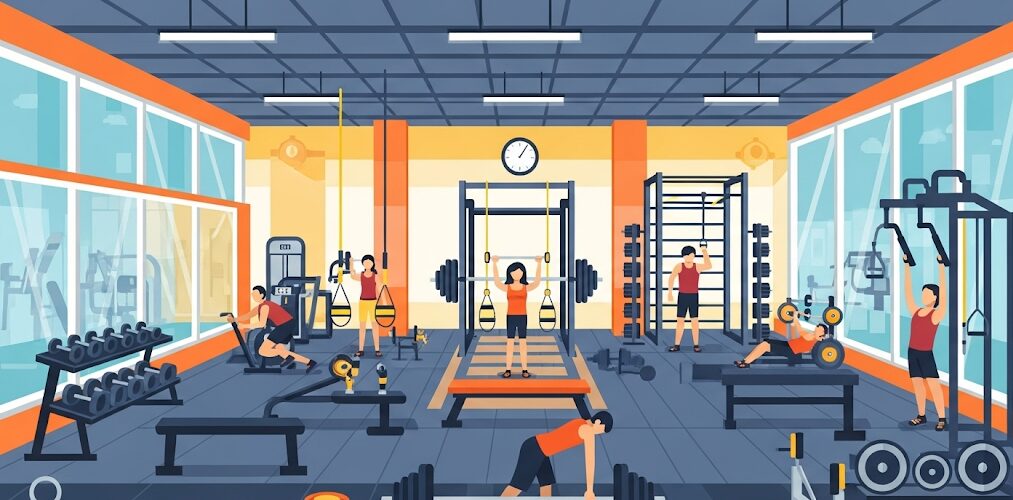
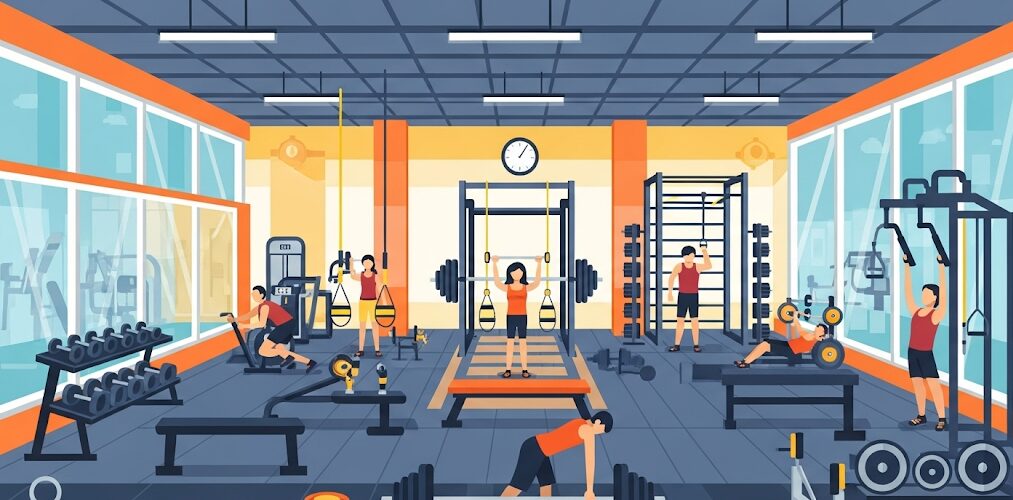
にごり酒を飲んだ場合、そのカロリーを消費するためには、どのくらいの運動が必要になるのでしょうか。具体的な運動量を知ることで、カロリーの数値をより現実的に捉えることができます。
ここでは、にごり酒1合(180ml)を飲んだ際のカロリーを、やや高めの250kcalと仮定して考えてみましょう。この250kcalという数値は、お茶碗に軽く一杯のご飯(約150g)のカロリー(約237kcal)とほぼ同等です。
体重60kgの人が250kcalを消費するために必要な運動時間の目安は、以下のようになります。
- ウォーキング(やや速め、時速約5km):約60分
- ジョギング(時速約8km):約30分
- サイクリング(時速約20km):約40分
- 水泳(クロール、ゆっくり):約25分
- 階段の上り下り:約30分
- 家事(掃除機をかけるなど):約80分
(注:これらの数値は運動強度や個人の基礎代謝によって変動するため、あくまで一般的な目安です)
このように見ると、「ついつい盃が進んでしまった」一杯分のカロリーを消費するためには、意外とまとまった時間の運動が必要になることが分かります。例えば、寝る前ににごり酒を1合飲んでしまった場合、そのカロリーを消費しないまま就寝することになり、体脂肪として蓄積されやすくなってしまいます。
もちろん、たまに楽しむ程度であれば過度に心配する必要はありません。しかし、日常的に飲む習慣がある方は、一杯のカロリーが持つ意味を理解し、日々の活動量を意識したり、飲む量をコントロールしたりすることが、体型維持のためには不可欠と言えるでしょう。



1合でジョギング30分か~!飲む前に走るか、飲んだ分だけ走るか…どっちにしてもええ運動になるな!
飲み過ぎると体に悪い?肝臓への負担も
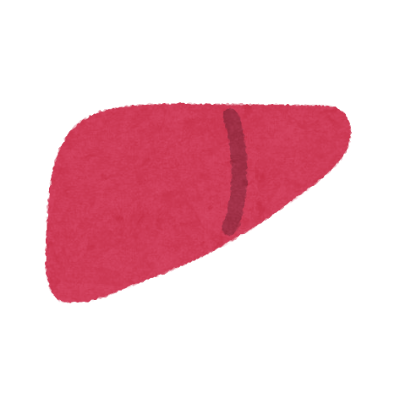
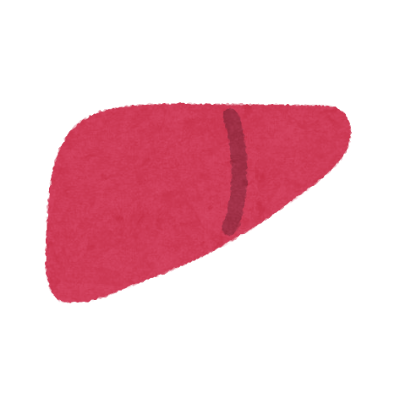
にごり酒に限った話ではありませんが、いかなるアルコール飲料も飲み過ぎは体に悪影響を及ぼす可能性があり、特に肝臓への負担は大きな懸念点となります。
アルコールを摂取すると、その分解は主に肝臓で行われます。しかし、肝臓が一度に処理できるアルコールの量には限りがあり、許容量を超えたアルコールが体内に入ってくると、分解が追いつかずにアセトアルデヒドという有害物質が血液中に長く留まります。これが二日酔いの原因となるだけでなく、長期的には肝臓の細胞を傷つける原因にもなります。
特に、にごり酒の場合は、アルコールに加えて糖質も多量に含んでいるため、肝臓への負担が二重になる可能性が考えられます。アルコールの過剰摂取は、肝臓に中性脂肪が蓄積する「脂肪肝」のリスクを高めますが、糖質の摂り過ぎも同様に脂肪肝の原因となります。つまり、にごり酒の飲み過ぎは、アルコールと糖質の両面から肝臓に負担をかけ、脂肪肝を引き起こしやすい状態を作ってしまうのです。
脂肪肝は自覚症状がほとんどないまま進行し、放置するとアルコール性肝炎や肝硬変、さらには肝臓がんといった、より深刻な病気につながるリスクも指摘されています。
厚生労働省が推進する「健康日本21」では、「節度ある適度な飲酒」として、1日あたりの純アルコール摂取量を約20g程度と推奨しています。これは、にごり酒を含む日本酒に換算すると、およそ1合(180ml)が目安となります。
健康を維持しながらお酒を楽しむためには、この適量を守ることが基本です。また、週に2日程度の「休肝日」を設けて肝臓を休ませることも、長期的に見て非常に大切な習慣となります。



そらそうやんな、体は大事にせなあかん。美味しいからって無理させたらアカンな。休肝日、ちゃんと考えよ!
にごり酒で太るのを防ぐ飲み方と注意点


- にごり酒はダイエット中にあり?なし?
- 太る飲み方・太りにくい飲み方のポイント
- 夜寝る前に飲むと太る?何時までにすべきか
- 美味しくて止まらなくなる対処法はある?
- ダイエット中のおすすめお酒3選
にごり酒はダイエット中にあり?なし?


「ダイエット中ににごり酒は飲んでも良いのか?」という問いに対しては、「絶対にNGというわけではないが、飲むのであれば細心の注意と工夫が必要」というのが答えになります。
前述の通り、にごり酒は他のお酒と比較してカロリーと糖質が共に高いという特性を持っています。そのため、ダイエット中に無計画に飲んでしまうと、せっかくの運動や食事制限の努力が水の泡になってしまう可能性が非常に高いです。
もし、どうしてもダイエット中ににごり酒を楽しみたいのであれば、それは「ご褒美」や「特別な日」といった位置づけにし、以下の点を徹底することが求められます。
1. 飲む量を厳格に管理する
飲む量は、お猪口に1杯(約30ml)から多くても2杯(約60ml)程度に留めるのが賢明です。1合(180ml)を飲んでしまうと、それだけで250kcal以上のカロリーと10g以上の糖質を摂取することになり、ダイエット中の食事計画に大きな影響を与えてしまいます。
2. 1日の総摂取カロリー・糖質量を調整する
にごり酒を飲む日は、その分のカロリーと糖質を他の食事から差し引く必要があります。例えば、夕食時に飲むのであれば、ご飯やパン、麺類といった主食を半分にするか、あるいは完全に抜くといった調整が不可欠です。また、その日一日の間食は完全に断つくらいの意識が大切になります。
3. 飲むタイミングを選ぶ
空腹時や寝る直前に飲むのは避け、食事と一緒にゆっくりと味わうようにしましょう。これにより、血糖値の急上昇を抑え、アルコールの吸収も緩やかになります。
要するに、ダイエット中ににごり酒を飲むことは可能ですが、それは日々の食事管理を完璧に行っている上での「例外的な楽しみ」と捉えるべきです。日常的な晩酌としてにごり酒を選ぶのは、ダイエットの観点からは推奨されません。もしお酒を飲む習慣を続けたいのであれば、後述するような、より糖質の少ないお酒に切り替えることを検討するのが現実的な選択と言えるでしょう。



絶対にアカンわけやないんやな!良かった~。ルールさえ守ればご褒美に飲めるんやったら、ダイエットも頑張れるわ!
太る飲み方・太りにくい飲み方のポイント
同じにごり酒を飲む場合でも、その飲み方や一緒におつまみを工夫するだけで、体に与える影響は大きく変わってきます。ここでは、太りやすい飲み方と、それを避けるための太りにくい飲み方のポイントを具体的に解説します。
太る飲み方:これだけは避けたいNG習慣
- 空腹での一気飲み空腹の状態でお酒を飲むと、アルコールが胃で速やかに吸収され、血糖値が急激に上昇しやすくなります。インスリンが過剰に分泌され、糖が脂肪として蓄積されやすくなるため、最も避けたい飲み方の一つです。
- 甘い割り材で割るにごり酒をジュースや甘い炭酸飲料で割るスタイルは、さらに糖質を追加することになり、カロリーオーバーの直接的な原因となります。
- 高カロリー・高糖質のおつまみアルコールには食欲増進作用があるため、ついおつまみに手が伸びがちです。唐揚げやポテトフライなどの揚げ物、ポテトサラダ、〆のラーメンやご飯ものは、アルコールと組み合わせることで脂肪蓄積を加速させてしまいます。
- 量を決めずにダラダラ飲む「テレビを見ながら」「話をしながら」といった状況で、時間をかけずに次々と盃を重ねる飲み方は、気づかないうちに許容量をオーバーしてしまいがちです。
太りにくい飲み方:賢く楽しむためのポイント
- 食事と一緒に、または食後に食事、特に野菜など食物繊維が豊富なものを先に食べてから飲むことで、アルコールの吸収や血糖値の上昇を緩やかにする効果が期待できます。
- 「和らぎ水」を必ず用意する「和らぎ水(やわらぎみず)」とは、日本酒と一緒に飲む水のことです。にごり酒を一杯飲んだら、同量以上の水を飲むように心がけましょう。これにより、血中アルコール濃度が薄まり悪酔いを防ぐだけでなく、満腹感が得やすくなり、飲み過ぎの防止にもつながります。
- 高タンパク・低糖質のおつまみを選ぶおつまみを選ぶなら、代謝を助けるタンパク質やビタミンが豊富な食材がおすすめです。
- 冷奴、湯豆腐:低カロリーで良質なタンパク質が摂れます。
- 枝豆:アルコールの分解を助けるビタミンB1やメチオニンが豊富です。
- お刺身(特にタコやイカ):タウリンが肝臓の働きを助けます。
- 野菜スティック、きのこのソテー:食物繊維が豊富で、満腹感も得られます。
- 体を温める飲み方(熱燗)を試す体を冷やすと基礎代謝が低下し、脂肪を溜め込みやすくなると言われています。にごり酒を少し温めて「熱燗」にすることで、体を内側から温め、代謝の低下を防ぐ助けになる可能性があります。
これらのポイントを意識するだけで、にごり酒との付き合い方は大きく変わります。楽しみながらも、自分の体をいたわる飲み方を実践することが大切です。



飲み方一つで全然違うんやな。和らぎ水とおつまみ選び、これめっちゃ大事やん!次から絶対やるで!
夜寝る前に飲むと太る?何時までにすべきか


夜、寝る前ににごり酒を飲む習慣は、体重増加の観点から見ると、非常にリスクの高い行為と言えます。その理由は、人間の体のメカニズムと深く関係しています。
私たちの体には、「BMAL1(ビーマルワン)」という特殊なタンパク質が存在します。このBMAL1は、体内で脂肪を合成し、溜め込む働きを促進する役割を担っており、時間帯によって体内の量が変動する「体内時計」のような性質を持っています。
BMAL1の量は、日中、特に午後3時頃に最も少なくなり、夜にかけて徐々に増加していきます。そして、夜10時から深夜2時にかけてその量がピークに達するとされています。つまり、この時間帯に食事や飲酒をすると、摂取したカロリーや糖質が効率よく脂肪として蓄積されやすいのです。
したがって、夜寝る前にカロリーも糖質も高いにごり酒を飲むことは、脂肪を溜め込むためのゴールデンタイムに、その材料を自ら供給しているようなものと言えます。
さらに、アルコールには睡眠の質を低下させるという側面もあります。寝る前に飲むと寝つきが良くなるように感じるかもしれませんが、実際には深い眠り(ノンレム睡眠)を妨げ、夜中に目が覚めやすくなるなど、睡眠サイクルを乱してしまいます。睡眠不足は、食欲を増進させるホルモン(グレリン)の分泌を増やし、食欲を抑制するホルモン(レプチン)の分泌を減らすことが分かっており、これもまた肥満につながる一因となります。
これらの理由から、お酒を飲むのであれば、就寝する3時間から4時間前までには飲み終えるのが理想的です。例えば、夜11時に寝る人であれば、夜7時から8時の夕食の時間に楽しむのが限度と考え、それ以降のいわゆる「寝酒」は避けるべきでしょう。健康的な体型を維持するためには、飲む時間帯を意識することが非常に重要なのです。



へぇ~、体の中にそんな仕組みがあったんか。知らんかったわ。これからは時間もちゃんと考えて、体に優しく飲まなあかんな。
美味しくて止まらなくなる対処法はある?
にごり酒の濃厚な甘みとコクは、一度飲むと「もう一杯」とつい手が伸びてしまう魅力があります。しかし、ダイエットや健康を考える上では、この「止まらなくなる」状況をコントロールすることが不可欠です。意志の力だけで我慢するのではなく、いくつかの具体的な対処法を実践することで、飲み過ぎを防ぐことが可能になります。
1. 和らぎ水を徹底する
最も効果的で基本的な対処法が、「和らぎ水」を飲むことです。にごり酒を一口飲んだら、必ず同量以上の水を飲む、というルールを自分に課しましょう。これにより、口の中がリフレッシュされるだけでなく、胃が水分で満たされるため、満腹感を得やすくなります。また、血中アルコール濃度の上昇が緩やかになり、酔いの回りが遅くなることで、冷静に飲む量をコントロールしやすくなるというメリットもあります。チェイサーとして、ただの水だけでなく、無糖の炭酸水やお茶を用意するのも良いでしょう。
2. 小さな酒器を選ぶ
大きなグラスや徳利で飲むと、一度に注ぐ量が多くなり、無意識のうちに飲むペースも速くなりがちです。そこで、お猪口(おちょこ)や盃(さかずき)のような、容量の小さな酒器を使ってみてください。一杯一杯、丁寧に注いで飲むという行為が間に入ることで、飲むこと自体に時間がかかり、少量でも満足感を得やすくなります。視覚的にも「何杯も飲んだ」という感覚が得られ、心理的なストッパーにもなり得ます。
3. 最初に飲む量を決めておく
「今日はここまで」と、その日に飲む上限をあらかじめ決めておくことも有効です。例えば、「この小瓶1本だけにしよう」「徳利一合分だけにしよう」と具体的に決め、それ以上は冷蔵庫から出さない、注がないといった物理的な制限を設けます。漠然と飲み始めるのではなく、ゴールを明確にすることで、セルフコントロールがしやすくなります。
4. 味わうことに意識を集中する
ただ喉の渇きを潤すように飲むのではなく、にごり酒の持つ繊細な風味をじっくりと堪能することに意識を向けてみましょう。香り、舌触り、お米の甘みの広がり、後味のキレなど、五感をフルに使って分析するように味わうのです。このように「飲む」という行為を「テイスティング」という体験に変えることで、一杯に対する満足度が格段に上がり、量を求めなくても心が満たされるようになります。
これらの対処法を組み合わせることで、にごり酒の美味しさを楽しみつつも、健康的な飲酒習慣を身につけることが可能になるでしょう。



これええやん!気合で我慢するんやなくて、道具とか飲み方でコントロールするんやな。賢いわ~!これならできそうや!
ダイエット中のおすすめお酒3選


ダイエット中にどうしてもお酒が飲みたいけれど、にごり酒のカロリーや糖質が気になる、という方は、より太りにくい特性を持つ他のお酒に目を向けるのが賢明な選択です。ここでは、ダイエット中でも比較的安心して楽しめるおすすめのお酒を3種類ご紹介します。
1. 焼酎・ウイスキーなどの「蒸留酒」
ダイエット中のお酒として最も推奨されるのが、焼酎、ウイスキー、ウォッカ、ジンといった蒸留酒です。これらのお酒は、製造過程で糖質が完全に除去されるため、糖質はゼロです。糖質を摂取すると血糖値が上昇し、インスリンの働きで脂肪が蓄積されやすくなるため、糖質ゼロであることはダイエットにおいて非常に大きなメリットとなります。
ただし、カロリーは決して低くないため、飲み方には工夫が必要です。ロックやストレートではなく、水割りやお湯割り、無糖の炭酸水で割るハイボール、ウーロン茶や緑茶で割るお茶割りなど、糖質を含まない割り材で楽しむのが基本です。
2. 辛口の日本酒(清酒)
「日本酒の風味は好きだけれど、にごり酒は避けたい」という方には、一般的な清酒の中でも「辛口」タイプがおすすめです。
日本酒の甘口・辛口の目安となる「日本酒度」という指標があり、この数値がプラスになるほど糖分が少なく辛口、マイナスになるほど糖分が多く甘口とされています。つまり、日本酒度が「+5」や「+10」といった辛口の日本酒を選べば、甘口のものやにごり酒に比べて糖質の摂取量を抑えることができます。キリリとした飲み口で食事にも合わせやすく、満足感も得やすいでしょう。
3. 糖質ゼロ・カロリーオフの「機能性アルコール」
最近では、健康志向の高まりを受け、大手酒造メーカーから「糖質ゼロ」や「カロリーオフ」を謳った日本酒やビールが数多く販売されています。
これらの商品は、独自の製法や技術によって、味わいをできるだけ損なわずに糖質やカロリーを大幅にカットしているのが特徴です。スーパーやコンビニでも手軽に購入できるため、日々の晩酌に取り入れやすいという利点があります。味わいはスッキリとしたものが多いため、濃い味のお酒が好きな方には物足りなく感じるかもしれませんが、ダイエット中の選択肢としては非常に有力です。
これらの太りにくいお酒を選ぶことで、お酒を完全に我慢するストレスから解放され、ダイエットをより長く、健康的に続けるための一助となるでしょう。



にごり酒以外にも、楽しめるお酒がいっぱいあるんやな!選択肢があると気持ちが楽になるわ~。今度スーパーで探してみよ!
【総まとめ】にごり酒は太る?飲み方次第で楽しめる
この記事では、にごり酒が太りやすいとされる理由から、具体的な対策までを詳しく解説してきました。最後に、今回の重要なポイントをまとめます。
- にごり酒が太るとされる主な原因は、製造工程で残される「もろみ」にある
- もろみには米由来の糖質や栄養素が豊富に含まれている
- にごり酒は一般的な日本酒(清酒)よりもカロリー・糖質共に高い傾向
- ある情報では、にごり酒1合(180ml)で約300kcalに達する場合もあるとされる
- 他のお酒と比較しても、にごり酒は「高カロリーかつ高糖質」な部類に入る
- ビールやワイン等の醸造酒よりカロリーが高く、糖質も多い
- 焼酎やウイスキー等の蒸留酒は糖質ゼロだが、にごり酒は糖質を多く含む
- にごり酒1合分のカロリー消費には、約30分のジョギングが必要な場合がある
- アルコールと糖質の同時摂取は、肝臓への負担を増大させ脂肪肝のリスクを高める
- ダイエット中に飲む場合は、飲む量を厳格に管理し、食事のカロリー調整が必須
- 太る飲み方は、空腹時の一気飲みや高カロリーなおつまみとの組み合わせ
- 太りにくい飲み方の鍵は、食事と一緒にゆっくり飲み、和らぎ水を徹底すること
- おつまみは冷奴や枝豆など、高タンパク・低糖質なものが適している
- 夜寝る前の飲酒は、脂肪を溜め込むタンパク質「BMAL1」の働きで太りやすい
- 飲酒は就寝の3時間以上前に終えるのが理想的
- 飲み過ぎを防ぐには、小さな酒器を使ったり、最初に飲む量を決めたりするのが有効
- ダイエット中の代替酒としては、糖質ゼロの蒸留酒や辛口の日本酒がおすすめ



よう分かったわ。ただ我慢するんやなくて、ちゃんと知識を持って賢く付き合うのが大事なんやな。これで心置きなく楽しめるわ、ありがとう!


・メンタルを整える本を紹介-1.png)






