こんにちは。ユキフルの道、運営者の「ゆう」です。
朝食のトーストに欠かせない、いちごジャム。
あの甘酸っぱさが美味しいんですよね。
でも、ふと「いちごジャムって、もしかして太る?」と心配になったことはありませんか。
特にダイエット中は、大さじ1杯のカロリーや糖質が気になりますし、「毎日食べたらどうなるんだろう…」と不安になるかもしれません。
ジャムとヨーグルトの組み合わせは定番ですが、それも大丈夫なのか、砂糖不使用タイプなら平気なのか、その太る理由や太らない食べ方があるなら知りたいですよね。
この記事では、そんないちごジャムに関する疑問を、私なりに調べて分かったことをまとめてみました。
なぜ太ると言われるのか、そしてどうすれば美味しく付き合っていけるのか、そのヒントが見つかるかもしれません。
- いちごジャムが太ると言われる科学的な理由(カロリー、糖質、メカニズム)
- 市販ジャムに潜む見落としがちな「異性化糖」のリスク
- 「太る」を回避するための具体的なジャムの選び方(原材料チェック)
- 体重管理中でもOKなジャムの賢い食べ方(組み合わせやタイミング)
いちごジャムは太ると言われる理由

まず、なぜ「いちごジャムは太る」と言われてしまうのか、その根本的な理由を探っていきます。単に「甘いから」というイメージだけではなく、その栄養成分や、食べた後に体の中でどういう働きをするのかが深く関係しているみたいですね。
特に気になるカロリーや糖質量、そして最近よく耳にする「異性化糖」というものについても、少し詳しく見ていきたいと思います。
いちごジャムのカロリーと糖質
いちごジャムが太ると言われる最大の理由は、やっぱりそのカロリーと糖質の圧倒的な高さにあるかなと思います。
私が見たあるデータ(一般的な高糖度ジャムの例)によると、なんと製品100gあたり約62gが糖質だそうです。製品重量の半分以上が糖質…と考えると、これはちょっと衝撃的ですよね。
もちろん、商品によってこの数値は変動します。例えば「低糖度」をうたったマーマレードでも、100gあたりの炭水化物(糖質)は47.7gほど。低糖度と言っても、製品の約半分が糖質であることには変わりなく、かなりの量が含まれているのが現実です。
ジャムの栄養的な特徴は、タンパク質や脂質がほぼゼロで、カロリーの源がほぼ全て糖質に極端に集中している点です。これが「カロリーの質」として、体重増加に直結しやすいポイントかもしれません。
そもそもなぜジャムは高糖度なの?
「太る」と分かっているのに、なぜこんなに砂糖(糖質)が多いのかというと、ジャムが元々「保存食」だからなんですね。
砂糖には、食品の水分を抱え込んで微生物(カビや細菌)が利用できる水分(自由水)を減らし、腐敗を防ぐ「天然の防腐剤」としての役割があります。また、果物に含まれるペクチンを固めて、あの独特の「ゼリー状」の食感を作るためにも、高濃度の砂糖が不可欠だったんです。
つまり、ジャムがジャムであるためには、歴史的に多くの糖質が必要だった、という背景があるんですね。

100gの半分以上が糖質かぁ…。こら、ちょっと考えなあかん数字やね。知れてよかったわ!
大さじ1杯の糖質量はどれくらい?


「100gあたりと言われてもピンとこない」ですよね。わかります。私たちが実際に使う量、例えば「大さじ1杯」で見てみましょう。
一般的な高糖度のいちごジャムの場合、大さじ1杯(約21g)あたり、糖質は約13gにもなる計算です。
これ、けっこう多くないですか? 分かりやすく言うと、スティックシュガー(約3g)なら4本以上、角砂糖(約3〜4g)なら3〜4個分に相当する可能性があります。
この数値がいかに重要かというと、世界保健機関(WHO)のガイドラインが参考になります。WHOは、肥満やむし歯予防の観点から、1日の「遊離糖類(砂糖やシロップなど、食品に添加される糖)」の摂取量を、総エネルギー摂取量の10%未満、理想的には5%未満(成人で約25gに相当)に抑えることを推奨しています。(出典:甘味(砂糖)の適正摂取方法 | e-ヘルスネット(厚生労働省))
あくまで目安ですが、もし朝食のトースト1枚に塗ったジャムだけで、この1日の理想的な糖質摂取量の半分以上を消費してしまう可能性があると考えると…。「いちごジャムは太る」という心配も、栄養科学的に見て極めて妥当なものだと言えそうですね。



大さじ1杯で13gか。目安の半分と思うと、大事に食べなアカンね。量さえ守ればええんや!
いちごジャムを毎日食べたら?


じゃあ、そのジャムを「毎日」食べたらどうなるんでしょうか。
たまにのご褒美ならともかく、毎日となると話は別です。問題は、糖質を摂る「頻度」と「量」の蓄積かなと思います。
もし毎日、糖質たっぷりのジャムを摂り続けると、体が「脂肪を蓄えやすいモード」に常になってしまうかもしれません。
これは、ジャムのように吸収の早い糖質を摂ると、血糖値が急上昇しやすい(血糖値スパイク)ことに関係しています。体が慌てて「インスリン」というホルモンを大量に分泌して血糖値を下げようとするんですが、このインスリンには「余った糖を脂肪として蓄える」働きもあるんです。
毎日この血糖値スパイクとインスリンの大量分泌を繰り返すのは、やっぱり体重管理の面では避けたいところですよね。
特に、ジャムを塗るパン自体も糖質ですし、朝食セットとして甘いカフェオレやジュース、加糖ヨーグルトなどを一緒に摂っていれば、糖質オン糖質となり、1食で想定以上の糖質を摂取してしまう「組み合わせの罠」に陥りやすいのも、毎日食べるリスクを高める要因かなと思います。



毎日やと、そらアカンわな。血糖値スパイクってやつか。メリハリつけて楽しむのが賢いやり方やね!
ジャムで太るメカニズムとは
ここで、ジャムで太るメカニズムをもう少し整理してみますね。
大前提として、太る(体脂肪が増える)のは、「摂取カロリー」が「消費カロリー」を上回る状態が続くからです。
ジャムの場合、そのカロリー源はほぼ糖質です。この糖質が、体の中でどう処理されるかが鍵になります。
- ジャム(高糖質)を食べる。特に空腹時やパン(糖質)と一緒に食べる。
- 消化吸収が非常に早く、血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が急上昇(血糖値スパイク)する。
- 急上昇した血糖値を下げるため、膵臓から「インスリン」というホルモンが大量に分泌される。
- インスリンは血糖をエネルギーとして全身の細胞に送る(これが本来の役割)。
- しかし、一度に大量の糖質が来るとエネルギーとして使いきれない。
- 使い道のない余ったブドウ糖は、インスリンの働きによって脂肪細胞に運ばれ、中性脂肪として蓄えられる(これが太る原因)。
つまり、ジャムのように吸収の早い高糖質な食品は、この「脂肪蓄積スイッチ」を非常に強く、速く押してしまう食品、ということなんですね。これが、ジャムが太りやすいと言われる直接的な生化学的メカニズムみたいです。
異性化糖(果糖ぶどう糖液糖)のリスク
そして、もう一つ。私たちが「砂糖」と同じか、それ以上に気にした方がいいかもしれないのが、使われている「糖の質」です。
スーパーでジャムの原材料表示を見たとき、「果糖ぶどう糖液糖」や「ぶどう糖果糖液糖」「異性化糖」という文字を見たことはありませんか?
これらは、主にトウモロコシのでんぷんを原料として工業的に作られる液体の糖です。「天然甘味料」と表示されることもありますが、砂糖(ショ糖)とは少し性質が異なります。
果糖(フルクトース)の代謝経路
砂糖がブドウ糖と果糖が1:1で結合したものなのに対し、異性化糖はブドウ糖と果糖がバラバラの状態で含まれています。
問題は、この「果糖(フルクトース)」の代謝経路です。ブドウ糖は全身のエネルギー源となりますが、果糖は主に肝臓で代謝されます。そのため、果糖を過剰に摂取すると、肝臓での脂肪合成(中性脂肪)が促進されやすいことや、インスリンの効きを悪くする(インスリン抵抗性)を引き起こす可能性が、研究などで心配されているそうです。
砂糖よりも安価なため、ジャムだけでなく、ジュースや炭酸飲料、スポーツドリンク、お菓子、パン、ヨーグルト、ケチャップやドレッシングなど、本当に色々な加工食品に使われています。
知らぬ間の「糖質重ね食べ」に注意
一番怖いのは、この異性化糖が色々な食品に入っていることによる「組み合わせの罠」です。
例えば、
- 異性化糖入りのパンに
- 異性化糖入りのジャムを塗り
- 異性化糖入りのヨーグルト(飲料)を飲む
…なんて朝食だったら、知らず知らずのうちに、代謝的にリスクのある果糖を含む糖質を、個々の食品から想定される量を遥かに超えて大量に摂取してしまうことになりかねません。
ジャム単体で心配する以上に、この「食生活全体の総量」が、現代の食環境において体重管理を難しくしている大きな要因の一つかもしれないですね。



異性化糖…これは盲点やったわ。ジャム以外もやなんて。これからは原材料名をしっかり見るで!
「いちごジャムで太る」を防ぐ対策


ここまでは「いちごジャムは太る」と言われる理由を、ちょっと詳しく見てきました。聞けば聞くほど怖くなってしまうかもしれませんが…じゃあもう食べちゃダメなの?というと、私はそんなことはないと思います!
伝統的な保存食としての側面もありますし、何より美味しいですからね。要は「どう選んで、どう食べるか」という賢い選択と管理が大事なんだと思います。ここからは、私たちが実践できる具体的な対策を一緒に見ていきましょう。
太りにくいジャムの選び方


「いちごジャムで太る」リスクを減らす第一歩は、なんと言っても「選び方」です。値段やパッケージの雰囲気だけでなく、スーパーに行ったら、ぜひ裏面の「原材料表示」をチェックする習慣をつけてみてください。
原材料表示のチェックポイント
原材料は、含まれている量が多い順に記載されています。この順番が非常に重要です。
ジャム選びのチェックリスト
- 危険信号:「異性化糖」を避ける まず確認したいのが、「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」「異性化糖」が入っていないか。これらが原材料の最初の方に書かれている製品は、私はなるべく避けるようにしています。
- 順番:「果物」が先頭か 次に確認するのが、「砂糖」よりも先に「いちご(果物)」が来ているかどうかです。「砂糖」が一番最初に来ているジャムは、それだけ多くの砂糖が使われている(=果肉より砂糖が多い)ということになります。
- 最善策:「代替甘味料」を選ぶ 体重管理を本気で考えるなら、砂糖の代わりに「アガベシロップ」のような低GI甘味料や、「エリスリトール」「ラカント」のような非カロリー甘味料を使ったものがベストな選択肢になるかなと思います。
ちなみに、「低糖度」と書かれたものも、JAS(日本農林規格)では糖度40%以上55%未満のものなどを指すようですが、高糖度品(60%以上など)よりはマシ、というレベルです。それでも糖質が多いことには変わりないので、やっぱり原材料を見て判断するのが確実ですね。



なるほどな!アガベシロップとかエリスリトールか。ちゃんと選べば楽しめるんやん!希望が見えてきたわ!
砂糖不使用ジャムのメリット
先ほども触れましたが、「砂糖不使用」をうたうジャムには大きなメリットがあります。これらは大きく2タイプに分けられるかなと思いますので、それぞれの特徴を比較してみましょう。
タイプ1:低GI甘味料(アガベシロップなど)
アガベシロップなどは、GI値(食後の血糖値の上昇しやすさを示す数値)が低いのが特徴です。血糖値の急上昇(スパイク)が抑えられるということは、インスリンの過剰分泌も抑えられ、結果として脂肪が合成されにくくなる、というわけです。甘さもしっかりあるのに、体に優しい感じがしますね。水溶性食物繊維(イヌリン)を含むものもあります。
タイプ2:非カロリー甘味料(エリスリトールなど)
エリスリトールやラカント(羅漢果配糖体)、ステビアなどは、体に吸収されずに排出されるか、血糖値に影響を与えない甘味料です。つまり、実質的な糖質量はほぼゼロ。カロリーもゼロです。
ダイエット中や糖質制限中の方にとっては、これ以上ないくらい心強い味方ですよね。ただし、砂糖が持つ「保存性」や「ゼリー化」の機能は持たないため、食感を出すための増粘剤(ペクチン、キサンタンガムなど)や、保存性を高めるための保存料(ソルビン酸Kなど)が別途必要になる場合があります。このあたりは、添加物に対するご自身の考え方と好みで選ぶと良いかなと思います。
| 甘味料タイプ | 代表例 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|---|
| 低GI甘味料 | アガベシロップ | ・血糖値スパイクを抑える ・自然な甘さ | ・カロリーや糖質はゼロではない ・価格がやや高め |
| 非カロリー甘味料 | エリスリトール、ラカント | ・カロリー/糖質ほぼゼロ ・血糖値に影響しない | ・独特の風味や冷涼感がある場合も ・添加物(増粘剤など)が必要な場合がある |
ヨーグルトと食べる時の注意点


いちごジャムとヨーグルト、定番の組み合わせですよね。私も大好きです。
実は、この組み合わせは栄養的にも良い面があります。ヨーグルトに含まれるタンパク質や脂質と一緒に摂ることで、胃での消化吸収が遅らされ、ジャム単体で食べるよりも血糖値の上昇が緩やかになる効果が期待できるんです。これは良いニュースですよね!
ただし、最大の注意点は「組み合わせるヨーグルト」です。
せっかくジャムを低糖質のものにしても、ヨーグルト自体が「加糖タイプ」や「果糖ぶどう糖液糖」入りのものだったら、結局、大量の糖質を摂ることになってしまいます。これは本当に避けたい「組み合わせの罠」です。
おすすめは、必ず「無糖」や「プレーン」のヨーグルトを選ぶこと。これ、鉄則かなと思います。タンパク質が豊富なギリシャヨーグルトの無糖タイプなども、食べ応えがあって良いですね。
ヨーグルトの健康効果については、以前に「ヨーグルトのすごい効果とは?毎日食べるときのポイント」という記事でも触れたので、よかったらそちらも参考にしてみてくださいね。(※外部サイト(ユキフルの道)へ移動します)



そらそうや!ヨーグルトが甘かったら意味ないもんな。無糖ヨーグルトと合わせる。これ、鉄則やね!
パンに塗るなら全粒粉がマシ?
ジャムといえば、やっぱりパン。でも、このパンの選び方もすごく重要です。
フワフワの白い食パンは、精製された小麦粉からできていてGI値が高く、それ自体が血糖値を急上昇させやすい食品です。そこに高糖度のジャムを塗るのは、まさに「糖質 on 糖質」の、最も太りやすい組み合わせと言えるかもしれません。
そこでおすすめなのが、「全粒粉パン」や「ライ麦パン」です。
これらは「全粒粉(ぜんりゅうふん)」という、表皮や胚芽を取り除いていない小麦粉から作られています。そのため、食物繊維が非常に豊富で、GI値も白いパンより低い傾向にあります。食物繊維が糖の吸収を遅らせてくれるので、血糖値の上昇が緩やかになることが期待できます。
もちろん、全粒粉パンでも食べ過ぎはダメですが、どうせ食べるなら、こうした「マシ」な選択(ベターな選択)を積み重ねるのが大事かなと思います。ビタミンやミネラルも豊富ですしね。
全粒粉パンがなぜ良いのかについては、全粒粉パンの記事も書いているので、よかったらどうぞ。
食べるタイミングは朝がベスト
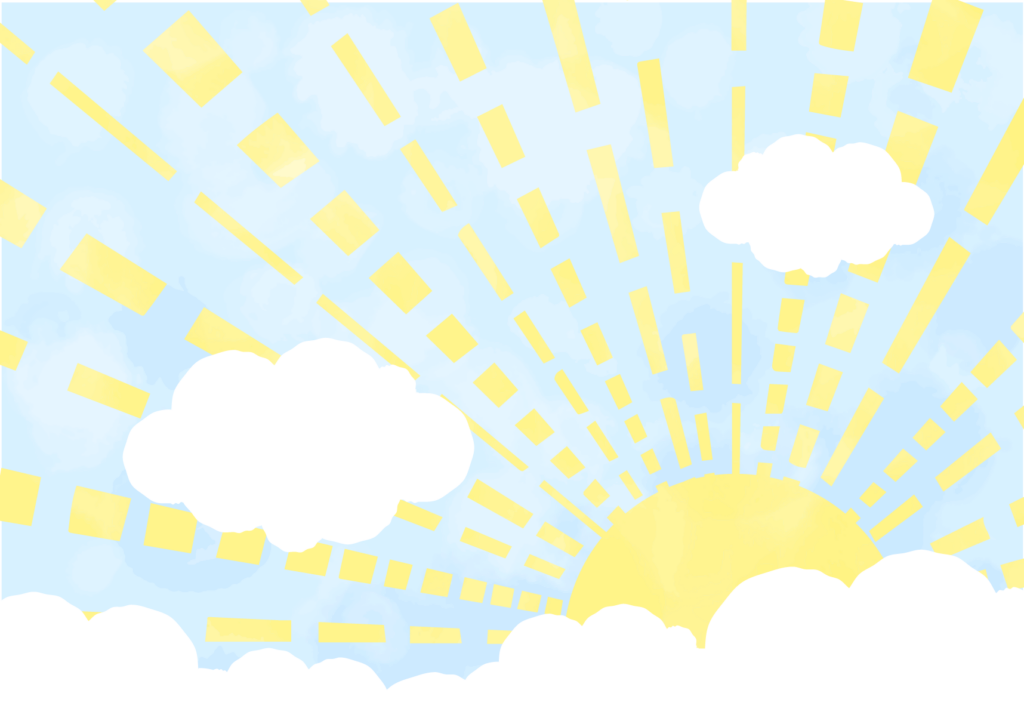
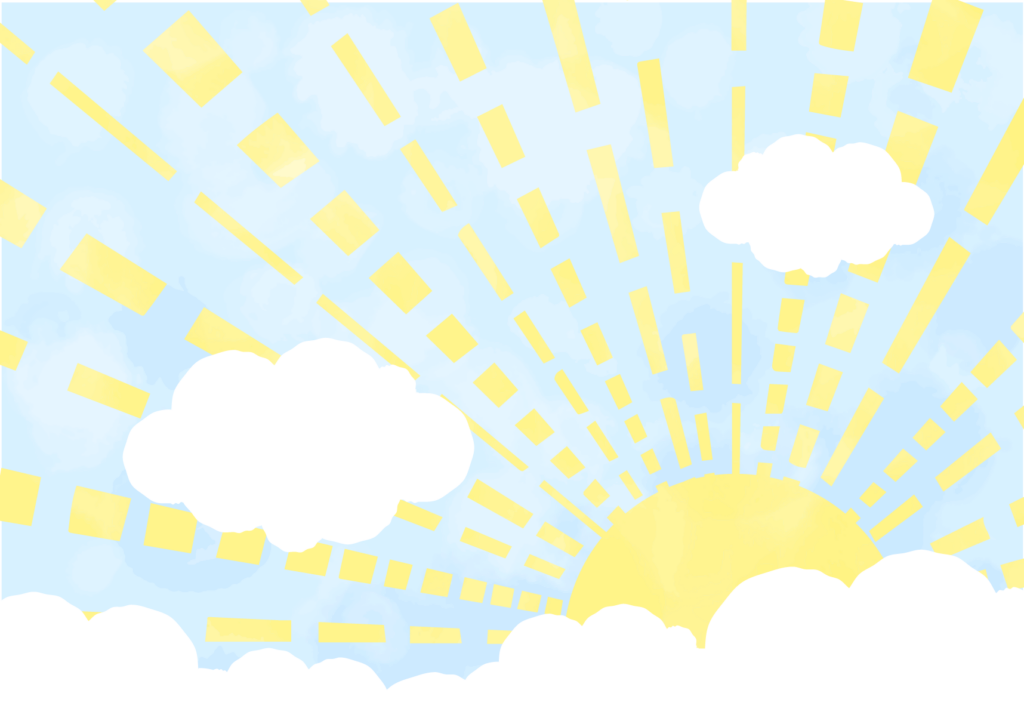
「いつ食べるか」も、地味に重要です。
ジャムの糖質は、素早いエネルギー源になるのが特徴です。ということは、これから活動するぞ!という「朝食」に摂るのが一番理にかなっていますよね。日中の活動でエネルギーとして消費されやすいからです。脳のエネルギー源はブドウ糖ですから、朝のスイッチを入れるという意味でも合理的です。
逆に、最も避けたいのは「夜」。特に寝る前に食べることです。
夜間は、体に脂肪を溜め込む働きをする「BMAL1(ビーマルワン)」というタンパク質が増える時間帯と言われています。そんなタイミングで糖質を摂ると、摂取したエネルギーが消費されず、インスリンとBMAL1の働きによって、そのまま体脂肪として蓄積されやすくなってしまいます。
「お風呂上がりの甘いもの…」は最高ですが、体重が気になる時はグッと我慢ですね。もし摂るなら、運動直後のエネルギー補給(リカバリー)として少量摂る、というのも一つの手かもしれません。
【総括】いちごジャムは太るか
さて、色々見てきましたが、「結局、いちごジャムは太るのか?」という問いへの私なりの結論です。
答えは、「YESでもあり、NOでもある」かなと思います。
YESの理由(太る理由)
伝統的なジャムは製品の半分以上が糖質ですし、現代の市販品には肥満リスクが懸念される異性化糖が使われていることもあります。何も考えずに、精製された白いパンにたっぷり塗って毎日食べていれば、太る原因になる可能性は非常に高いです。
NOの理由(太らないための道筋)
ジャムは「敵」ではなく、上手に「管理」すべき嗜好品だと私は思います。糖質が迅速なエネルギー源になるという側面も事実ですからね。
大切なのは、その特性を理解し、リスクを最小限に抑える工夫をすることです。
「いちごジャムで太る」のを避ける3つの心得
体重増加を避けながらジャムを楽しむためには、以下の3つの防衛策を講じることが、私なりの結論です。
- 選ぶ (Select): 「高糖度・異性化糖」の製品を避け、「低GI(アガベシロップなど)」や「非カロリー(エリスリトールなど)」の甘味料を使用した製品を賢く選択すること。
- 管理する (Manage): 摂取量を「大さじ1杯まで」など、厳格に管理すること。どれだけ健康的なジャムでも、食べ過ぎればカロリーオーバーに繋がります。
- 組み合わせる (Pair): 血糖値の急上昇を避けるため、無糖ヨーグルト(タンパク質)や全粒粉パン(食物繊維)と組み合わせ、糖質との「組み合わせの罠」を回避すること。
これらの知識武装こそが、「いちごジャム 太る」という懸念に対する最も効果的な処方箋になるんじゃないかな、と私は思います。
健康に関する重要なご注意
この記事で紹介した情報は、あくまで私個人が調べた範囲での一般的なものであり、特定の健康効果やダイエット効果を保証するものではありません。数値データなども、すべて目安としてお考えください。
特に糖尿病などで血糖値の厳格な管理をされている方や、治療の一環として体重管理が必要な方、その他健康に関して不安のある方は、ご自身の判断で行わず、必ずかかりつけの医師や管理栄養士といった専門家にご相談くださいね。

・メンタルを整える本を紹介-1.png)



