「寝る前に納豆を食べると太る」という話を聞いたことはありませんか。
日本の食卓に欠かせない健康食品として知られる納豆ですが、夜に食べることに対して漠然とした不安や疑問を抱いている方も多いようです。
テレビや雑誌ではその栄養価が頻繁に取り上げられる一方で、食べるタイミングによっては逆効果になるのでは、という声も聞こえてきます。この記事では、そうした「寝る前に納豆を食べると太る」という噂の真相に、科学的根拠を基に深く迫ります。
夜、小腹が空いたときに納豆を選ぶことは、果たしてダイエット中にありなのか、それとも知らず知らずのうちに失敗や後悔へとつながる選択なのでしょうか。
納豆の正確なカロリーや糖質、そして他の食品とのカロリー比較を通じて、太る原因となり得るメカニズムを解明していきます。
さらに、ただ単に太るか否かだけでなく、食べ過ぎると体に悪いのかという健康面でのリスクや、夜寝る前に食べると太るなら一体何時までが許容範囲なのか、といった具体的な時間にも言及します。
太る食べ方と太りにくい食べ方の本質的な違いを理解し、納豆のダイエット効果を最大限に引き出す痩せる組み合わせも詳しくご紹介します。
この記事を最後まで読めば、夜の納豆との付き合い方が明確になり、不安なく食生活に取り入れられるようになるはずです。
- 寝る前に納豆を食べると太るとされる本当の原因
- 納豆のカロリーや栄養素がダイエットに与える影響
- 夜に納豆を食べる際の太りにくい食べ方や適切な時間帯
- ダイエット効果を最大限に引き出すための食材の組み合わせ
「寝る前(夜)に納豆を食べると太る」は本当?

- 納豆の食べ方による太る原因とは
- 納豆のカロリー・糖質はどのくらい?
- 他の食品とのカロリー比較で見る納豆
- 納豆のカロリーを消費するための運動量
- 納豆は食べ過ぎると体に悪い?
納豆の食べ方による太る原因とは

納豆は、その栄養価の高さと低カロリー・低糖質という特性から、本来ダイエットに適した食品です。したがって、納豆そのものが直接的に体重増加を引き起こす主犯である、と考えるのは早計です。しかしながら、特定の条件下では、納豆が太る一因となる可能性は否定できません。その原因は、納豆自体ではなく、私たちの「食べ方」に潜んでいます。
主な原因として挙げられるのは、「食べる量」「組み合わせる食材」、そして「食べる時間帯」の三つです。
まず「食べる量」についてです。「体に良いから」という安心感から、つい量を過ごしてしまうのはよくある落とし穴です。納豆1パックのカロリーは約95kcalですが、これが3パックになれば約285kcalとなり、軽めのご飯一膳分に相当します。摂取カロリーが消費カロリーを上回れば、体脂肪は増えていきます。これは納豆に限らず、あらゆる食品に共通する原則です。
次に「組み合わせる食材」です。特に問題となるのが、白米などの糖質を多く含む主食との組み合わせです。納豆ご飯は非常に美味しい組み合わせですが、夜遅い時間に大量の白米と一緒に食べると、血糖値が急上昇します。これを下げるために分泌されるインスリンというホルモンは、余った糖を脂肪として体内に蓄える働きを促進してしまうのです。
最後に「食べる時間帯」が大きく関わってきます。私たちの体は、夜間になるとエネルギー消費量が低下し、休息モードに入ります。このタイミングで食事をすると、日中のようにエネルギーとして消費されにくく、脂肪として蓄積されやすくなります。
言ってしまえば、納豆で太るという現象は、これらの要因が複合的に絡み合った結果生じるものです。「納豆の過剰摂取」「高糖質な食材との組み合わせ」「夜遅い時間の食事」という食習慣こそが、根本的な原因であると理解することが大切です。

なるほどな、納豆自体は悪ないんや。食べ方をちょっと気ぃつければええだけの話やったんやな。
納豆のカロリー・糖質はどのくらい?


体重管理を行う上で、食品の正確なカロリーと糖質量を把握しておくことは基本中の基本です。納豆がダイエットにおいてどのような位置づけになるのか、具体的な数値を通して見ていきましょう。
文部科学省が公表している「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」を参照すると、糸引き納豆100gあたりの栄養価は以下のようになっています。
- エネルギー:190 kcal
- たんぱく質:16.5 g
- 脂質:10.0 g
- 炭水化物:12.1 g
- うち糖質:5.4 g
- うち食物繊維:6.7 g
市販されている納豆は1パックあたり45g〜50gが一般的ですので、これを50gに換算すると、より実践的な数値が見えてきます。
| 項目 | 1パック(約50g)あたりの目安 | 主な働き |
| エネルギー(カロリー) | 約95 kcal | 活動のためのエネルギー源 |
| たんぱく質 | 約8.3 g | 筋肉や肌、髪の材料となる |
| 脂質 | 約5.0 g | 細胞膜の構成やホルモンの材料となる |
| 糖質 | 約2.7 g | 主要なエネルギー源 |
| 食物繊維 | 約3.4 g | 腸内環境を整え、血糖値の上昇を穏やかにする |
| ビタミンK | 300 µg | 骨の健康維持や血液凝固に関わる |
| ビタミンB2 | 0.28 mg | 脂質の代謝を助け、エネルギー産生をサポートする |
| 鉄 | 1.65 mg | 全身に酸素を運ぶ赤血球の材料となる |
| マグネシウム | 50 mg | 多くの酵素反応を助け、筋肉の収縮を調整する |
このように、1パックあたりのカロリーは約95kcalと、ご飯一膳(約150gで234kcal)の半分以下に抑えられています。糖質も非常に少ない一方で、筋肉の材料となるたんぱく質や、ダイエット中に不足しがちなビタミン、ミネラルを豊富に含んでいることが大きな特長です。
付属のタレには注意が必要
納豆自体の糖質は低いものの、多くの製品に付属している「タレ」には注意が必要です。原材料表示を見ると、「果糖ぶどう糖液糖」や「砂糖」といった糖類が上位に記載されていることが少なくありません。このタレを全て使うと、数グラムの糖質を追加で摂取することになります。
ダイエットをより意識するならば、タレの使用量を半分に減らす、あるいは使用せずにお酢、ポン酢、だし醤油、めんつゆなどで代用するのがおすすめです。こうした小さな工夫が、長期的に見ると大きな差となって現れます。



カロリーも糖質もこないに低いんやったら、安心して食べられるわ。タレだけは、まあ、ちょっと控えめにしとこか!
他の食品とのカロリー比較で見る納豆


納豆が持つカロリーの価値を客観的に評価するためには、他のたんぱく質源となる食品と比較することが有効です。ここでは、スーパーマーケットで手軽に入手できる代表的な食品と、100gあたりのカロリーを比較してみましょう。
| 食品名 | 100gあたりのエネルギー (カロリー) | 特徴 |
| 納豆(糸引き) | 190 kcal | 植物性たんぱく質、食物繊維、発酵食品 |
| 鶏ささみ(生) | 98 kcal | 低脂肪・高たんぱくの代表格 |
| 鶏卵(全卵・生) | 142 kcal | バランスの取れた栄養素、良質なたんぱく質 |
| 鶏もも肉(皮つき・生) | 190 kcal | 脂質も適度に含み、ジューシーな味わい |
| 豚ロース肉(脂身つき・生) | 248 kcal | 脂質が多く、カロリーは高め |
| 木綿豆腐 | 73 kcal | 低カロリーでかさ増しにも向く大豆製品 |
| 鮭(しろさけ・生) | 124 kcal | 良質な脂質(EPA・DHA)を含む |
この表から、納豆のカロリーは皮つきの鶏もも肉と同程度であることがわかります。一方で、豆腐や鶏ささみよりは高く、脂質の多い豚肉よりは低いという、中間的な位置にいることが見て取れます。
ここで考えたいのは、カロリーの「質」です。例えば、納豆と鶏もも肉のカロリーは同じでも、納豆には鶏肉にはない「食物繊維」や「納豆菌」といった腸内環境を整える成分が含まれています。また、大豆イソフラボンやビタミンKなど、独自の健康効果を持つ栄養素も豊富です。
このように、単なる数値の比較だけでなく、その食品が持つ多面的な価値を理解することが大切です。夕食のメインを豚肉から納豆を活用した料理に置き換えるなど、賢く選択することで、カロリーを抑えつつ、より多くの健康メリットを享受することが可能になります。



鶏もも肉と同じくらいで、食物繊維もとれるなんて、めっちゃお得やんか!これは賢く使わなあかんな。
納豆1パックのカロリーを消費するための運動量


納豆1パック(約95kcal)は、食事全体から見れば比較的低カロリーです。しかし、「塵も積もれば山となる」という言葉があるように、このカロリーが体にどのような影響を与えるのかを運動量に換算して理解しておくことは、健康的な食生活を送る上で非常に有益です。
では、納豆1パック分の約95kcalを消費するためには、具体的にどの程度の運動が必要になるのでしょうか。ここでは、体重60kgの成人を基準とした場合のおおよその運動時間の目安を、日常生活に取り入れやすい活動に絞ってご紹介します。
| 運動の種類 | 95kcalを消費するのに必要な時間(目安) |
| ウォーキング(やや速歩、時速4.8km程度) | 約22〜27分 |
|---|---|
| ジョギング(時速8km程度) | 約10〜14分 |
| 自転車(平地、時速15km程度) | 約15〜20分 |
| 階段の昇降 | 約8〜10分 |
※これらの数値はあくまで一般的な目安であり、個人の体重、年齢、性別、筋肉量、そしてその日の体調によって消費カロリーは変動します。
このように、ヘルシーなイメージのある納豆1パック分であっても、そのカロリーを消費するためには決して無視できない時間の運動が必要になることがわかります。
しかし、ここで最も考えたいのは、そのカロリーの「質」です。納豆から摂取する95kcalには、筋肉や血液の材料となる良質なたんぱく質、エネルギー代謝を円滑にするビタミンB群、そして腸内環境を整える食物繊維や納豆菌といった、体を内側からサポートする栄養素が豊富に含まれています。
これは、同程度のカロリーを持つお菓子やスナック類の「エンプティカロリー(栄養素が空っぽのカロリー)」とは本質的に異なります。納豆を食べることは、単なるエネルギー補給に留まらず、自身の体への価値ある投資と考えることができるでしょう。
納豆は食べ過ぎると体に悪い?
「体に良い」というイメージが強い納豆ですが、任何食品も「過ぎたるは猶及ばざるが如し」です。過剰な摂取は、かえって健康上のリスクを引き起こす可能性があります。納豆を食べ過ぎた場合に考えられる主なデメリットを理解しておきましょう。
プリン体の過剰摂取による痛風リスク
納豆には、旨味成分の一つであるプリン体が含まれています。プリン体は体内で分解されると尿酸を生成します。この尿酸が血液中で過剰になると、関節で結晶化して激しい痛みを引き起こす「痛風」を発症するリスクが高まります。
納豆1パック(約50g)に含まれるプリン体は約57mgとされています。日本痛風・核酸代謝学会のガイドラインでは、高尿酸血症・痛風の患者におけるプリン体の摂取量を1日400mg以内に制限することが推奨されています。もちろん、健康な方が納豆を食べるだけでこの数値を超えることは考えにくいですが、日常的に飲酒量が多い方や、肉・魚介類を多く食べる方は、納豆の食べ過ぎが重なるとリスクを高める可能性があるため注意が必要です。
栄養バランスの偏り
納豆は多くの栄養素を含みますが、完全栄養食品ではありません。例えば、皮膚や粘膜の健康を保つビタミンA、抗酸化作用のあるビタミンC、カルシウムの吸収を助けるビタミンDなどはほとんど含まれていません。納豆ばかりを食べるような偏った食生活を送っていると、これらの重要な栄養素が不足し、思わぬ体調不良を招くことがあります。
特定の持病がある場合の注意点
納豆に豊富に含まれる不溶性食物繊維は、便のかさを増やして腸を刺激するため、一般的な便秘には効果的です。しかし、ストレスなどが原因で腸が過敏に痙攣する「痙攣性便秘」の方が摂り過ぎると、かえって症状を悪化させることがある、という情報もあります。
カロリーオーバーの可能性
前述の通り、納豆は決してゼロカロリーではありません。1パック約95kcalというカロリーを念頭に置かず、「ヘルシーだから大丈夫」と1日に3パックも4パックも食べていれば、簡単にカロリーオーバーにつながります。
これらの理由から、納豆の摂取量は1日1〜2パック程度を目安とし、多様な食品と組み合わせたバランスの良い食事を心がけることが、健康を維持する上で最も賢明な方法と言えます。



なんでも食べ過ぎはあかんってことやな。1日1パックか2パック、美味しくいただくのが一番や。
寝る前(夜)の納豆、太るのを避ける食べ方


- 夜の納豆はダイエット中にあり?なし?
- 夜寝る前に食べると太る?何時間前までならOK
- 太る食べ方・太りにくい食べ方の違い
- ダイエット効果を高める痩せる組み合わせ
- 寝る前の納豆で期待できる美肌などの効果
- 寝る前(夜)の納豆で太るかの結論
夜の納豆はダイエット中にあり?なし?
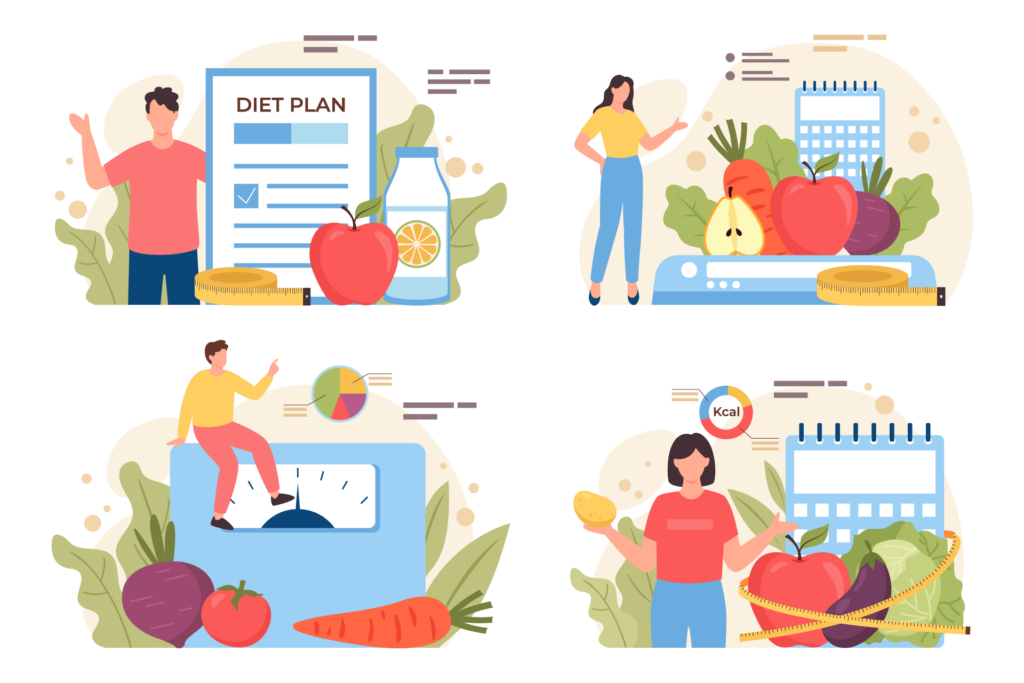
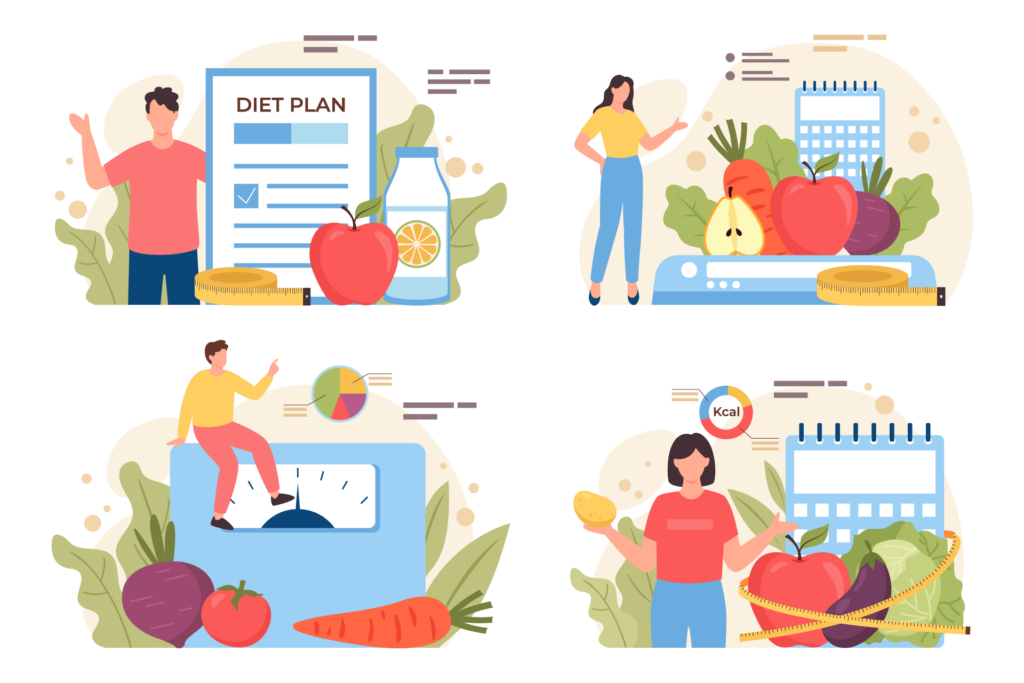
結論から言うと、夜に納豆を食べることはダイエット中においても「あり」であり、むしろ戦略的に取り入れることで多くのメリットを享受できます。夜間の体のメカニズムを考えると、納豆に含まれる特定の栄養素が非常に効果的に作用するためです。
成長ホルモンの分泌をサポートし、脂肪燃焼を促進
私たちの体は、睡眠中に「成長ホルモン」を分泌します。このホルモンは、体の修復や再生を担うだけでなく、脂肪を分解する強力な作用を持っています。納豆に含まれるアミノ酸の一種である「アルギニン」は、この成長ホルモンの分泌を促進する働きがあることが知られています。特に、成長ホルモンは就寝後、最初の深い眠り(ノンレム睡眠)の際に最も多く分泌されるため、夕食でアルギニンを補給しておくことは、睡眠中の脂肪燃焼を効率化する上で理にかなっています。
睡眠の質を高める効果
納豆には、「トリプトファン」という必須アミノ酸も豊富に含まれています。トリプトファンは、体内で精神を安定させる「セロトニン(幸せホルモン)」という神経伝達物質の材料となります。そして、このセロトニンは夜になると「メラトニン(睡眠ホルモン)」に変化し、自然な眠りを誘います。つまり、夕食に納豆を食べることは、質の高い睡眠を得るための準備にもつながるのです。良質な睡眠は、食欲をコントロールするホルモンバランスを整えるため、ダイエットの成功に不可欠です。
血流を改善し、代謝をサポート
納豆特有の酵素である「ナットウキナーゼ」は、血液をサラサラにし、血栓を溶解する働きがあります。血栓は、活動量が低下する深夜から早朝にかけて形成されやすいという性質があるため、夕食時にナットウキナーゼを摂取しておくことで、就寝中の血流をスムーズに保つ効果が期待できます。血行が促進されると、全身の細胞に酸素や栄養が届きやすくなり、基礎代謝の維持・向上にも貢献します。
このように、夜に納豆を食べることは、睡眠中の体の働きを多角的にサポートし、ダイエットを有利に進めるための賢い選択肢となり得るのです。



え、夜に食べた方がええ効果もあるんか!寝てる間にええ仕事してくれるなんて、納豆えらすぎるやろ…。
夜寝る前に食べると太る?何時間前までならOK
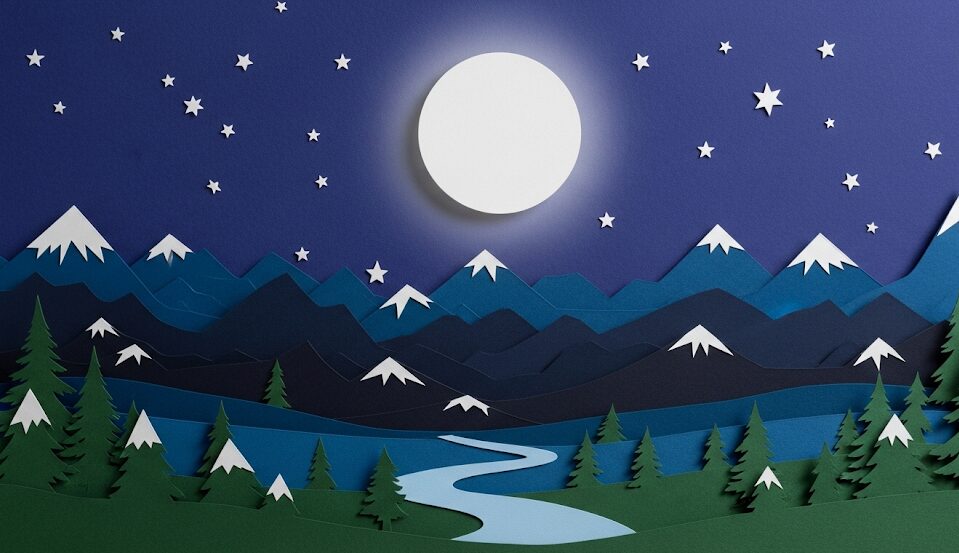
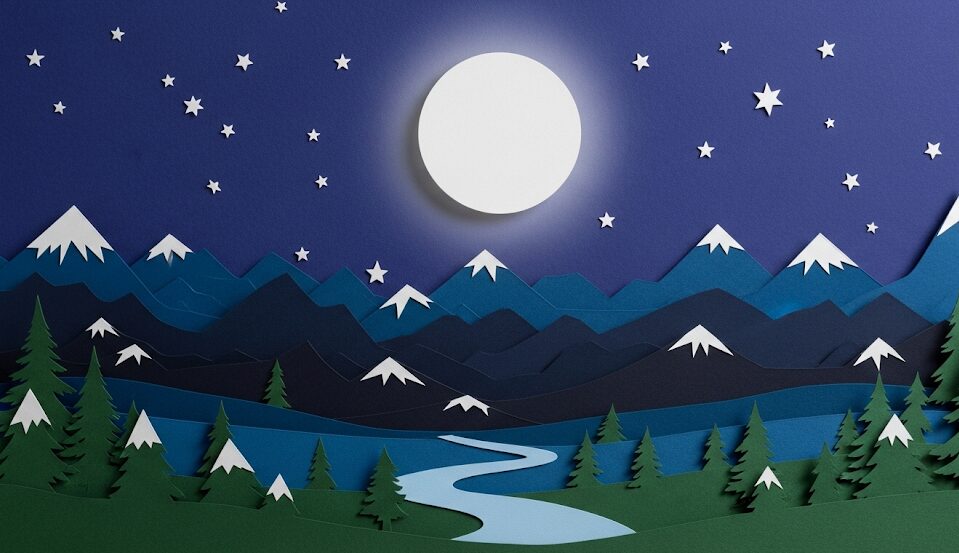
夜に納豆を食べることのメリットは大きいですが、体重増加を避けるためには「いつまでに食べるか」というタイミングが決定的に重要になります。
私たちの体には「BMAL1(ビーマルワン)」という、脂肪の蓄積を促進するたんぱく質が存在します。このBMAL1は、時間帯によって体内の量が変動し、夜10時から深夜2時にかけて最も増加することが分かっています。つまり、この時間帯は「食べたものが最も脂肪に変わりやすい魔の時間帯」と言えるのです。
この体のリズムを考慮すると、理想的な食事時間は、就寝する3時間前まで、とされています。例えば、夜11時に就寝する方であれば、夜8時までには夕食を済ませておくのがベストです。これにより、食べたものが消化・吸収され、血糖値が落ち着いた状態で眠りにつくことができます。
納豆を食べる際は、この原則に従い、夕食の一品として取り入れるのが最も安全で効果的です。もし、夕食後どうしてもお腹が空いてしまい、夜食として納豆を食べたい場合でも、できる限り就寝の2時間前までには食べ終えるようにしましょう。そして、その際はご飯などは加えず、納豆単品で食べることを徹底するのが賢明です。
「何時まで」という問いに対する答えは、「就寝の3時間前までが理想、遅くとも2時間前まで」と覚えておくと良いでしょう。



なるほど、寝る3時間前か。体のリズムに合わせるんが大事なんやな。これなら覚えやすいわ。
太る食べ方・太りにくい食べ方の違い
同じ納豆という食材でも、その食べ方一つで、体への影響は天国と地獄ほどに変わります。ここでは、体重増加を招きやすい「太る食べ方」と、ダイエットを力強くサポートする「太りにくい食べ方」の具体的な違いを、より深く掘り下げて解説します。
太る食べ方
夜遅い時間に、温かいご飯の上に納豆を乗せて食べる「納豆ご飯」は、多くの日本人にとって至福の組み合わせですが、ダイエットの観点からは最も避けたい食べ方の一つです。この食べ方が太りやすい理由は、主に血糖値の急上昇にあります。精製された白米は糖質が多く、消化吸収が速いため、血糖値を急激に上げます。すると、体は血糖値を下げるためにインスリンを大量に分泌し、エネルギーとして使い切れなかった糖を効率よく脂肪細胞に送り込んでしまうのです。
さらに、納豆の付属のタレを全て使い、塩分の多い漬物などを一緒に食べると、塩分の過剰摂取による「むくみ」も引き起こしやすくなります。むくみは血行不良や代謝の低下を招き、痩せにくい体質を作る一因となります。
太りにくい食べ方
一方で、太りにくい食べ方の基本は、「糖質の摂取を抑え、満足感を高める工夫をする」ことです。
まず、納豆は主食としてではなく、あくまで「おかずの一品」として位置づけましょう。ご飯の代わりに、冷奴(木綿豆腐)の上に納豆を乗せる「納豆奴」は、糖質を大幅にカットしつつ、たんぱく質をしっかり補給できる優れたメニューです。
また、食事のかさを増すことも有効です。刻んだきゅうり、千切りにした大葉やみょうがといった薬味野菜、または茹でたきのこやワカメなどの海藻類をたっぷりと混ぜ込むことで、少ない量でも満腹感を得やすくなります。これらの食材は低カロリーである上に、食物繊維が豊富なので、血糖値の上昇をさらに穏やかにしてくれます。
調味料の工夫も大切です。前述の通り、付属のタレの代わりに、お酢やポン酢を使うことで、糖質と塩分をカットできます。特にお酢は、脂肪燃焼を助ける効果も期待できるため、積極的に活用したい調味料です。



白ごはんと一緒もええけど、豆腐に乗せたり野菜と混ぜたり、工夫次第でぎょうさん楽しめるんやな。賢う食べよ!
ダイエット効果を高める痩せる組み合わせ


納豆単体でも優れたダイエット食品ですが、特定の食材と組み合わせることで、その効果を相乗的に高めることができます。ここでは、科学的な根拠に基づいた、特におすすめの「痩せる組み合わせ」を3つ、詳しくご紹介します。
納豆 + キムチ:「腸活」を加速させる最強タッグ
発酵食品である納豆とキムチの組み合わせは、「腸活」の観点から見て最強のタッグと言えます。納豆に含まれる「納豆菌」は、生きたまま腸に届き、善玉菌として働く非常に強い菌です。一方、キムチに含まれる「植物性乳酸菌」もまた、胃酸に強く、腸まで届きやすいという特徴があります。
この二つの善玉菌を同時に摂取することで、腸内の善玉菌が多様化し、活発になります。近年の研究では、腸内細菌のバランスが肥満と深く関わっていることが分かっており、「ヤセ菌」とも呼ばれる特定の腸内細菌を増やすことが、痩せやすい体質作りに繋がるとされています。この組み合わせは、まさに「ヤセ菌」が好む環境を腸内に作り出す手助けをしてくれるのです。
納豆 + 酢:脂肪燃焼と血糖値コントロールの専門家
納豆にお酢を小さじ1杯程度加えて混ぜる「酢納豆」は、手軽ながら絶大な効果が期待できる組み合わせです。お酢の主成分である「酢酸」には、主に二つの嬉しい働きがあります。一つは、食後の血糖値の上昇を緩やかにする作用です。これにより、脂肪の蓄積を促すインスリンの過剰分泌を抑えることができます。
もう一つは、脂肪の燃焼を促進する働きです。酢酸は、体内で脂肪燃焼を司る酵素を活性化させることが研究で示唆されています。リンゴ酢や黒酢など、好みの風味のお酢を選ぶことで、飽きずに続けやすいのも魅力です。
納豆 + オクラやめかぶ:満足感とデトックスを担うネバネバコンビ
オクラやめかぶ、つるむらさきといったネバネバ食材と納豆の組み合わせは、満足感を高めつつ、デトックス効果を促進します。これらの食材のネバネバの正体は、「水溶性食物繊維」です。水溶性食物繊維は、胃の中で水分を吸ってゲル状に膨らむ性質があるため、満腹感が持続しやすくなります。
さらに、腸内では善玉菌のエサとなって腸内環境を整えるほか、コレステロールや糖質の吸収を穏やかにし、余分なナトリウム(塩分)を体外に排出するのを助ける働きもあります。食感のアクセントにもなり、食べ過ぎを防ぎながら、体を内側からきれいにしてくれる、一石二鳥の組み合わせです。



キムチとかお酢とか、ちょっと足すだけでえらい違いやな。明日から早速やってみよ。体の中から変われそうや!
寝る前の納豆で期待できる美肌などの効果


夜、就寝前に納豆を食べる習慣は、私たちの体が休息している間に、健康と美容の両面で多くの素晴らしい効果をもたらす可能性があります。納豆に含まれる栄養素が、睡眠中の体のメカニズムと相乗効果を生み出すためです。具体的にどのような効果が期待できるのか、一つずつ詳しく見ていきましょう。
① 睡眠中の身体の修復と成長をサポート
私たちの体は、寝ている間に日中の活動で受けたダメージを修復し、新しい細胞を作り出すメンテナンス作業を行っています。この重要なプロセスには、材料となる栄養素が不可欠です。
納豆には、筋肉や皮膚、髪の毛の主成分である良質なたんぱく質が豊富に含まれています。夕食で納豆を食べることで、この修復作業に必要な材料を体に供給し、効率的な回復を助けることができます。さらに、エネルギー代謝を円滑にするビタミンB群や、肌の健康維持に役立つビタミンEも含まれているため、翌朝のすっきりとした目覚めや、健やかな肌作りにも貢献します。
② 睡眠の質を高めるリラックス効果
質の高い睡眠は、ダイエットや健康維持の土台となります。納豆には、「GABA(ギャバ)」というアミノ酸の一種が含まれていることがあり、これが深いリラックス状態へと導いてくれます。
GABAは、脳の興奮を鎮めて神経を落ち着かせる働きを持つ神経伝達物質です。ストレスや緊張を感じていると、なかなか寝付けなかったり、夜中に目が覚めてしまったりすることがありますが、GABAを摂取することで、心身がリラックスし、穏やかな入眠と深い眠りをサポートする効果が期待できます。質の良い睡眠は、食欲をコントロールするホルモンのバランスを整える上でも非常に大切です。
③ 血液の流れを健やかに保つ
納豆のネバネバ成分に含まれる特有の酵素「ナットウキナーゼ」は、血液をサラサラに保つ働きで知られています。この酵素は、血栓(血の塊)を溶かしやすくし、血流を改善する効果が期待されています。
特に興味深いのは、ナットウキナーゼの効果は摂取してから約10時間後にピークを迎えるという点です。人の体は、活動量が減る深夜から早朝にかけて血栓ができやすいとされているため、夕食に納豆を食べることは、ちょうどそのリスクが高まる時間帯に血流を保護する、非常に理にかなった習慣と言えます。血行が促進されると、冷えや肩こりの改善、そして全身の細胞への栄養供給がスムーズになり、基礎代謝の維持にもつながります。
④抗酸化作用によるエイジングケア
私たちの体が日々浴びる紫外線やストレスは、体内で「活性酸素」を発生させ、細胞を傷つけ、老化や生活習慣病の原因となります。これを体の「サビ」と例えることができますが、納豆にはこのサビに対抗する「抗酸化物質」が豊富に含まれています。
代表的なものに、「大豆イソフラボン」や「サポニン」、そして「ビタミンE」があります。これらの成分が連携して体内の活性酸素を除去し、細胞のダメージを防いでくれます。肌の細胞が守られることで、シミやシワ、たるみといった老化サインの予防につながり、内側からのエイジングケアが期待できるのです。
寝る前(夜)の納豆で太るかの結論
この記事を通じて解説してきた「寝る前(夜)に納豆を食べると太るのか」という疑問について、最終的な要点を以下にまとめます。
- 納豆そのものが直接的な太る原因ではない
- 太るかどうかは食べる「量」「時間」「組み合わせ」で決まる
- 夜遅くに白米などの糖質と一緒に食べることが最も太りやすい原因
- 納豆1パックのカロリーは約95kcalと比較的低カロリーである
- 糖質も1パックあたり約2.7gと非常に少ない
- ただし付属の甘いタレは糖質を増やすため注意が必要
- 食べ過ぎはプリン体の過剰摂取や栄養バランスの偏りを招く
- 健康的な摂取目安は1日に1〜2パック程度
- 夜に食べることは成長ホルモン分泌促進などのメリットがある
- 睡眠の質を高めるトリプトファンも含まれている
- 理想的な時間は夕食の一品として就寝の3時間前までに食べ終えること
- 太りにくい食べ方は単品、または豆腐や野菜と組み合わせる
- タレの代わりに、お酢やポン酢を活用するのが賢い選択
- キムチやお酢、オクラなどとの組み合わせはダイエット効果を相乗的に高める
- 正しい知識と食べ方を実践すれば、夜の納豆は太るどころかダイエットの強力な味方になる



結局、納豆はめっちゃ味方やったんやな。ルールさえ守れば、夜でも気にせんでええねん。これからも頼りにしてるで!


・メンタルを整える本を紹介-1.png)




コメント