「お米から造られる日本酒は太る」というイメージから、ダイエット中はつい敬遠してしまう方も多いのではないでしょうか。
しかし、本当に日本酒は太るのか、それとも工夫次第で痩せることも可能なのか、気になるところです。
例えば、ビールとどっちが太るのか、あるいは糖質がないと言われる焼酎とどっちが太るのか、具体的なカロリーや糖質を把握した上で、他のお酒とのカロリー比較を通じて正しく知りたい、と考えるのは自然なことです。
また、話題の糖質ゼロの日本酒は本当に効果があるのか、飲み過ぎると体に悪いのではないかという健康面の不安や、夜寝る前に飲むと太るのか、飲むなら何時までが良いのかという疑問もあるでしょう。
この記事では、日本酒にまつわる太る飲み方と太りにくい飲み方の違いを科学的な視点から解説します。
つい飲み過ぎて止まらなくなる場合の対処法から、ダイエット中でも楽しめるおすすめ日本酒3選まで、あなたの「日本酒は太るか痩せるか」という疑問に、多角的な情報でお答えしていきます。
- 日本酒が太るとされる原因と実際のカロリー・糖質
- ビールや焼酎など他のお酒との太りやすさの違い
- 体重増加を防ぐための太りにくい飲み方と時間帯
- ダイエット中でも楽しめる糖質オフ日本酒の選び方
日本酒で太る?痩せる?噂の真相を徹底解剖

- 日本酒のカロリー・糖質はどのくらい?
- ビールとどっちが太る?数値を比較
- 焼酎とどっちが太る?製造法の違い
- 他のお酒とのカロリー比較でわかること
- 話題の糖質ゼロ日本酒は太りにくい?
日本酒のカロリー・糖質はどのくらい?
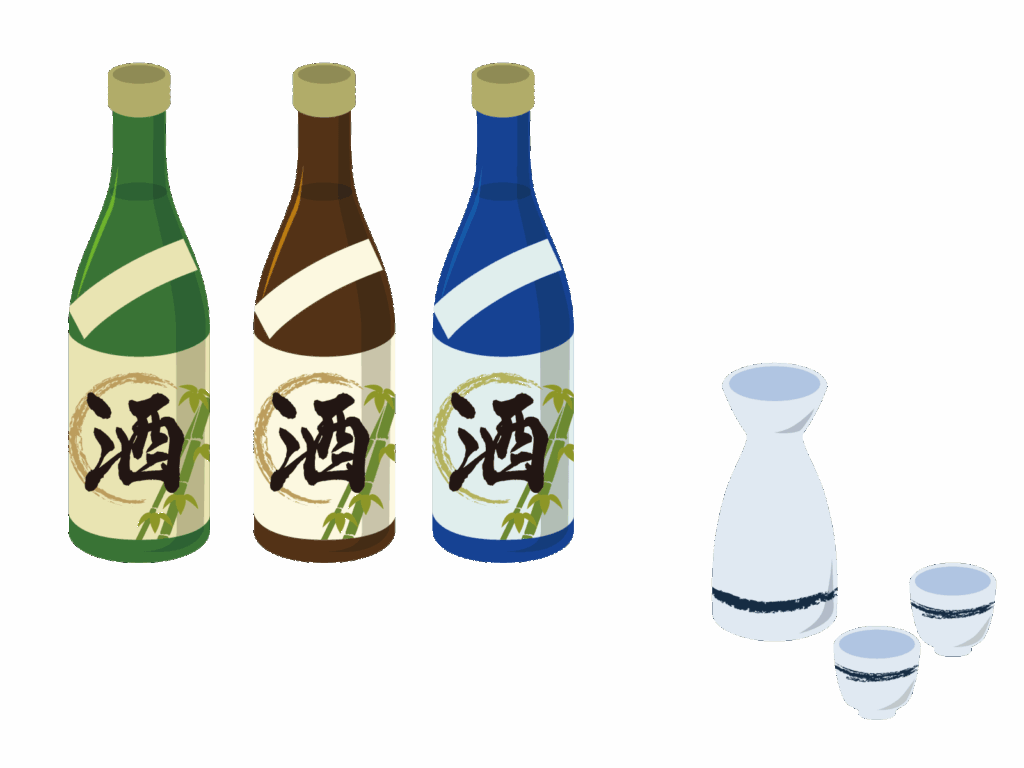
日本酒が太りやすいというイメージの根源には、カロリーと糖質への懸念があるかと思われます。まず、日本酒の具体的な数値について見ていきましょう。
文部科学省が公表している「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」によると、日本酒(純米酒)100gあたりのカロリーは約102kcal、炭水化物(ほとんどが糖質)は3.6gとされています。居酒屋などでよく使われる1合(約180ml)に換算すると、カロリーは約184kcal、糖質は約6.5gとなります。
これを他の食品と比較すると、例えばご飯お茶碗1杯(約150g)のカロリーが約234kcalであるため、日本酒1合のカロリーはそれよりも低いことがわかります。しかし、お酒は食事と一緒に楽しむ嗜好品であり、飲み物としてはカロリーや糖質を意識する必要がある数値だと言えます。
また、「日本酒」と一括りにしても、種類によって成分は少しずつ異なります。特に、米や米麹の成分が多く残っている「にごり酒」のようなタイプは、一般的な清酒に比べて糖質やカロリーが高くなる傾向があるため、選ぶ際には注意が必要です。
このように、日本酒には確かにカロリーと糖質が含まれていますが、その数値が他のお酒と比べて突出して高いわけではありません。太るかどうかを判断するには、他のお酒との比較や飲み方がより重要な要素となります。

なんや、ご飯よりカロリー低いんやったら、そこまでビビる必要もあらへんな。数字をちゃんと知るんが大事やねんな〜。
ビールとどっちが太る?数値を比較


乾杯の定番であるビールと日本酒では、一体どちらが太りやすいのでしょうか。数値を比較して検証してみましょう。
まず、100mlあたりのカロリーと糖質を単純に比較すると、ビールの方が低い数値になります。
- 日本酒(純米酒)100mlあたり: 約102kcal / 糖質 約3.6g
- ビール(淡色)100mlあたり: 約39kcal / 糖質 約3.1g※日本食品標準成分表2020年版(八訂)参考
このデータだけを見ると、ビールの方がヘルシーに感じられるかもしれません。しかし、お酒の太りやすさを考える上で大切なのは、「一度に飲む標準的な量」です。
ビールはアルコール度数が約5%と比較的低いため、中ジョッキ(約400ml)や缶ビール(350ml/500ml)を数杯飲むことも珍しくありません。一方で、日本酒はアルコール度数が約15%と高めなので、1合(180ml)程度をゆっくり楽しむのが一般的です。
厚生労働省が「健康日本21」で示す「節度ある適度な飲酒量」は、1日平均純アルコールで約20gです。これをお酒の量に換算して比較すると、以下のようになります。
| お酒の種類 | 純アルコール20gに相当する量 | カロリー(目安) | 糖質(目安) |
| 日本酒 | 約1合 (180ml) | 約184kcal | 約6.5g |
|---|---|---|---|
| ビール | 中瓶1本 (500ml) | 約195kcal | 約15.5g |
この表からわかるように、同じアルコール量を摂取した場合、ビールの方が日本酒よりもカロリー、特に糖質の摂取量が多くなる傾向にあります。したがって、「ビールは低カロリーだから安心」と油断して量を飲んでしまうと、結果的に日本酒よりも太りやすい状況を招く可能性があるのです。



ビール好きの人にはちょっと耳が痛い話かもやけど、よう考えたらそうなるんやな(笑)。量で考えなあかんてことやね!
焼酎とどっちが太る?製造法の違い


では、ヘルシーなイメージがある焼酎と日本酒ではどうでしょうか。この二つを比較する鍵は「製造法の違い」にあります。
日本酒は、米と米麹を発酵させて造る「醸造酒」です。醸造酒は原料由来の糖分が製品の中に残るため、糖質が含まれます。
一方、焼酎は、発酵させた液体を加熱し、気化したアルコールを冷やして再び液体に戻す「蒸留」という工程を経て造られる「蒸留酒」です。この蒸留の過程で糖質などの成分は除去されるため、焼酎の糖質は基本的にゼロになります。
この点から、血糖値の上昇を抑えたい、糖質制限ダイエットをしているといった方にとっては、焼酎の方が適していると考えられます。
しかし、カロリーに目を向けると話は少し変わってきます。100mlあたりのカロリーを比較すると、以下のようになります。
- 日本酒(純米酒): 約102kcal
- 焼酎(乙類/本格焼酎): 約144kcal
- 焼酎(甲類/連続式蒸留): 約203kcal※日本食品標準成分表2020年版(八訂)参考
このように、アルコール度数が高い分、焼酎の方が100mlあたりのカロリーは日本酒よりも高くなります。もちろん、焼酎はロックや水割り、お湯割りなど、薄めて飲むことが一般的です。そのため、1杯あたりの実際のカロリー摂取量は飲み方によって大きく変動します。
例えば、焼酎60mlを水で割った場合(アルコール度数12.5%程度)のカロリーは約86kcalとなり、日本酒1合(約184kcal)よりは低く抑えられます。
以上のことから、日本酒と焼酎のどちらが太りやすいかは一概には断定できません。糖質を重視するなら焼酎、1杯あたりの満足感とカロリーのバランスを考えるなら日本酒、というように、ご自身のライフスタイルや何を重視するかによって選択が変わってくると言えるでしょう。



なるほどな〜、糖質かカロリーか、どっちを気にするかで変わってくるんか。自分の体と相談しながら選ぶのが一番賢いやり方なんやろな。
他のお酒とのカロリー比較でわかること


ここまでビールや焼酎と比較してきましたが、他のお酒も含めて全体的に見ることで、日本酒の立ち位置がより明確になります。
主要なお酒の100mlあたりのカロリーと糖質の目安を以下の表にまとめました。
| お酒の種類 | 種類 | カロリー(目安) | 糖質(目安) |
| 日本酒(純米酒) | 醸造酒 | 約102 kcal | 約3.6 g |
|---|---|---|---|
| ビール(淡色) | 醸造酒 | 約39 kcal | 約3.1 g |
| ワイン(赤) | 醸造酒 | 約68 kcal | 約1.5 g |
| ワイン(白) | 醸造酒 | 約75 kcal | 約2.0 g |
| 焼酎(乙類) | 蒸留酒 | 約144 kcal | 0 g |
| ウイスキー | 蒸留酒 | 約234 kcal | 0 g |
| 梅酒 | 混成酒 | 約155 kcal | 約20.7 g |
※日本食品標準成分表2020年版(八訂)参考
この表を見ると、日本酒のカロリーや糖質は、数あるお酒の中で突出して高いわけではないことがわかります。むしろ、甘いリキュールである梅酒などは、日本酒よりも糖質が格段に多くなっています。
一方で、焼酎やウイスキーといった蒸留酒は糖質を含まないため、糖質制限を意識する場合には有利です。ただし、アルコール度数に比例してカロリーは高くなるため、飲む量には注意が必要です。
ここで「エンプティカロリー」という言葉についても触れておく必要があります。アルコール由来のカロリーは、体内で優先的に熱として消費されやすく、体に蓄積されにくいことから「エンプティ(からっぽの)カロリー」と呼ばれることがあります。しかし、これは「カロリーがない」という意味ではありません。アルコールからも1gあたり約7.1kcalのエネルギーが生じます。飲み過ぎれば当然、カロリーオーバーにつながります。
さらに重要なのは、肝臓がアルコールの分解を優先している間、食事から摂った脂質や糖質の代謝が後回しにされてしまう点です。これにより、おつまみのカロリーが体脂肪として蓄積されやすくなるのです。
これらのことから、特定のお酒だけを「太る」「太らない」と判断するのではなく、それぞれのお酒の特性を理解した上で、飲む量やおつまみを含めた総摂取カロリーを管理することが大切になります。



こうやって比べると、日本酒だけが悪者にされてる感じもするけど、全然そんなことないんやな。どのお酒も付き合い方が大事ってことや。
話題の糖質ゼロ日本酒は太りにくい?
健康志向の高まりを受け、近年では「糖質ゼロ」や「糖質オフ」を謳った日本酒も増えてきました。ダイエット中の方や、糖質の摂取を控えたい方にとっては、非常に魅力的な選択肢に映るでしょう。
糖質ゼロ日本酒のメリット
最大のメリットは、その名の通り糖質をほとんど含まない点です。糖質は血糖値を上昇させる主な原因であり、インスリンの分泌を促します。インスリンは血中の糖をエネルギーとして利用する一方で、余った糖を脂肪として蓄える働きも持つため、「肥満ホルモン」とも呼ばれます。糖質ゼロの日本酒を選ぶことで、この血糖値の急上昇とインスリンの過剰分泌を抑えることができ、結果として脂肪が蓄積されにくい状態を保てます。
注意すべき点
ただ、糖質ゼロだからといって、完全に太らないわけではありません。前述の通り、アルコール自体にもカロリーは存在します。メーカーの公式サイトなどを確認すると、糖質ゼロの日本酒でも100mlあたり70kcal~90kcal程度のカロリーがあるとされています。これは、通常の日本酒よりは低いものの、決してゼロではありません。そのため、いくら糖質ゼロでも飲み過ぎればカロリーオーバーになります。
また、味わいの面でも特徴があります。糖質は日本酒の「旨味」や「ふくよかさ」を構成する重要な要素の一つです。これを取り除くことで、味わいは全体的に「淡麗辛口」ですっきりとした飲み口になる傾向があります。伝統的な日本酒のコクや豊かな香りを求める方には、少し物足りなく感じられる可能性もあります。
糖質ゼロの日本酒は、太りにくい飲み方の一つの有効な手段です。しかし、カロリーの存在を忘れず、あくまで適量を守って楽しむことが、健康的なお酒との付き合い方の鍵となります。



こらええやん!ダイエット中でも飲める選択肢があるんは嬉しいことやな。ただ、味の違いもあるんやったら、TPOに合わせて使い分けるんがええかもな。
日本酒で太るのを防ぎ痩せる飲み方のコツ


- 太る飲み方・太りにくい飲み方の違い
- 夜寝る前に飲むと太る?何時までOK?
- 飲み過ぎると体に悪い?休肝日の重要性
- つい飲み過ぎる…止まらなくなる対処法
- ダイエット中におすすめ日本酒3選
- 結論!日本酒は太るか痩せるかは飲み方次第
太る飲み方・太りにくい飲み方の違い
日本酒を飲んで太るかどうかの分かれ道は、日本酒そのものよりも、実は「どう飲むか」という点にあります。太りやすい飲み方と、太りにくい飲み方の違いを具体的に見ていきましょう。
体重増加につながりやすい飲み方
- 空腹状態で飲む: 空腹時にお酒を飲むと、アルコールの吸収が非常に速くなります。これにより血糖値が急激に変動しやすくなるほか、酔いが早く回ることで満腹中枢が麻痺し、食べ過ぎにつながりがちです。
- ハイペースで飲む: 短時間で多量を飲むと、肝臓でのアルコール分解が追いつかなくなります。血中のアルコール濃度が高い状態が続くと、代謝機能が低下し、脂肪が燃焼されにくくなります。
- 高カロリー・高糖質のおつまみ: アルコールには食欲増進作用があるため、つい味が濃く、脂っこいものが食べたくなります。唐揚げやフライドポテト、ピザといったおつまみは、お酒と一緒に摂るとカロリーオーバーの直接的な原因になります。
- 締めのラーメンやご飯: 飲んだ後に炭水化物を食べたくなるのは、アルコール分解によって一時的に低血糖状態になるためです。しかし、ここでラーメンやお茶漬けなどを食べてしまうと、一日の総摂取カロリーを大幅に超えてしまいます。
太りにくい上手な飲み方
- 和らぎ水(やわらぎみず)を飲む: 和らぎ水とは、日本酒を飲む合間に飲む水のことです。日本酒と同量の水を飲むことを目標にしましょう。これにより、血中アルコール濃度の上昇が緩やかになり、悪酔いを防ぎます。また、水を飲むことで満腹感が得やすくなり、日本酒やおつまみの量を自然に減らす効果も期待できます。
- 体を温める「燗酒」で楽しむ: 冷たい飲み物は体を冷やし、代謝を低下させる可能性があります。一方、日本酒を温めて飲む「燗酒」は、体を内側から温め、血行を促進し代謝を助ける効果が期待されます。ゆっくりと味わうことで、飲むペースも自然と落ち着きます。
- おつまみの選び方を工夫する: おつまみは、アルコールの吸収を穏やかにするためにも必要ですが、その選び方が重要です。おすすめは、高たんぱくで低カロリーなものです。
- お刺身: 良質なたんぱく質と、体によいとされる不飽和脂肪酸が摂れます。
- 枝豆・冷奴: 大豆製品は、アルコールの代謝に必要なビタミンB1を豊富に含みます。
- 焼き鳥(塩): 鶏肉は高たんぱく。タレよりも塩を選ぶことで糖質をカットできます。
- 野菜やきのこ、海藻類: 食物繊維が豊富で、血糖値の急上昇を抑える助けになります。
このように、少しの工夫で日本酒はぐっと太りにくいお酒になります。お酒の席を楽しみながらも、自分の体をコントロールする意識を持つことが大切です。



おぉ〜、めっちゃ分かりやすいやん!和らぎ水と枝豆やな、覚えとこ(笑)。これなら罪悪感なく楽しめるわ〜!
夜寝る前に飲むと太る?何時までOK?


「夜、寝る前の一杯が楽しみ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、体重管理の観点からは、夜遅くの飲酒、特に就寝直前の飲酒は避けるのが賢明です。
その理由は、私たちの体に備わっている「体内時計」と深く関係しています。体内には「BMAL1(ビーマルワン)」と呼ばれるたんぱく質が存在し、これは脂肪の蓄積を促進する働きを持っています。このBMAL1の量は一日の中で変動し、日中は少なく、夜22時から深夜2時にかけて急増することがわかっています。
つまり、BMAL1が活発になる夜遅い時間帯に食事やお酒を摂取すると、そのカロリーが脂肪として蓄積されやすくなるのです。
さらに、就寝中は内臓も休息モードに入ります。その状態でアルコールが体内に入ってくると、肝臓は休む間もなく分解作業に追われることになり、大きな負担がかかります。睡眠の質が低下し、翌日の疲労や代謝の低下につながる悪循環も生まれかねません。
では、一体何時までなら飲んでも良いのでしょうか。明確な線引きは難しいですが、一般的には「就寝する3~4時間前」までには飲み終えるのが一つの目安とされています。例えば、24時に寝るのであれば、20時か21時にはお酒を切り上げるのが理想的です。これにより、体がアルコールをある程度分解し、睡眠への影響を最小限に抑えるための時間を確保できます。
夜のリラックスタイムとして日本酒を楽しみたい場合は、飲む時間を少し早めに設定し、量を控えめにするなどの工夫が求められます。



へぇ〜、BMAL1ていうたんぱく質が関係しとるんか。体の仕組みを知ると、時間も気にせなあかんなって思うわ。飲むなら早めの時間から楽しまなあかんな。
飲み過ぎると体に悪い?休肝日の重要性
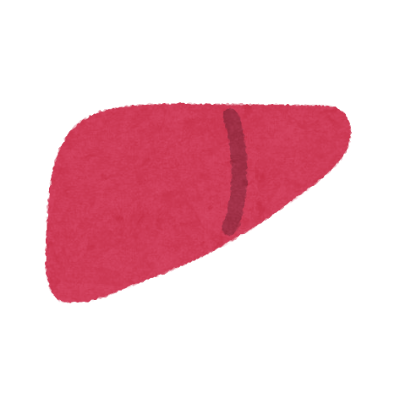
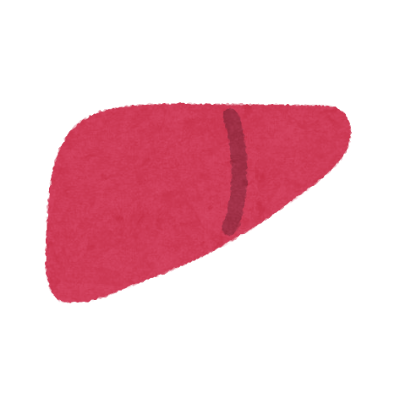
日本酒に限らず、アルコールの飲み過ぎが体に良くないことは広く知られています。適量であれば血行促進やリラックス効果など、良い面もありますが、量を超えると肥満だけでなく、様々な健康リスクを高めることになります。
アルコールを分解する主な臓器は肝臓です。毎日多量のお酒を飲み続けると、肝臓は常にフル稼働の状態となり、疲弊してしまいます。肝臓の機能が低下すると、アルコールの分解だけでなく、脂肪や糖の代謝も滞り、脂肪肝や生活習慣病のリスクが高まります。これが、お酒の飲み過ぎが肥満に直結する大きな理由の一つです。
そこで大切になるのが「休肝日」を設けることです。休肝日とは、文字通り肝臓を休ませる日のこと。お酒を飲まない日を意識的に作ることで、疲れた肝臓が回復するための時間を与えることができます。
厚生労働省は、健康を守るための飲酒のガイドラインとして、週に2日程度の休肝日を設けることを推奨しています。例えば「月曜日と木曜日は飲まない」というように曜日を決めておくと、習慣化しやすくなります。「5日間飲んで週末に2日休む」という形よりも、「2~3日飲んだら1日休む」というサイクルの方が、肝臓への負担をより軽減できると考えられています。
また、飲む日の「適量」を知ることも大切です。前述の通り、厚生労働省が示す「節度ある適度な飲酒」は1日あたり純アルコールで20g程度。これは日本酒に換算すると約1合(180ml)に相当します。
飲み過ぎは確実に体を蝕みます。お酒と長く、健康的に付き合っていくためにも、自分の適量を守り、定期的な休肝日をライフスタイルに取り入れる意識が不可欠です。



せっかく美味しいお酒やから、長く楽しみたいもんな。そのためにも、肝臓さんにもお休みをあげなあかんね。体あっての楽しみやからな。
つい飲み過ぎる…止まらなくなる対処法
「今日は軽く一杯だけ」と決めていたはずなのに、気づけば二杯、三杯と杯を重ねてしまう。そんな経験は、お酒が好きな方なら一度はあるかもしれません。意思の力だけでコントロールするのが難しい場合は、具体的な工夫を取り入れて、飲み過ぎを防ぐ習慣を身につけましょう。
まず、最も手軽で効果的なのが「和らぎ水」を徹底することです。日本酒を一口飲んだら、水を一口飲む。これを繰り返すことで、飲むペースが自然とゆっくりになります。また、水分補給によってアルコールの分解が助けられるだけでなく、満腹感も得やすくなるため、結果として飲む量を抑えることにつながります。
次に、使用する「酒器」を見直すのも一つの方法です。大きなグラスや徳利を使っていると、無意識のうちに飲む量が増えてしまいます。あえて小さなおちょこや容量の少ない片口などを選び、「一杯ずつ注いで味わう」という手間を加えることで、一杯一杯を大切に飲む意識が生まれます。
また、飲み始める前の準備も大切です。空腹状態で飲み始めると、食欲が増してしまい、お酒も食事も進みがちです。飲酒前におにぎり一個や、チーズ、ナッツなどを少しお腹に入れておくだけで、アルコールの急激な吸収を防ぎ、落ち着いてお酒と向き合うことができます。
そして、「ながら飲み」をやめることも意識しましょう。テレビやスマートフォンを見ながらダラダラと飲んでいると、自分がどれだけ飲んだか把握しにくくなります。日本酒の香りや味わいに集中し、食事とのマリアージュを楽しむことに意識を向ければ、量よりも質を重視した満足度の高い飲酒体験が得られるはずです。
これらの対処法は、どれもすぐに実践できるものばかりです。飲み過ぎてしまう自分を責めるのではなく、環境や行動を少し変えることで、上手にお酒と付き合っていくことが可能になります。



ははっ、確かにスマホ見ながらやと、なんぼでも飲んでまうもんな(笑)。小さいおちょこでじっくり味わうって、なんか粋でええやん!
ダイエット中におすすめ日本酒3選


ダイエット中でも日本酒を楽しみたい、という方のために、近年の技術革新によって生まれた糖質やカロリーを抑えた日本酒が存在します。ここでは、比較的手に入りやすく、ダイエットの味方になってくれるおすすめの日本酒を3つご紹介します。
1. 日本盛 糖質ゼロ プリン体ゼロ
大手酒造メーカーである日本盛が開発した、糖質とプリン体の両方をゼロにした画期的な商品です。味わいは「麗辛口」と表現されるように、非常にすっきりとしたキレのある辛口が特徴。糖質がない分、日本酒特有の甘みやコクは控えめですが、その分どんな料理にも合わせやすいという利点があります。特に、お刺身や焼き魚といった和食との相性は抜群です。カロリーも100mlあたり76kcalと、通常の日本酒より低く抑えられています。
2. 菊正宗 清酒 しぼりたて糖質オフパック
「辛口はキクマサ」で知られる菊正宗から発売されている糖質オフ商品です。糖質を50%カットしながらも、生貯蔵酒ならではのフレッシュな香りと、しっかりとした飲みごたえを残しているのが特徴。大吟醸のようなフルーティーさも感じられ、ただ軽いだけでなく、日本酒としての旨味も楽しみたいという方におすすめです。冷やして飲むと、その爽やかさが一層引き立ちます。
3. 月桂冠 糖質・プリン体Wゼロパック
月桂冠が展開する、こちらも糖質とプリン体をダブルでゼロにした商品です。味わいは「大辛口」で、雑味や苦味が少なく、後味のキレが良いのが持ち味です。このお酒が持つウォッシュ効果(口の中を洗い流す効果)は、唐揚げや天ぷらといった脂っこい料理や、中華料理など味の濃い食事と合わせる際に真価を発揮します。料理の味を邪魔せず、次のひと口を新鮮な気持ちで迎えることができます。カロリーも100mlあたり74kcalと、非常に低く設定されています。
これらの日本酒は、体重管理をしながらもお酒を楽しみたいというニーズに応えてくれる心強い存在です。ただし、前述の通りカロリーがゼロではないため、適量を守ることを忘れずに楽しんでください。



こんな便利な商品があるんや!これやったらダイエット中でも気兼ねなく楽しめるな。今度見かけたら買うてみよっと!
結論!日本酒は太るか痩せるかは飲み方次第
この記事を通じて解説してきたポイントを、以下にまとめます。
- 日本酒は「太るお酒」と断定することはできない
- 日本酒1合(180ml)のカロリーは約184kcalでご飯1杯より低い
- 日本酒には米由来の糖質が含まれている
- ビールは飲む量が多くなりがちで総摂取カロリーや糖質が高くなる場合がある
- 焼酎は糖質ゼロだが100mlあたりのカロリーは日本酒より高い
- 太るか痩せるかは飲むお酒の種類だけでなく総量で決まる
- アルコール分解中は食事の脂肪や糖質の代謝が後回しにされる
- 太る最大の原因はハイペースな飲酒と高カロリーなおつまみ
- 太りにくい飲み方の鍵は「和らぎ水」と「おつまみ選び」
- 体を温める「燗酒」は代謝を助ける効果が期待できる
- 夜22時以降の飲酒は脂肪を蓄積しやすいため避けるのが賢明
- 飲むなら就寝の3~4時間前までには終えるのが理想
- 肝臓を休ませるため週2日以上の「休肝日」が推奨される
- 飲み過ぎを防ぐには小さな酒器を使いゆっくり味わうのが有効
- 糖質ゼロやオフの日本酒はダイエット中の選択肢として有力



結局は、日本酒をどう愛してあげるか、ちゅうことやな!正しい知識があれば、美味しく楽しく、健康的に付き合えるんや。これからも日本酒、楽しんでいこか!


・メンタルを整える本を紹介-1.png)





