こんにちは。ユキフルの道、運営者の「ゆう」です。
お正月やお祝い事で食べることの多い「餅米」。
美味しいんですけど、食べながら「餅米って太るんだろうなぁ…」って気になっちゃいますよね。
私も、お餅が大好きなので、その気持ちすごく分かります。
実際のところ、餅米のカロリーや糖質は、普段食べている白米と比較してどう違うんでしょうか。
血糖値への影響や、ダイエット中にどう付き合っていけばいいのか、食べ過ぎないための工夫や太らない食べ方があるなら知りたい、と思うのは当然かなと思います。
この記事では、そんな「餅米は太る?」という疑問について、私なりに調べたことをまとめてみました。
お餅が太りやすいと言われる理由から、賢く楽しむための具体的な方法まで、分かりやすく解説していきますね。
- 餅米が太りやすいと言われる本当の理由
- 白米ごはんと餅米(お餅)の「1食分」での比較
- ダイエット中でも安心な餅米の食べ合わせ
- なぜ玄米餅がスマートな選択肢なのか
餅米は太る?その科学的な真相

まずはじめに、「餅米=太る」というイメージがなぜあるのか、その真相を探っていこうと思います。実は、餅米そのものが白米より圧倒的に悪い、というわけではないみたいなんですよね。ポイントは「密度」と「食べ方」にあるようです。
餅米が太ると言われるのはなぜ?
餅米、特にお餅が「太る」と言われるのには、いくつか複合的な理由が重なっているみたいです。
一番大きな理由は、「高密度」だから、ですね。お餅は、餅米を蒸した後に「搗く(つく)」という工程を経ます。この工程で水分が適度に飛び、米の成分(デンプン)が物理的にギュギュッと凝縮されます。だから、同じ100gで比べると、水分をたっぷり含んだ白米ごはんよりも、実質的な「米(炭水化物)」の量が多くなり、結果的に高カロリー・高糖質になる、というカラクリです。
他にも、こんな理由が考えられます。
高カロリーな味付けの誘惑
お餅って、それ自体はほんのり甘い程度で、味が淡白ですよね。だからこそ、味付けが濃くなりがちです。
- あんこ餅:あんこ自体が砂糖と小豆(炭水化物)で作られています。
- 砂糖醤油餅:砂糖をダイレクトに加えます。
- きな粉餅:きな粉自体は健康的ですが、たっぷり砂糖を混ぜることが多いですよね。
このように、お餅本体のカロリー・糖質に加えて、トッピングでさらに大量のカロリーと糖質を上乗せしてしまうことが、太るイメージを強力に後押ししちゃってるんです。
食べ過ぎの容易さ
お餅は柔らかくて、つるんとした食感で食べやすいですよね。それが故に、満腹感を感じる前に「もう1個、もう1個」と、つい手が伸びてしまいがちです。特に、お正月のような特別な雰囲気の中だと、「今日くらいは」という気持ちもあって、適正量(=ご飯1膳分)を簡単に超えて食べ過ぎてしまう傾向があります。
血糖値の急上昇(血糖値スパイク)
お餅の主成分は、消化吸収されやすい糖質です。特に甘い味付けで単品で食べたりすると、食後の血糖値が急激に上がりやすい(いわゆる「血糖値スパイク」が起きやすい)食品と言えます。血糖値が急上昇すると、それを下げるためにインスリンというホルモンが大量に分泌されます。このインスリンには、血中の糖を脂肪として体に蓄積する働きを促進する側面があるため、太りやすさにつながると指摘されています。

なるほどな、密度と味付けがポイントやったんか!原因がわかれば対策できるやん!
餅米のカロリーと糖質を白米と比較


「じゃあ、どれくらい違うの?」って気になりますよね。ここで、よく比較に使われる「100gあたり」の数値を見てみましょう。データの参照元は、信頼性の高い公的機関のものです。
白米ごはん (100g): エネルギー:156 kcal / 炭水化物(糖質):35.6g
お餅 (100g): エネルギー:223 kcal / 炭水化物(糖質):50.3g
うーん、こうして数字だけ見ると、やっぱりお餅って高カロリーで太りそう…って思っちゃいますよね。白米ごはんの約1.4倍のカロリーと糖質ですから。
注意!これが「密度の罠」です でも、ここで「やっぱり餅米は太る!」と結論づけるのは早いです。これはあくまで同じ「重さ(100g)」で比べた場合の話。さっきも触れたように、お餅は水分が少なくて凝縮されている状態(お餅100g)と、白米は水分をたっぷり吸って膨らんだ状態(ごはん100g)を比べているんです。
イメージとしては、お餅100gの方が、白米ごはん100gよりも、ギュッと詰まった「米粒」の量が多いということ。この食品の成り立ちの違いを無視して100g同士で比較することが、「餅米=太る」という誤解を生む最大の原因なんですね。
「1食分」なら餅米は太らない?
私たちが普段食べる時って、「100g測って食べよう」とは、なかなかならないですよね。「ご飯1膳」とか「お餅2個」みたいに「1食分(1サービング)」で考えるのが現実的です。じゃあ、こっちの現実的な単位で比べたらどうなるんでしょうか。
白米ごはん 茶碗1杯(約150g): 約234 kcal / 糖質 約53.4g(※156kcal/100gで換算)
切り餅 1個(市販品で約50g〜55g): 1個(55g)の場合:約123 kcal / 糖質 約27.7g(※223kcal/100gで換算) 1個(50g)の場合:約112 kcal / 糖質 約25.2g
……あれ? と思いませんか? お餅1個のカロリー・糖質は、ご飯1膳の半分以下です。
ということは、切り餅を2個(合計 約100g〜110g)食べたとすると…
【重要】1食分で比較した真実 切り餅 2個 (計約110g) = 約245 kcal / 糖質 約55.3g
なんと、「切り餅 2個」と「白米ごはん 1膳(150g)」は、カロリーも糖質もほぼ同じなんです!
これ、私にとっては本当に衝撃でした。つまり、「お餅は小さいから大丈夫」って3個も4個も食べてしまう「食べ過ぎ」こそが、太る一番の原因だったんですね。「お餅2個でご飯1膳」という「等価交換」の知識を持つことが、太らないための第一歩と言えそうです。
丸餅と切り餅の違いにも注意
お餅の形状によっても1個あたりの重さが違います。
- 切り餅 1個:約50g〜55g程度
- 丸餅 1個:約35g程度
この重さで換算すると、「切り餅なら2個、丸餅なら3個」が、おおよそご飯1膳分に相当すると言えますね。ご家庭で食べるお餅のタイプに合わせて覚えておくと便利です。
【表】主要主食の「100g」vs「1食分」比較
「100gの罠」と「1食分の真実」をテーブルにまとめてみました。100gあたりで見るか、1食分で見るかで、いかにお餅の印象が変わるかが分かるかなと思います。
| 食品名 | 100gあたり カロリー | 100gあたり 糖質 | 1食分の目安 | 1食分 カロリー | 1食分 糖質 |
|---|---|---|---|---|---|
| お餅(切り餅) | 223 kcal | 50.3g | 2個 (110g) | 約245 kcal | 約55.3g |
| お餅(丸餅) | 223 kcal | 50.3g | 3個 (105g) | 約234 kcal | 約52.8g |
| 白米ごはん | 156 kcal | 35.6g | 1膳 (150g) | 約234 kcal | 約53.4g |
| 食パン (6枚切) | 約260 kcal | 約46g | 1枚 (60g) | 約156 kcal | 約27.6g |
| うどん(茹で) | 約95 kcal | 約20.3g | 1玉 (200g) | 約190 kcal | 約40.6g |
※数値は目安です。出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)および一般的な食品の目安量に基づき換算。



え、マジか!お餅2個でご飯一杯と同じなん!?これ知らんかったわ~、知れてラッキーや!
餅米を使った赤飯やおこわは太る?


「餅米 太る」と検索する時、お餅(搗いたもの)だけでなく、おこわや赤飯といった「炊いた(蒸した)」状態のものも気になりますよね。
これも白米ごはんと比較してみると、やはり同じ重量(例えば100g)なら、赤飯やおこわの方が高カロリー・高糖質になる傾向があります。
| 食品名(100gあたり) | カロリー | 糖質 |
|---|---|---|
| 白米ごはん | 156 kcal | 35.6g |
| 赤飯 | 186 kcal | 40.3g |
| 栗おこわ | 206 kcal | 45.8g |
※出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)より
この理由は、お餅の「密度の罠」と共通しています。餅米は、うるち米(白米)よりも水分を吸いにくい特性がある、または伝統的な「蒸す」調理法により、炊き上がり(蒸し上がり)が白米ごはんよりも「高密度」になるためです。
さらに、赤飯の小豆(ささげ)や、おこわの栗、鶏肉、野菜といった、具材自体のカロリーと糖質が加算されることも大きな要因ですね。
「おこわは野菜も入ってヘルシーかも」と油断しがちですが、主食としては白米ごはんより少しパワフル(高カロリー)だ、と意識しておくと良さそうです。
餅米の栄養と腹持ちの良さ
ここまで「太る」という側面ばかり見てきましたが、餅米はもちろん悪いことだけじゃありません。栄養学的には多くのメリットを持つ、優れた食品なんです。
まず、「お餅は炭水化物の塊で栄養がない」というのは完全な誤解です。確かに主成分は炭水化物(糖質)ですが、それ以外にもタンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルも含まれています。
特に注目したいのが、糖質をエネルギーに変える(代謝する)のを助ける「ビタミンB1」や、体の調子を整える「亜鉛」も含まれていること。エネルギー源となる「糖質」と、その糖質を燃焼させるために必要な「ビタミンB1」の両方を併せ持っているのは、非常に効率的なエネルギー供給源であることを示しています。昔から「力が出る」と言われるのも納得ですね。
最大のメリット:「腹持ちの良さ」の科学
ダイエット中に空腹感は最大の敵ですが、お餅は「腹持ちが良い」という強力なメリットがあります。
これにもちゃんと科学的な根拠があるみたいです。
アミロペクチンと消化のパラドックス
米のデンプンは、「アミロース(サラサラ系)」と「アミロペクチン(ネバネバ系)」の2種類で構成されています。
- うるち米(白米):アミロースとアミロペクチンの両方を含む
- 餅米:デンプンのほとんどが「アミロペクチン」
このアミロペクチンの構造的な特徴により、消化酵素がデンプン質に浸透しにくいことが分かっています。その結果、お餅は胃腸にとどまる時間が長くなります。これが「腹持ちの良さ」の正体なんですね。
ここで「消化吸収がよい(エネルギー効率が良い)」という話と、「消化酵素が浸透しにくい(腹持ちが良い)」という話は、一見矛盾するように聞こえるかもしれません。
でもこれは、「胃での滞留時間が長く、ゆっくり消化されるから“腹持ちが良い”」のと、「胃を通過したあと、小腸で吸収される際には効率よくエネルギーになるから“エネルギー効率が良い”」という、消化の異なる段階の話なんです。つまり、お餅は「ゆっくりと、しかし効率的に」エネルギーに変わる、持続性に優れた食品だと言えそうです。
さらに、お餅は弾力があり、自然と「よく噛む」ことにつながりますよね。よく噛むことは満腹中枢を刺激し、食べ過ぎを防ぐ効果も期待できるので、腹持ちの良さに貢献してくれます。



腹持ちええのは最高やん!ゆっくりエネルギーになるんやったら、ダイエットの味方にもなりそうやね!
「餅米で太る」を防ぐ賢い食べ方


ここまで見てきて、餅米(お餅)は「食べ過ぎ」と「味付け」、そして「食べ合わせ」に気をつければ、ダイエット中でも怖がる必要はない、ということが分かってきました。ここからは、具体的にどう食べればいいのか、私なりに「賢い食べ方」をまとめてみます。
餅米(お餅)の適正な量とは?
やっぱり一番大事なのは「量」のコントロールですね。ここを間違えると、今までの知識が全部ムダになってしまうかもしれません。
1食あたり1〜2個まで。
これを徹底するのが良さそうです。さっき確認したように、「切り餅2個(または丸餅3個)で、ご飯1膳分」というのが基本のライン。これは「1食」の主食としての量です。
お餅を食べたらご飯は減らす「置き換え」が基本
大事なのは、「ご飯1膳」にプラスして「お餅2個」を食べたら、それは単純に「炭水化物を2倍食べた」ことになる、という点です。
もしお餅を1個(ご飯0.5膳分)食べたら、その分ご飯を半膳減らす、といった「置き換え」の意識が重要ですね。お餅はあくまで「主食(炭水化物)」としてカウントして、1日の総炭水化物量がオーバーしないように調整するのが鉄則かなと思います。
餅米の太らない食べ方5つの鉄則
量を守る以外にも、太りにくくする工夫がいくつかあります。私が「これは大事!」と思った5つの鉄則を、おさらいとしてまとめてみますね。
太らないための5つの鉄則
- 鉄則1:量を守る(1食1〜2個まで。必ずご飯と置き換える)
- 鉄則2:時間を考える(活動量の多い朝食や昼食に。夜遅くは避ける)
- 鉄則3:食べ順と食べ合わせを意識する(野菜やタンパク質を先に・一緒に)
- 鉄則4:とにかく良く噛む(満腹中枢を刺激し、少ない量で満足する)
- 鉄則5:賢いレシピを選ぶ(甘い味付けは避け、栄養を補える食べ方を選ぶ)
特に「食べ順・食べ合わせ」と「レシピ」は、血糖値コントロールに直結するので、次で詳しく見ていきますね。
ダイエット中におすすめの食べ合わせ
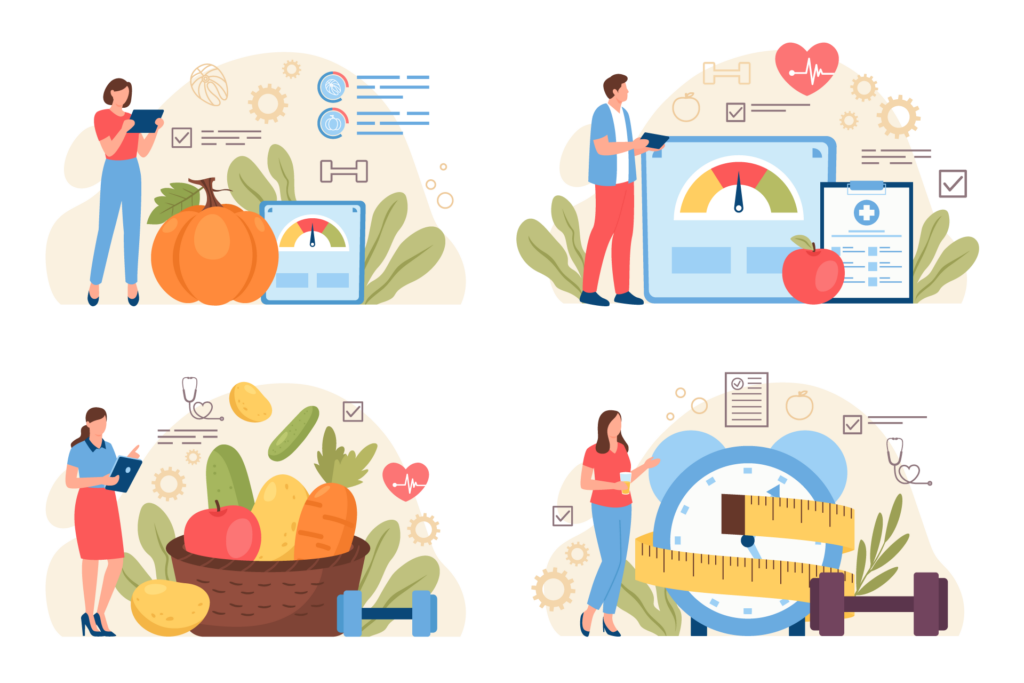
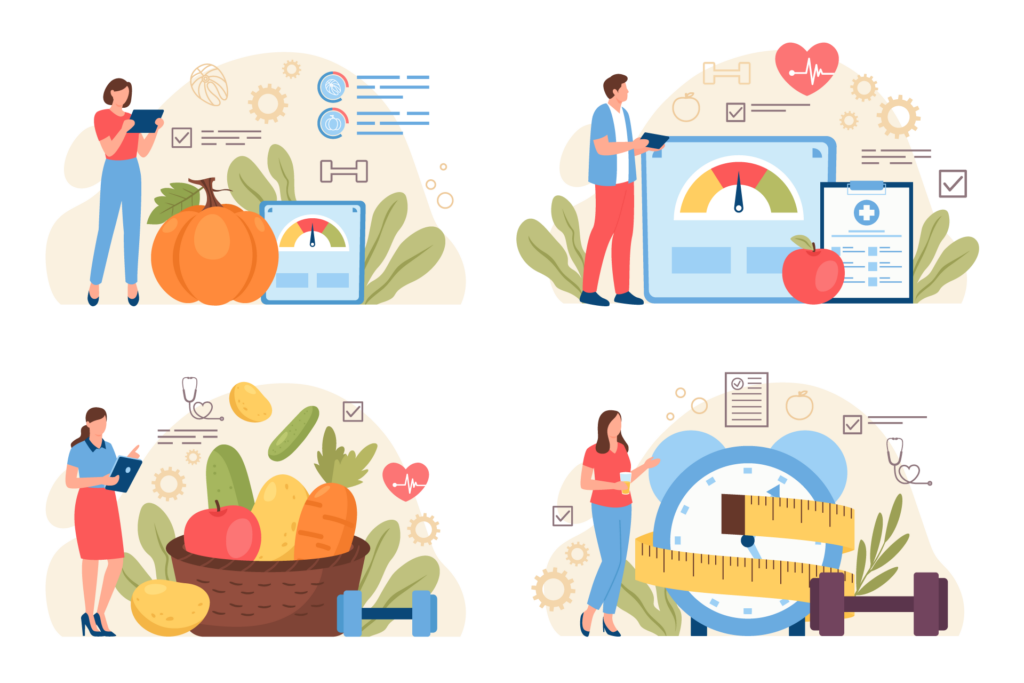
お餅は糖質がメインなので、単品で食べると血糖値が急上昇しやすいのが弱点です。この「血糖値スパイク」を抑えるのが、太らないためのカギになります。
おすすめは、「食物繊維」と「タンパク質」を一緒にとること。これらが糖の吸収を穏やかにし、血糖値の急上昇を防いでくれます。
推奨される食べ方
- 具だくさんのお雑煮: 野菜やキノコ(食物繊維)、鶏肉(タンパク質)がたっぷり摂れます。汁物でお腹も膨れますし、最初に野菜から食べる「食べ順」も自然に実践できます。最強の食べ方かもしれませんね。
- 納餅: 納豆のタンパク質と豊富な食物繊維(水溶性・不溶性両方)がプラスされます。ネギや大葉などの薬味を加えれば、さらに栄養価アップです。
- からみ餅(大根おろし): 大根おろしには、アミラーゼ(デンプン消化酵素)が含まれており、お餅の消化を助けてくれます。もちろん食物繊維も豊富です。
- 磯辺焼き: 海苔は手軽に食物繊維をプラスできる優等生です。
伝統の知恵はすごかった! こうして見ると、「納豆餅」や「からみ餅」って、単なる味のバリエーションじゃなくて、お餅の「消化の重さ」や「血糖値スパイク」といった弱点を、栄養学的に完璧にカバーする、すごく合理的な食べ方だったんですね。昔の人の知恵ってすごいなぁと、改めて思います。
ダイエット中は避けたい食べ方
逆に、ダイエット中に避けた方がいいのは、やっぱり「甘い味付け」です。
- あんこ餅
- 砂糖醤油餅
- ぜんざい、おしるこ
- きな粉餅(砂糖たっぷり)
これらは糖質(お餅)にさらに糖質(砂糖、あんこ)を重ねる食べ方。カロリーも糖質も跳ね上がります。
例えば、お餅2個(約245kcal, 糖質約55g)に、つぶあん40g(約100kcal, 糖質約20g)を加えると、それだけで約345kcal、糖質約75gにもなってしまいます。これはもう血糖値スパイク待ったなし、ですよね。
これらはもう「主食」じゃなくて、「高糖質なお菓子」として、たまに楽しむ、くらいの心構えが良さそうです。



納豆とか大根おろしって、ただの味変ちゃうかったんやな。昔の人の知恵、ホンマあなどれんわ!
餅米(お餅)を食べる時間帯
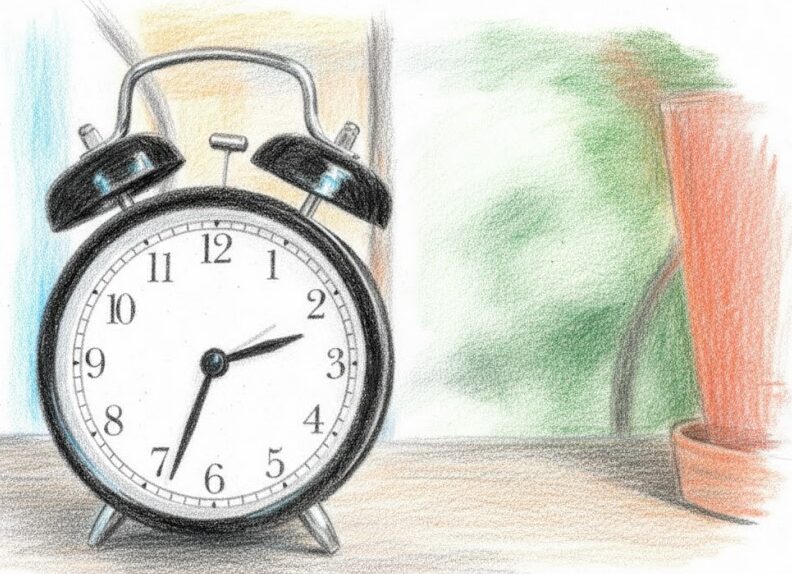
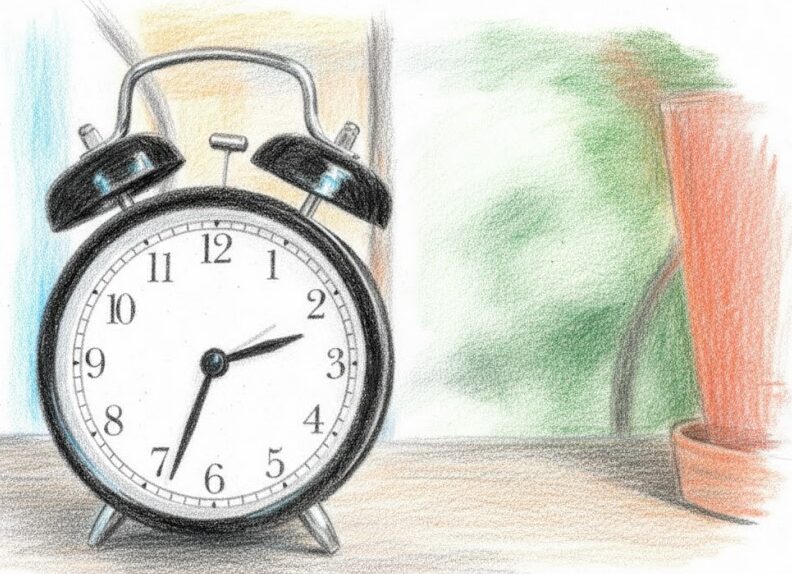
「何を」「どれだけ」食べるかと同じくらい、「いつ食べるか」も結構重要ですよね。
やっぱり活動量が減る「夜遅く」に高糖質のお餅を食べるのは避けるべきかなと思います。寝る前に摂取したエネルギーは消費されにくく、そのまま脂肪として蓄積されやすくなってしまいますから。
食べるなら、これから活動するぞ!という「朝食」や「昼食」の主食として取り入れるのがベスト。日中の活動エネルギー源としてしっかり活躍してくれます。
間食にするなら「魔法の時間」に
もし、どうしても間食として食べたい場合は、「14時〜15時」あたりが「脂肪になりにくい時間帯」として推奨されることが多いです。
これは、体内で脂肪を溜め込む働きをする「BMAL1(ビーマルワン)」というタンパク質の分泌が、1日の中でこの時間帯が最も少なくなるから、と言われています。どうせ食べるなら、一番太りにくい時間を狙うのも賢い戦略ですね。



14時~15時が『魔法の時間』て!そんなんあるんか!これからはその時間におやつタイムやな!
ダイエットなら玄米餅を選ぶべき理由
「ダイエット中は白米より玄米」というのは、健康意識の高い人には常識になりつつありますが、実はお餅にも「玄米餅」という素晴らしい選択肢があるんです。
玄米餅とは?
玄米餅は、その名の通り、精白していない「もち玄米」を原料として作られたお餅です。そのため、白餅(精白したもち米)では製造工程で取り除かれてしまう「ぬか(外皮)」や「胚芽」に含まれる豊富な栄養素が、丸ごと残っています。
これがダイエットにおいて、すごく大きな違いを生むみたいです。
白餅で失われる「ビタミンB群」
さっき、餅米には「ビタミンB1(糖質を燃やすのを助ける)」が含まれている、と話しました。でも、白餅はその製造工程(精白)で、その貴重なビタミンB1やミネラル、食物繊維の多くを失ってしまっています。
一方、玄米餅は、失われたビタミンB群やミネラル、食物繊維が豊富に残っているんです。(製品によっては、精白米の5倍以上のビタミンB1を含むものもあるとか)
白餅 = 「糖質(エネルギー)」がメイン 玄米餅 = 「糖質(エネルギー)」+「糖質を燃やす着火剤(ビタミンB群)」
ビタミンB群は、摂取した「糖質」や「脂質」の代謝を促進する、燃焼系ダイエットにおいて不可欠な栄養素です。
つまり、玄米餅は白餅に比べて「食べても代謝されやすい」食品と言えるかもしれません。同じお餅を食べるなら、代謝を強力にサポートしてくれる玄米餅を選ぶのは、すごくスマートな選択かなと思います。
プチプチとした独特の食感もあって噛み応えが増すので、満腹感も得られやすいですよ。



どうせ食べるんやったら、燃やすのを手伝ってくれる玄米餅って賢い選択やん!これからはこっち試してみよ!
結論:「餅米は太る」の誤解と真実
ここまで「餅米は太る?」というテーマで見てきましたが、私なりの結論はこうです。
「餅米(餅)は、太る食べ物ではなく、太りやすい特性を持った食べ物」
その特性を理解せずに付き合うと、太る原因になってしまう、ということですね。
太る原因は餅米そのものではなく、
- ご飯よりも高密度であることを知らずに「100g」で比べて誤解すること。
- ご飯1膳分(2個)を超える「食べ過ぎ」てしまうこと。
- あんこや砂糖といった「高糖質な味付け」で食べること。
この3つが主な原因だと分かりました。
お餅は、腹持ちが良くて効率的なエネルギー源になる、日本の素晴らしい伝統食ですよね。ダイエット中だからと完全に我慢するんじゃなくて、
- 「量」のコントロール(1食1〜2個まで、ご飯1膳分と知る)
- 「食べ合わせ」のコントロール(野菜、海藻、タンパク質と組み合わせて血糖値スパイクを抑える)
- 「選択」のコントロール(白餅よりも、代謝を助ける玄米餅を賢く選ぶ)
この3つを意識すれば、お餅を「ダイエットの敵」から「賢いエネルギー源」へと変えることができるんじゃないかなと思います。
免責事項 この記事に記載されているカロリーや糖質量、栄養素に関する情報は、文部科学省「日本食品標準成分表」や一般的な知見に基づく「目安」の数値です。実際の数値は、個々の製品や調理法、使用する具材によって大きく異なる場合があります。
また、健康やダイエットに関する効果・効能を保証するものではありません。食物アレルギーのある方や、持病をお持ちの方、健康状態に不安がある場合は、最終的な判断はご自身の責任において行うとともに、必ず医師や管理栄養士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

・メンタルを整える本を紹介-1.png)



