おつまみやサラダの彩りとして人気の生ハムですが、「生ハムの食べ過ぎは太るのでは?」と気になったことはありませんか。
美味しくてつい手が伸びてしまうものの、ダイエット中の食事としては適切なのか、不安に感じる方も多いはずです。
この記事では、生ハムの食べ過ぎが太る原因になるのか、カロリーや糖質、他の食材とのカロリー比較を交えながら詳しく解説します。
また、そもそもダイエット中にありかなしか、食べ過ぎると体に悪いのかといった疑問にもお答えします。
さらに、夜寝る前に食べると太るのか、何時までなら良いのかという時間帯のポイントから、具体的な太る食べ方と太りにくい食べ方の違い、アボカドと生ハムの組み合わせをはじめとしたダイエットレシピまで、網羅的にご紹介します。
この記事を読めば、生ハムと上手に付き合い、美味しく健康的に楽しむための知識が身につきます。
- 生ハムが太る原因となる具体的な栄養素
- 他の加工肉と比べた生ハムのカロリーや脂質の特徴
- ダイエット中に生ハムを食べる際の注意点や最適な時間帯
- 太りにくい食べ方や健康的なアレンジレシピ
生ハムの食べ過ぎは太る?気になる原因を解説

- 生ハムで太る原因は塩分と脂質
- 生ハムのカロリー・糖質はどのくらい?
- 他の食材とのカロリー比較でわかること
- 食べ過ぎると体に悪い?健康への影響
- 生ハムはダイエット中にあり?なし?
生ハムで太る原因は塩分と脂質
生ハムが太る原因として挙げられるのは、主に「塩分」と「脂質」の多さです。美味しく保存性を高めるために、製造過程で多くの食塩が使われるため、生ハムは加工肉の中でも特に塩分が高い傾向にあります。
塩分を過剰に摂取すると、体は体内の塩分濃度を一定に保とうとして水分を溜め込みやすくなります。これが「むくみ」の主な原因です。むくみは一時的に体重を増加させるだけでなく、血行やリンパの流れを滞らせる一因にもなります。流れが滞ると、基礎代謝の低下につながり、結果として痩せにくく太りやすい体質を招く可能性があります。
もう一つの原因である脂質も無視できません。脂質は1gあたり9kcalと、タンパク質や炭水化物の1gあたり4kcalに比べて倍以上のエネルギーを持っています。生ハムに含まれる脂質には、健康に良いとされる不飽和脂肪酸のオレイン酸なども含まれていますが、全体として脂質量が多いため、食べ過ぎれば当然カロリーオーバーにつながります。
薄くて食べやすいため、気づかないうちに何枚も食べてしまいがちですが、その積み重ねが塩分と脂質の過剰摂取となり、体重増加の引き金となるのです。したがって、生ハムを食べる際には、これらの成分を意識し、適量を守ることが大切になります。

なるほど、塩分と脂質が原因やったんか。これを知っとくだけで、だいぶ食べ方が変わってくるわな。賢うなったで!
生ハムのカロリー・糖質はどのくらい?
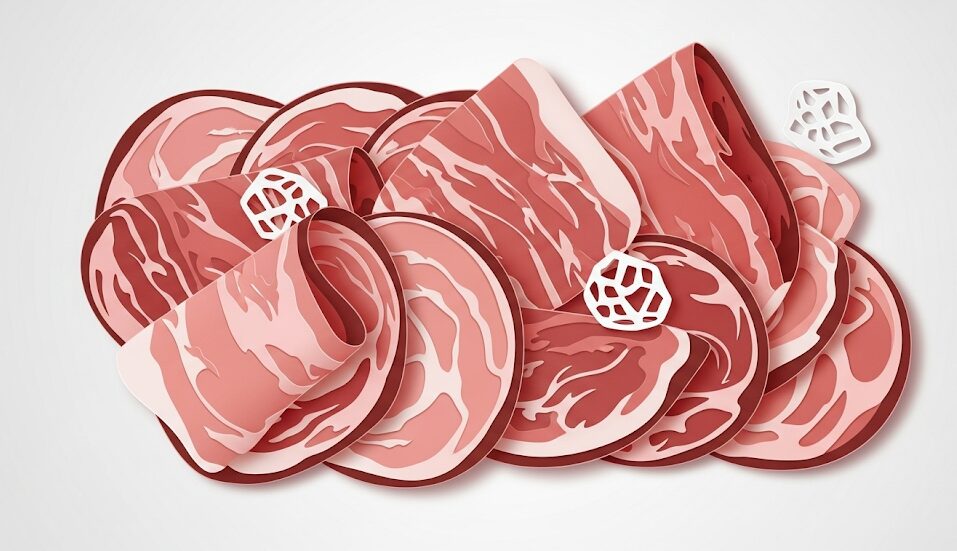
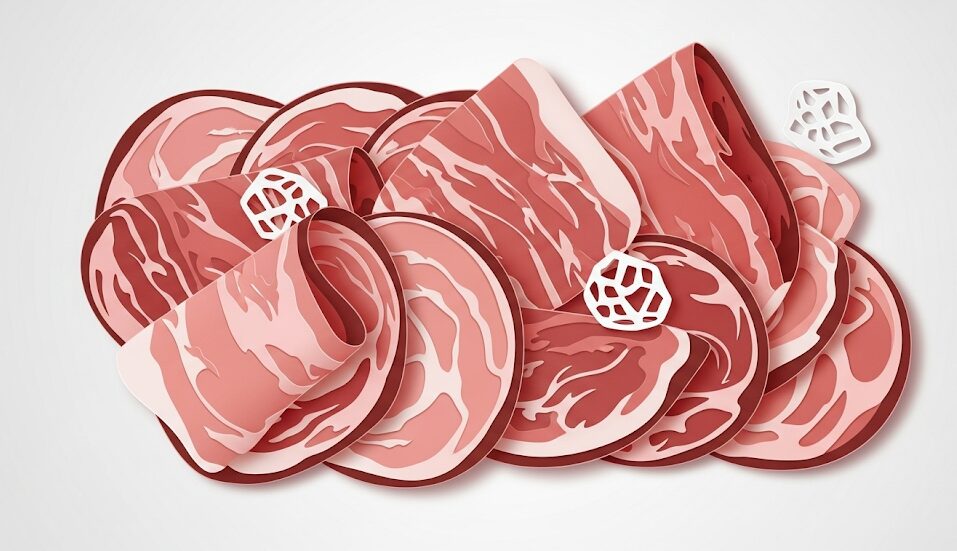
生ハムの具体的なカロリーや糖質量を把握することは、体重管理において非常に有効です。文部科学省が公表している「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」によると、生ハム(促成タイプ)100gあたりの栄養成分は以下のようになっています。
- エネルギー(カロリー):243kcal
- たんぱく質:24.0g
- 脂質:16.6g
- 炭水化物:0.5g
- 食塩相当量:2.8g
このデータから分かるように、生ハムは糖質が100gあたり0.5gと非常に少ない「低糖質」な食材です。糖質制限を意識した食事法を取り入れている方にとっては、使いやすい食材と考えられます。一方で、カロリーは243kcal、脂質は16.6gと決して低くはありません。
スーパーなどで一般的に販売されているスライスパックは、1パックあたり50g〜80g程度のものが多く見られます。仮に70gのパックを1つ食べたとすると、摂取カロリーは約170kcal、脂質は約11.6gとなります。また、1枚あたりの重さを約6gと仮定すると、カロリーは約15kcal、脂質は約1.0gです。
1枚だけなら大した数値ではありませんが、前述の通り、その手軽さから食べ過ぎてしまう傾向があります。例えば、10枚食べればカロリーは150kcal、脂質は10gに達し、これは決して無視できない数値です。タンパク質が豊富であるというメリットもありますが、カロリーと脂質の量を念頭に置き、食べる枚数をあらかじめ決めておくなどの工夫が求められます。



糖質はめっちゃ低いんやな!せやけどカロリーは油断したらあかん感じやね。こうやって数字で見ると分かりやすいわ〜。
他の食材とのカロリー比較でわかること


生ハムの栄養価をより深く理解するために、他の一般的な加工肉と比較してみましょう。それぞれの食材100gあたりの栄養成分を表にまとめました。
| 食品名 | エネルギー(カロリー) | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
| 生ハム(促成) | 243 kcal | 24.0 g | 16.6 g | 0.5 g | 2.8 g |
| ロースハム | 211 kcal | 16.5 g | 15.5 g | 2.0 g | 2.6 g |
| ベーコン(ばら) | 400 kcal | 12.9 g | 39.1 g | 0.3 g | 2.0 g |
| ウインナーソーセージ | 319 kcal | 12.7 g | 28.5 g | 3.3 g | 1.9 g |
| 鶏むね肉(皮なし) | 105 kcal | 23.3 g | 1.9 g | 0.1 g | 0.1 g |
※出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
この比較表から、いくつかの特徴が見えてきます。
まず、生ハムはベーコンやウインナーソーセージに比べると、カロリーと脂質が低いことがわかります。特にベーコンと比較すると、カロリーは約6割、脂質は半分以下です。この点では、比較的ヘルシーな選択肢と言えるかもしれません。
しかし、ロースハムと比較すると、カロリーや脂質はやや高めです。また、注目すべきはタンパク質の量です。生ハムは100gあたり24.0gと、比較した加工肉の中では最も多くのタンパク質を含んでいます。この数値は、高タンパク食材として知られる鶏むね肉に匹敵します。
一方で、塩分量(食塩相当量)は2.8gと最も高くなっています。ベーコンやウインナーよりも塩分が多い点は、明確な注意点です。
これらの比較から、生ハムは「高タンパク・低糖質だが、脂質と塩分は多め」という特性を持つ食材であることがわかります。ダイエット中にタンパク質を補給する目的で選ぶのは有効ですが、脂質や特に塩分の摂取量を抑えるためには、他の加工肉以上に食べる量への配慮が不可欠です。



ベーコン先生に比べたら、全然ヘルシーやん!タンパク質もぎょうさんあるし、ええとこもいっぱいあるんやで。あとは塩分とどない付き合うかやな!
食べ過ぎると体に悪い?健康への影響
生ハムの食べ過ぎは、体重増加だけでなく、健康面においてもいくつかの懸念点があります。主な影響としては、塩分の過剰摂取によるものと、加工肉全般に関連するリスクが挙げられます。
塩分過剰によるリスク
前述の通り、生ハムは塩分が非常に多い食品です。厚生労働省が定める「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、1日あたりの食塩摂取量の目標値を成人男性で7.5g未満、成人女性で6.5g未満としています。
生ハムを100g食べると、それだけで1日の目標量の半分近くを摂取してしまう計算になります。塩分の慢性的な過剰摂取は、むくみや代謝の低下だけでなく、高血圧の主要なリスク因子です。高血圧は、自覚症状がないまま進行し、将来的には脳卒中や心筋梗塞といった命に関わる重大な病気を引き起こす可能性があります。
加工肉の摂取に関する注意点
生ハムは豚肉を原料とする「加工肉」に分類されます。世界保健機関(WHO)の専門組織である国際がん研究機関(IARC)は、加工肉を継続的に毎日50g摂取し続けると、大腸がんのリスクが18%増加するという報告を発表しています。
これはあくまで継続的な大量摂取に関するリスクであり、たまに少量を楽しむ分には過度に心配する必要はないと考えられます。しかし、習慣的に生ハムを大量に食べている場合は、このリスクを念頭に置き、摂取頻度や量を見直すことが賢明です。
添加物の存在
市販されている生ハムの多くには、色を鮮やかに保つための発色剤(亜硝酸ナトリウムなど)や、保存性を高めるための保存料といった食品添加物が使用されています。これらの添加物は国の安全基準に基づいて使用されていますが、摂取はなるべく避けたいと考える方もいるでしょう。特に、国産の安価な生ハムは、熟成期間を短縮するために調味液に漬け込む製法が取られることがあり、添加物が多くなる傾向があるという情報もあります。
これらの健康への影響を考慮すると、生ハムは日常的に大量消費するのではなく、特別な日のおつまみや料理のアクセントとして、適量を意識して楽しむのが望ましい付き合い方と言えます。



うーん、食べ過ぎはやっぱり体によろしくないんやな…。でもまあ、何でも”ほどほど”が大事ってことやんね。知れてよかったわ、ほんまに。
生ハムはダイエット中にあり?なし?


これまでの情報を総合すると、「生ハムはダイエット中に食べても良いのか?」という問いに対する答えは、「条件付きであり」となります。生ハムをダイエットの味方にするか、敵にしてしまうかは、食べ方次第です。
ダイエット中のメリット
生ハムがダイエット中に役立つ最大の理由は、その栄養成分の構成にあります。
- 高タンパク質:タンパク質は筋肉の材料となる重要な栄養素です。ダイエット中に筋肉量が落ちると基礎代謝が低下し、リバウンドしやすい体になってしまいます。生ハムからタンパク質を補給することで、筋肉量の維持を助ける効果が期待できます。また、タンパク質は消化に時間がかかるため、満腹感を持続させやすく、食べ過ぎを防ぐことにも繋がります。
- 低糖質:糖質がほぼゼロであるため、血糖値の急激な上昇を招きにくいという特徴があります。血糖値の乱高下は、脂肪を溜め込むホルモンであるインスリンの過剰分泌につながるため、これを避けられるのは大きなメリットです。糖質制限ダイエットを行っている方にとっては、特に取り入れやすい食材です。
ダイエット中のデメリットと注意点
一方で、これまで繰り返し述べてきた通り、デメリットも存在します。
- 高塩分:むくみを引き起こし、代謝の低下を招く可能性があります。
- 高脂質:カロリーオーバーの原因となり得ます。
したがって、生ハムをダイエット中に取り入れる際は、これらのデメリットを理解し、対策を講じることが不可欠です。具体的には、1日に食べる量を厳密に決めること(例えば30g~50g程度)、そして塩分の排出を助けるカリウムが豊富な野菜や果物と一緒に食べることです。
これらのポイントを守れば、生ハムはタンパク質を手軽に補給できる便利な食材として、ダイエット中の食事を豊かにしてくれます。メリットとデメリットを正しく理解し、賢く食事に取り入れることが鍵となります。



おっ、食べてええんや!やり方次第で味方になってくれるなんて、めっちゃ嬉しい話やんか!工夫のしがいがあるわ〜。
生ハムの食べ過ぎで太るのを防ぐ食べ方のコツ


- 夜寝る前に食べると太る?何時までならOK?
- 太る食べ方・太りにくい食べ方の違いとは
- ヘルシーなおすすめダイエットレシピ
- アボカドと生ハムはダイエットに最適
夜寝る前に食べると太る?何時までならOK?


夜、特に寝る前に食事をすると太りやすいというのは、多くの方が経験的に知っている事実です。これには、私たちの体内に存在する「BMAL1(ビーマルワン)」というタンパク質が深く関係しています。
BMAL1は、体内時計を調整する役割を持つと同時に、脂肪の合成を促進し、体脂肪として蓄積させる働きがあります。このBMAL1の量は一日の中で変動し、最も少なくなるのが午後2時~3時頃、そして夜10時から深夜2時にかけて急増することが分かっています。
つまり、BMAL1が増加する夜遅い時間帯に食事をすると、食べたものが脂肪として蓄積されやすくなるのです。生ハムは脂質を多く含むため、この影響を特に受けやすい食材と言えます。
では、何時までなら食べて良いのでしょうか。明確な線引きは難しいですが、一般的に、就寝の3時間前までには食事を終えるのが理想的とされています。もし夕食で生ハムを食べるのであれば、できるだけ早い時間帯に済ませるのが賢明です。例えば、夜11時に就寝する生活スタイルであれば、夜8時以降に生ハムを食べるのは避けた方が良いでしょう。
夜にお酒のおつまみとして生ハムを楽しむ習慣がある方は、特に注意が必要です。食べる時間を少し早める、あるいは量を普段より減らすといった工夫をすることで、体重増加のリスクを抑えることができます。



夜は体が脂肪をためこむモードになるんか〜、賢いな体って。よっしゃ、食べる時間だけはきっちり守ることにしよか!
太る食べ方・太りにくい食べ方の違いとは
同じ生ハムでも、食べ方一つで太りやすさは大きく変わります。ここでは、避けるべき「太る食べ方」と、おすすめの「太りにくい食べ方」を具体的に解説します。
注意したい「太る食べ方」
- 生ハムだけで大量に食べる:塩分と脂質をダイレクトに過剰摂取してしまいます。特にパックを開けてそのまま食べ続けるのは最も避けたい食べ方です。
- パンやクラッカー、チーズと合わせすぎる:生ハムと相性の良いこれらの食材ですが、いずれも脂質や糖質、カロリーが高い傾向にあります。美味しい組み合わせですが、ダイエット中は量を控えめにしないと、あっという間にカロリーオーバーになります。
- 味の濃いドレッシングをかける:生ハム自体にしっかりとした塩味があるため、さらに塩分や油分の多いドレッシングをかけると、塩分・カロリーの過剰摂取につながります。
おすすめの「太りにくい食べ方」
- 野菜や果物と一緒に食べる:これが最も重要なポイントです。野菜や果物には、体内の余分なナトリウム(塩分)の排出を促す「カリウム」が豊富に含まれています。きゅうり、トマト、レタス、アボカド、メロン、柿などは特におすすめです。生ハムの塩分を相殺する効果が期待でき、栄養バランスも整います。
- 食べる量をあらかじめ決める:パックから直接食べるのではなく、先に食べる分だけ(例えば3~5枚)をお皿に取り分けましょう。これにより、無意識の食べ過ぎを防ぐことができます。1日の目安は30g~50g程度と考えるのが良いでしょう。
- 減塩タイプの製品を選ぶ:最近では、塩分をカットした減塩タイプの生ハムも販売されています。塩分が気になる場合は、製品選びから工夫するのも一つの手です。
- 水分をしっかり摂る:こまめに水分を補給することで、体内の塩分濃度を調整し、排出を助ける効果が期待できます。
これらの「太りにくい食べ方」を実践することで、生ハムのメリットを活かしながら、デメリットを最小限に抑えることが可能になります。



食べ合わせで全然ちゃうんやな!野菜とか果物と一緒に食べたらええんやったら、むしろお洒落やし最高やん!早速やってみるわ!
ヘルシーなおすすめダイエットレシピ
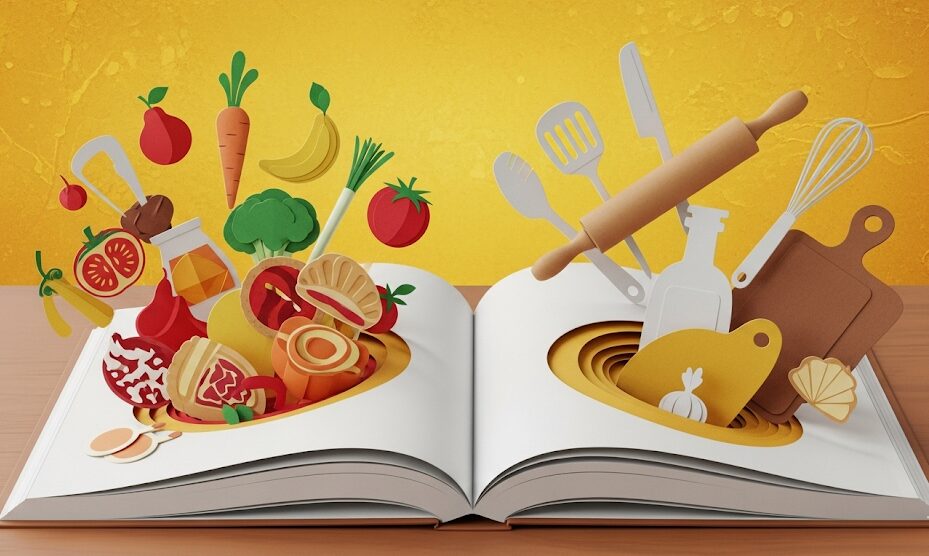
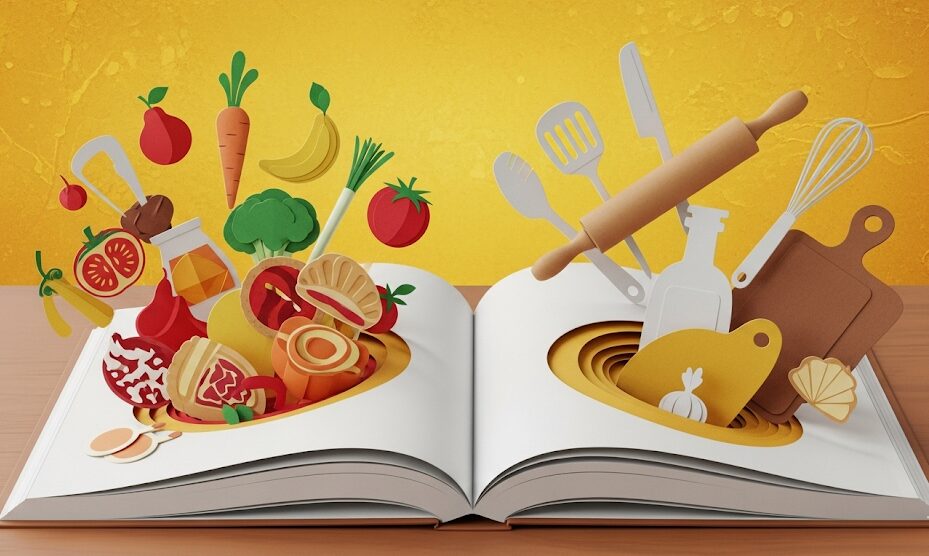
生ハムを美味しく、かつ健康的に楽しむための簡単なアレンジレシピをいくつかご紹介します。これらのレシピは、太りにくい食べ方のポイントを押さえたものばかりです。
生ハムと豆腐麺の冷製パスタ風
糖質が気になるパスタを豆腐麺で代用することで、罪悪感なく楽しめる一品です。
- 材料:生ハム、市販の豆腐麺、ミニトマト、オリーブオイル、塩、こしょう、お好みでパルメザンチーズ
- 作り方:
- 豆腐麺は水気をよく切っておきます。
- ミニトマトは半分にカットします。
- ボウルに豆腐麺、ミニトマト、オリーブオイル、塩、こしょうを入れて和えます。
- お皿に盛り付け、食べやすく切った生ハムを乗せ、お好みでパルメザンチーズをかければ完成です。トマトの酸味と生ハムの塩気が食欲をそそり、さっぱりといただけます。
水ナスの生ハム巻き クリームチーズ添え
火を使わずに作れる、おしゃれで簡単なオードブルです。
- 材料:生ハム、水ナス(またはきゅうり)、クリームチーズ、ブラックペッパー、オリーブオイル
- 作り方:
- 水ナスは薄切りにします。
- 水ナスを生ハムで巻き、お皿に並べます。
- 一口大のクリームチーズを乗せ、ブラックペッパーとオリーブオイルをかければ完成です。ダイエット中であれば、クリームチーズの代わりに水切りヨーグルトを使うと、さらに脂質を抑えられます。
生ハムとたっぷりきのこのレンジ蒸し
きのこの食物繊維と旨味を活かした、ノンオイルでヘルシーな一品です。
- 材料:生ハム、お好みのきのこ(しめじ、舞茸、エリンギなど)、白ワイン(または酒)、こしょう
- 作り方:
- きのこは石づきを取ってほぐします。
- 耐熱皿にきのこを広げ、上に生ハムを乗せます。
- 白ワインを振りかけ、こしょうを振ります。
- ふんわりとラップをして、電子レンジ(600W)で3~4分加熱すれば完成です。生ハムの塩気ときのこの旨味が染み出て、調味料がほとんどなくても美味しくいただけます。



なんやこれ、めっちゃ美味そうやんか!豆腐麺とかレンジ蒸しとか、これなら罪悪感なく楽しめるわ。料理のレパートリーが増えるで!
アボカドと生ハムはダイエットに最適
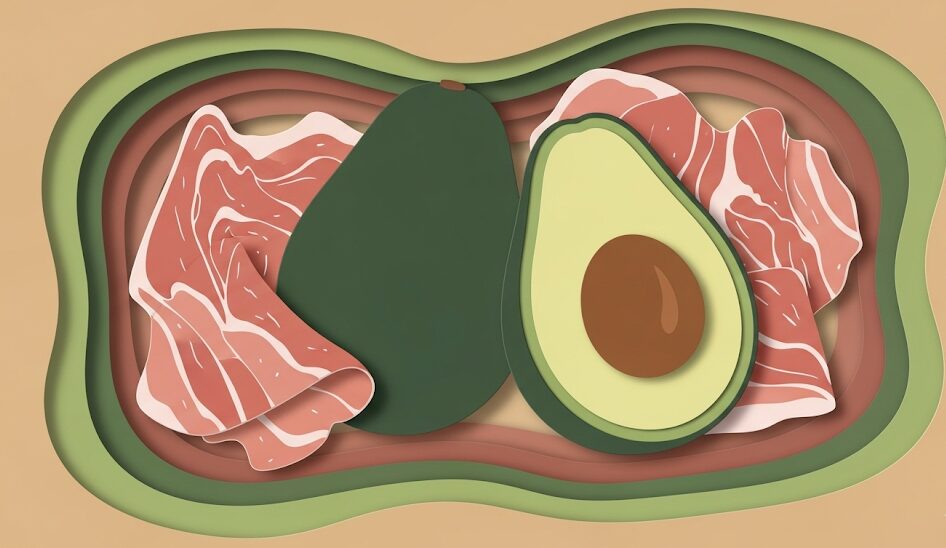
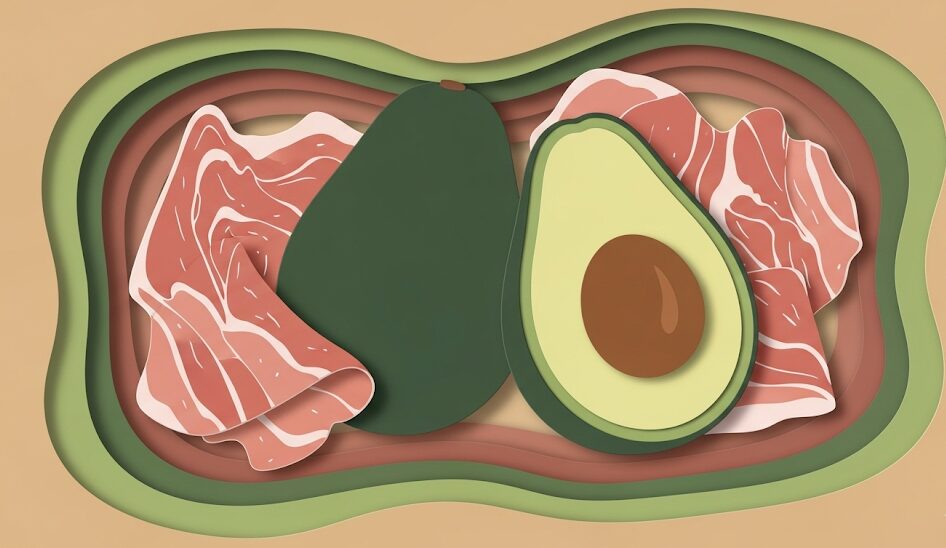
数ある組み合わせの中でも、「アボカドと生ハム」はダイエットにおいて特におすすめできる最適なペアリングです。その理由は、アボカドが持つ栄養素が生ハムのデメリットを見事にカバーし、相乗効果を生み出してくれるからです。
アボカドが持つ優れた栄養素
- 豊富なカリウム:アボカドは、カリウムが非常に豊富な食材として知られています。前述の通り、カリウムには体内の余分な塩分を排出する働きがあるため、塩分が多い生ハムと一緒に食べることで、むくみの予防・改善に大きな効果が期待できます。
- 良質な脂質(オレイン酸):アボカドの脂質の主成分は、生ハムにも含まれるオレイン酸です。この不飽和脂肪酸は、血中の悪玉(LDL)コレステロールを減らす作用があるとされています。脂質は腹持ちを良くし、満足感を持続させる効果もあるため、食べ過ぎの防止に役立ちます。
- 豊富な食物繊維:アボカドには、水溶性・不溶性の両方の食物繊維がバランス良く含まれています。食物繊維は、腸内環境を整えて便通を改善するだけでなく、食後の血糖値の急上昇を穏やかにする働きもあります。これにより、脂肪が蓄積されにくい状態を保つことができます。
- ビタミンE:強力な抗酸化作用を持つビタミンEも豊富です。血行を促進する効果が期待でき、代謝の良い体づくりをサポートします。
おすすめの食べ方
食べ方は非常にシンプルです。
- スライスしたアボカドに生ハムを巻くだけでも、立派な一品になります。オリーブオイルとブラックペッパーをかければ、さらに風味豊かになります。
- 角切りにしたアボカドとちぎった生ハムを、レモン汁と和えてサラダにするのもおすすめです。レモンに含まれるビタミンCは、美肌効果も期待できます。
このように、アボカドと生ハムを組み合わせることで、お互いの長所を活かしつつ、短所を補い合うことができます。美味しくて栄養価も高く、満足感も得られるこの組み合わせは、ダイエット中の食事の強い味方になってくれるはずです。



アボカドと生ハム、最強タッグやん!お互いのええとこ引き出して、弱点カバーして…まるで夫婦みたいやな。これはもう定番にするしかないわ!
結論:生ハムの食べ過ぎは太るのか
この記事で解説してきた内容を基に、「生ハムの食べ過ぎは太るのか」という疑問について、重要なポイントをまとめます。
- 生ハムの食べ過ぎは太る可能性がある
- 主な原因は塩分と脂質の多さにある
- 塩分の過剰摂取はむくみを引き起こし代謝を低下させる
- 脂質はカロリーが高く過剰摂取は体重増加に直結する
- 一方で生ハムは高タンパクかつ低糖質な食材である
- タンパク質は筋肉維持と満腹感持続に役立つ
- 低糖質のため血糖値が上がりにくく脂肪を溜め込みにくい
- ベーコンやウインナーに比べるとカロリーや脂質は低い
- しかしロースハムよりは高く塩分は加工肉の中でも特に多い
- ダイエット中に食べるなら1日30gから50g程度が目安
- 夜遅い時間に食べるのはBMAL1の影響で太りやすいため避ける
- 就寝3時間前までには食事を終えるのが理想
- 太りにくい食べ方は野菜や果物と一緒に摂ること
- 野菜や果物のカリウムが塩分の排出を助ける
- 特にアボカドとの組み合わせは栄養面で非常に優れている



結局は『賢く、美味しく、ほどほどに』ってことやな!ポイントさえ押さえとけば、生ハムは怖くないで。めっちゃ勉強になったわ、ありがとうな!

・メンタルを整える本を紹介-1.png)




