湯気の向こうに優しく揺れる小豆、ふっくらとろけるお餅…。
肌寒い季節、心までじんわり温めてくれるおしるこは、まさに冬のご馳走ですよね。
しかし、その甘く幸せな一杯を味わうたびに、ふと頭をよぎる「これって、もしかしてすごく太る…?」という罪悪感。
そのカロリーや糖質を気にして、本当は食べたい気持ちをグッと我慢していませんか?
ご安心ください。この記事では、そんなあなたの“おしるこにまつわるモヤモヤ”を徹底的に解消します。
「太る」と言われる本当の理由から、気になる餅なしの場合のカロリー、そしてケーキやチョコレートとの衝撃的なカロリー比較まで、専門家が具体的な数字で分かりやすく解説。
さらに、「夜に食べても太らない魔法の時間帯とは?」「むしろダイエットの味方になる賢い食べ方って?」といった誰もが知りたい疑問に答え、ご家庭で簡単に作れる驚きのヘルシーレシピまで、網羅的にご紹介します。
もう「太るから」と我慢するのは今日で終わりにしましょう。
この記事を読めば、おしるこを罪悪感ゼロで心から味わうための知識が身につき、これからの季節、大好きなその美味しさを満喫できるはずです。
- おしるこが太ると言われる本当の理由
- 他のスイーツとのカロリーや糖質の比較
- ダイエット中でもおしるこを楽しむための具体的な方法
- 太りにくい時間帯やヘルシーなアレンジレシピ
「おしるこは太る」は本当?原因を徹底分析

多くの人が抱く「おしるこは太る」というイメージ。それは一体なぜなのでしょうか。このセクションでは、その原因をカロリーや栄養素の観点から多角的に分析し、具体的な数値と共にその真相に迫ります。
- おしるこはこれが太る原因だった
- 気になる餅なしのカロリーは?
- 他の食べ物とのカロリー比較
- おしるこのカロリーを消費するための運動量
- 食べ過ぎると体に悪い?健康への影響
おしるこはこれが太る原因だった
おしるこが太りやすいと言われる最大の原因は、その成分の大部分を占める高い「糖質量」にあります。主原料である小豆自体にも炭水化物が含まれますが、それ以上に、特有の甘みを出すために使用される多量の砂糖が糖質量を押し上げる主要因です。
糖質は、私たちの体を動かすための重要なエネルギー源です。しかし、一度に必要以上の量を摂取してしまうと、エネルギーとして消費されなかった余剰分が体内で中性脂肪に変換され、脂肪細胞として蓄積されやすくなります。これが、体重増加の直接的なメカニズムです。
特に、精製された砂糖を多く含む甘いおしるこは、摂取後の血糖値を急激に上昇させる傾向があります。この血糖値の急上昇、いわゆる「血糖値スパイク」が起こると、私たちの体はそれを正常値に戻そうと、すい臓からインスリンというホルモンを大量に分泌します。
インスリンには、血中の糖を筋肉や細胞に取り込ませてエネルギーとして利用させるという重要な働きがあります。しかし、同時に脂肪の合成を促進し、脂肪の分解を抑制するという、ダイエットの観点からは好ましくない作用も持っています。そのため、インスリンが過剰に分泌される状況は、体脂肪の蓄積に直結しやすい非常に太りやすい状態であると言えるのです。
さらに、おしるこの満足感を高める具材である「餅」や「白玉」も、カロリーと糖質を大幅に増加させる見逃せない要因です。これらは主にもち米や米粉といった炭水化物の塊であり、エネルギー密度が非常に高い食材。ただでさえ糖質が高いおしるこの汁に、さらに餅や白玉が加わることで、一杯あたりの糖質量と総カロリーは大きく跳ね上がってしまうのです。
一方で、おしるこの原料である小豆自体には、食物繊維やサポニン、ポリフェノールといった、健康維持に役立つとされる栄養素も豊富に含まれています。食物繊維は腸内環境を整え、サポニンやポリフェノールには強い抗酸化作用があることが知られています。しかし、こうした小豆のメリットも、砂糖の過剰な添加や高カロリーな具材の組み合わせによって、その効果が霞んでしまうのです。つまり、調理法や食べ方次第で、ヘルシーな食材が太りやすい食べ物へと変わってしまう点を理解しておくことが極めて重要です。

なるほどなあ、犯人は糖質やったんか!脂質が低いからって油断したらあかんってことやな。勉強になるわ〜。
気になる餅なしのカロリーは?


おしるこの総カロリーを大きく左右するのが、トッピングされる餅の存在です。では、餅を入れない「汁のみ」のおしるこであれば、カロリーはどの程度に抑えられるのでしょうか。具体的な数値を見ていきましょう。
餅なしおしるこのカロリー目安
使用するあんこの種類(つぶあんか、こしあんか)や、家庭や製品ごとの砂糖の量によってカロリーは変動しますが、一般的な餅なしのおしるこ一杯(約150g)あたりのカロリーは、およそ180kcal〜210kcalの範囲に収まります。これは、間食(おやつ)の適正カロリーとしてよく目安にされる200kcalとほぼ同等であり、餅さえ入れなければ、おしるこは決して高カロリーすぎるスイーツではないことがわかります。
| あんこの種類 | カロリー目安 (150gあたり) | 特徴 |
| つぶあん | 約180kcal | 小豆の皮ごと使用するため、食物繊維が豊富。 こしあんより甘さ控えめに作られることが多い。 |
|---|---|---|
| こしあん | 約210kcal | 皮を取り除き、なめらかにする工程で砂糖が多く使われる傾向があり、 カロリーが高くなりがち。 |
表からも分かるように、こしあんは製造工程でつぶあんよりも多くの砂糖が加えられることが一般的であるため、カロリーが高くなる傾向にあります。少しでもカロリーを抑えたい場合は、つぶあんを選択する方が賢明です。
餅ありの場合との劇的な差
ここに、一般的な市販の切り餅を1個(約50g)加えると、約110kcal〜120kcalが一気に上乗せされます。つまり、餅入りのつぶあんおしるこであれば約290kcal、こしあんの場合は約320kcal以上にも達する計算になります。これはもはや、軽食やスイーツの範囲を超え、一食分の食事に近いカロリーです。
また、白玉団子の場合でも油断はできません。白玉粉25g(約90kcal)から作られる白玉を5つ加えるだけで、餅とほぼ同等のカロリーがプラスされます。
このように、餅や白玉を加えるというシンプルな行為だけで、総カロリーは約1.5倍にも膨れ上がります。ダイエット中などでカロリーを厳密に管理している場合は、まず餅や白玉を入れない、あるいは量を減らすという工夫が最も簡単で効果的なカロリーコントロール術です。例えば、餅を半分にするだけでも約60kcalの削減につながります。おしるこを食べる際は、この「具材のカロリー」を意識するだけで、賢く楽しむことができるのです。
他の食べ物とのカロリー比較
「おしるこは太る」というイメージが先行しがちですが、他の一般的なスイーツと比較した場合、その立ち位置はどのようになるのでしょうか。ここでは、具体的な数値を基に、おしるこの栄養的な特徴を明らかにします。おしるこの最大の個性は**「脂質が極端に低いが、炭水化物(糖質)が非常に高い」**という点です。
| 食品名 | 1食分の目安 | カロリー | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 |
| おしるこ(餅1個入) | 約200g | 約323 kcal | 約5.5 g | 約0.7 g | 約71.0 g |
| ショートケーキ | 1切れ(約120g) | 約366 kcal | 約4.6 g | 約25.3 g | 約29.0 g |
| ミルクチョコレート | 1枚(50g) | 約279 kcal | 約3.5 g | 約17.1 g | 約28.0 g |
| どら焼き | 1個(約70g) | 約200 kcal | 約4.5 g | 約1.9 g | 約41.0 g |
| シュークリーム | 1個(約70g) | 約145 kcal | 約3.8 g | 約8.2 g | 約13.6 g |
※数値は「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」などを参考に算出された一般的な目安であり、製品やレシピによって大きく異なります。
この比較表から、驚くべき事実が浮かび上がります。おしるこ(餅入り)の脂質量は、ショートケーキの約1/36、ミルクチョコレートの約1/24と、他のスイーツとは比較にならないほど低いのです。脂質は1gあたり9kcalと、タンパク質や炭水化物(1gあたり4kcal)に比べて2倍以上のカロリーを持つため、この低脂質という点は、脂質を制限したいダイエットを行っている方にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
しかし、その一方で注目すべきは炭水化物(糖質)の量です。餅入りの場合、ショートケーキの約2.4倍、どら焼きの約1.7倍もの炭水化物を含んでいます。前述の通り、糖質の過剰摂取は血糖値の急上昇を招き、脂肪蓄積の直接的な原因となり得ます。
結論として、おしるこは**「脂質が原因で太る」タイプの洋菓子とは異なり、「糖質が原因で太る」タイプの和菓子**であると明確に定義できます。総カロリーだけを見るとショートケーキと大差ないように感じられますが、その栄養素の構成が全く異なるため、自分の体質やダイエットのスタイルに合わせて選択する必要があります。糖質制限を実践している方にとっては特に注意が必要な食べ物ですが、脂質を避けたい方にとっては、選択肢の一つになり得るのです。



ショートケーキより脂質がめっちゃ低いんは意外やな!これならダイエットの種類によっては頼もしい味方になってくれそうやんか!
おしるこのカロリーを消費するための運動量
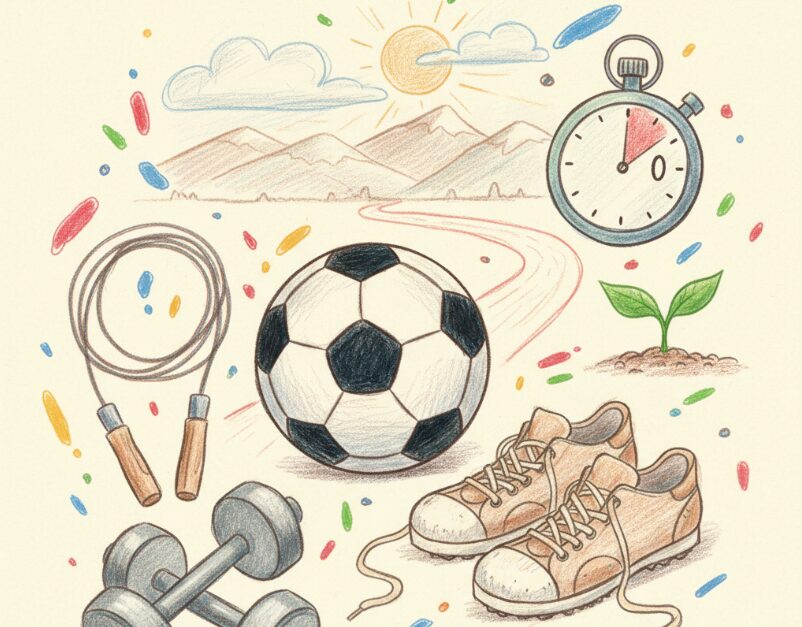
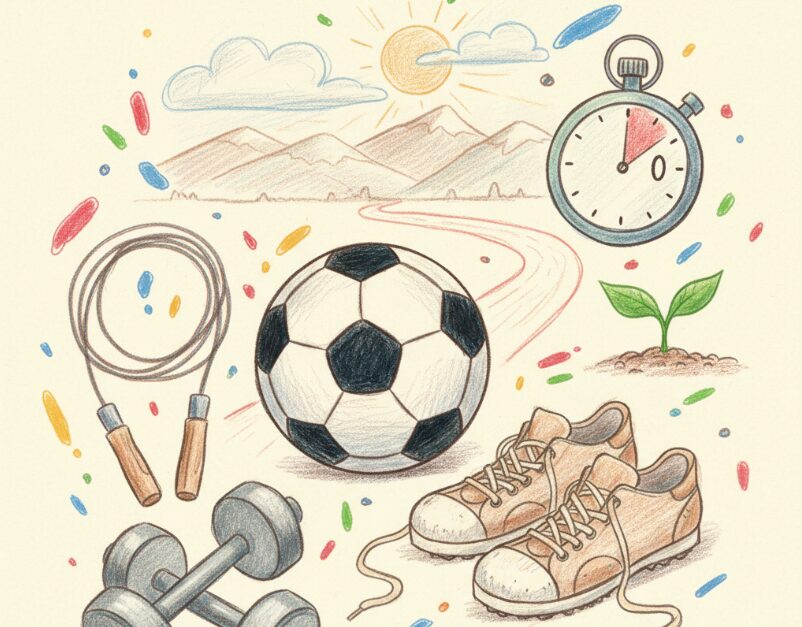
美味しいおしるこを楽しんだ後、その一杯分のカロリーは、具体的にどのくらいの運動で消費できるのでしょうか。ここでは、少し高めの設定として、餅1個入りのこしあんおしるこ(約323kcal)を摂取したと仮定し、そのカロリーを消費するために必要となる各種運動時間の目安を体重別に示します。この具体的な数値を知ることで、食べ過ぎ防止の意識を高めるきっかけになるかもしれません。
| 運動の種類 | 体重50kgの場合 | 体重60kgの場合 | 体重70kgの場合 |
| ウォーキング(やや速め) | 約98分 | 約82分 | 約70分 |
| ジョギング(軽いペース) | 約61分 | 約51分 | 約43分 |
| 自転車(サイクリング) | 約48分 | 約40分 | 約34分 |
| 水泳(クロール、ゆっくり) | 約36分 | 約30分 | 約26分 |
| 階段の上り下り | 約42分 | 約35分 | 約30分 |
| 掃除(家事全般) | 約108分 | 約90分 | 約77分 |
| ストレッチ・ヨガ | 約144分 | 約120分 | 約103分 |
※消費カロリーは個人の年齢、性別、筋肉量、運動強度によって大きく変動するため、あくまで一般的な目安としてご参照ください
この表を見ると、おしるこ一杯のカロリーを消費するためには、決して少なくない身体活動が必要になることが一目瞭然です。例えば、食後に約50分間のジョギングをする、あるいは1時間半かけて念入りに家中の掃除をするといった活動量に相当します。
もちろん、これはあくまで計算上の目安であり、私たちは生命維持活動(基礎代謝)によって常にカロリーを消費しているため、食べた分をすべて運動で相殺しなければならないわけではありません。
しかし、特にデスクワーク中心で活動量が少ない日に、デザートとして甘いおしるこを追加で食べてしまうと、摂取カロリーが消費カロリーを上回り、その差分が脂肪として蓄積されやすいことは紛れもない事実です。
おしるこを食べる日は、意識的に活動量を増やす工夫が体型維持の鍵となります。例えば、一駅手前で電車を降りて歩いてみる、エレベーターやエスカレーターではなく階段を使ってみる、テレビを見ながらストレッチをするなど、日常生活の中に小さな運動を取り入れることを心がけるだけで、長期的に見れば大きな違いとなって現れるでしょう。



うわ、結構がんばらなあかんのやな(笑)でも、食べる前に歩く距離をちょっと伸ばすとか、工夫次第で楽しめそうやん!
食べ過ぎると体に悪い?健康への影響
おしるこはその美味しさから、ついもう一杯と手が伸びてしまいがちですが、食べ過ぎは単なる体重増加だけでなく、様々な健康問題を引き起こす可能性があります。その主な懸念点は、やはり繰り返し指摘してきた**「糖質の過剰摂取」**に集約されます。
血糖値の乱高下とそれに伴うリスク
精製された砂糖を多く含むおしるこを一度にたくさん食べると、血糖値がジェットコースターのように急上昇し、その後インスリンの働きで急降下する「血糖値スパイク」という現象が起きやすくなります。この血糖値の乱高下は、体にとって大きなストレスとなります。
短期的には、強い眠気や倦怠感、イライラ、集中力の低下などを引き起こします。また、血糖値が急降下すると体は「低血糖状態」と錯覚し、再び甘いものを欲するという悪循環に陥りやすくなります。
長期的には、この乱高下を繰り返すことで血管の内壁にダメージが蓄積し、動脈硬化を促進する一因となります。さらに、血糖値をコントロールするために常にインスリンを大量分泌させていると、すい臓が疲弊し、インスリンの効きが悪くなる「インスリン抵抗性」という状態を招き、2型糖尿病の発症リスクを著しく高める可能性が指摘されています。
中性脂肪の増加と生活習慣病
食事から摂取した糖質のうち、エネルギーとして消費されなかった余剰分は、主に肝臓で中性脂肪に変換され、血液中を漂ったり、脂肪細胞や内臓の周りに蓄えられたりします。中性脂肪の値が高くなりすぎると、血液がドロドロの状態になり、脂質異常症や動脈硬化の直接的な原因となります。これらは自覚症状がないまま進行し、ある日突然、心筋梗塞や脳梗塞といった生命を脅かす深刻な病気を引き起こすリスク要因です。
栄養バランスの極端な偏り
おしるこは、その成分のほとんどが炭水化物(糖質)であり、タンパク質やビタミン、ミネラルといった、体の組織を作ったり、調子を整えたりするために不可欠な栄養素がほとんど含まれていません。
もし食事代わりにおしるこばかり食べていると、深刻な栄養失調に陥る可能性があります。タンパク質が不足すれば筋肉量が減少し、基礎代謝が低下してさらに太りやすく痩せにくい体質になります。また、ビタミンやミネラルの不足は、肌荒れや口内炎、貧血、免疫力の低下など、様々な体の不調を招く原因となるのです。
もちろん、これらはすべて「食べ過ぎ」が前提の話です。おしるこの原料である小豆には、便通を改善する食物繊維や、むくみ解消に役立つカリウム、老化防止に繋がるポリフェノールなど、健康に良い成分も確かに含まれています。問題なのは、あくまでその量と頻度です。一日一杯程度を目安にし、他の食事とのバランスをしっかりと考慮しながら、賢く取り入れることが健康を維持する上で非常に大切です。
おしるこで太るのを避けるダイエット活用術
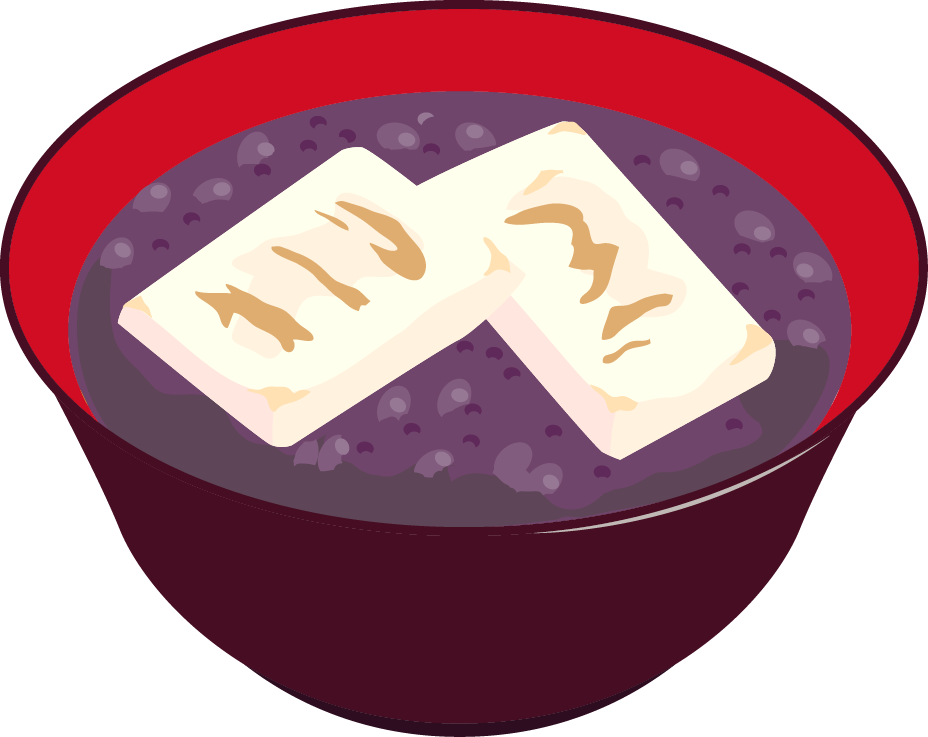
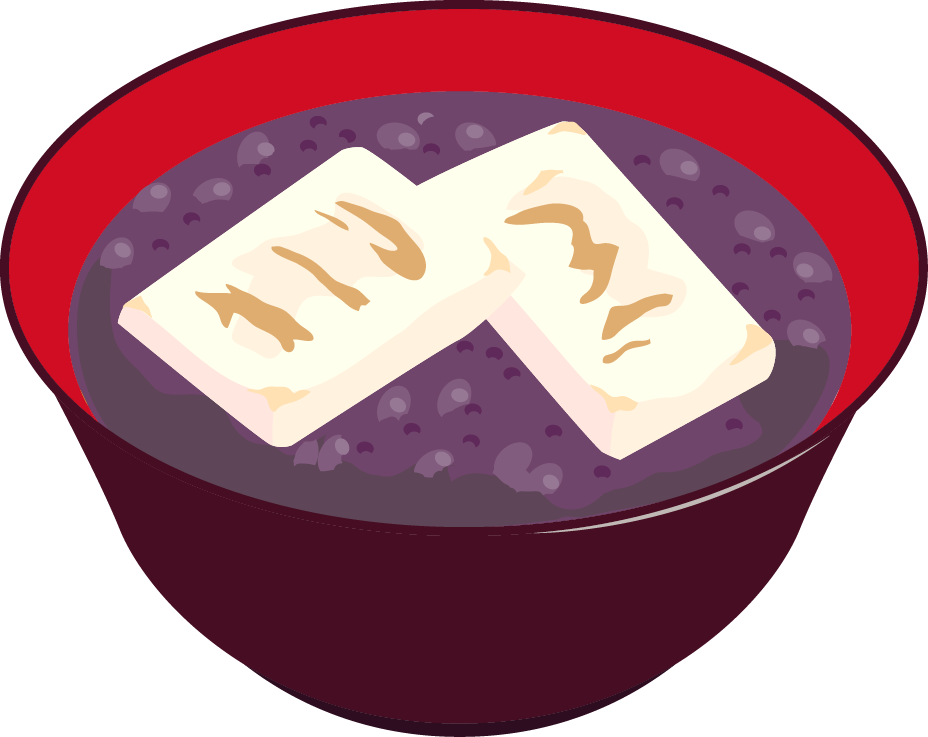
おしるこは太りやすい要素を持つ一方で、その特性を理解し、食べ方を工夫すれば、ダイエット中でも楽しむことができます。このセクションでは、おしるこを「敵」ではなく「味方」にするための、具体的なダイエット活用術を詳しく解説していきます。
- ダイエット中におしるこはあり?
- 太る食べ方・太りにくい食べ方とは
- 夜寝る前に食べると太る?何時までOK?
- 朝ごはんとして食べるメリット
- ヘルシーなダイエットレシピ
- 「おしるこで太る」は食べ方次第で防げる
ダイエット中におしるこはあり?


「ダイエット中だから甘いものは一切禁止」とストイックに制限をかける方もいるかもしれませんが、結論から言うと、食べ方やタイミング、そして自分のダイエット法との相性を考えれば、ダイエット中におしるこを楽しむことは十分に可能です。過度な我慢は強いストレスを溜め込み、その反動で過食に走ってしまうなど、かえってリバウンドの大きな原因になることも少なくありません。
おしるこをダイエットの味方にするための最大のポイントは、その**「低脂質・高糖質」**という栄養的な特徴を深く理解することです。この特性は、実践しているダイエット法によって、おしることの相性が大きく分かれることを意味します。
ローファットダイエット中なら比較的相性が良い
食事全体の脂質の摂取量を抑えることを目的とした**「ローファットダイエット」**を実践している場合、おしるこは比較的取り入れやすいスイーツと言えます。生クリームやバターをふんだんに使用する洋菓子に比べて脂質が格段に少ないため、脂質制限のルールを守りながら甘いものを楽しむことができます。
ただし、いくら低脂質でも糖質の摂りすぎは総カロリーのオーバーに直結するため、量には十分な注意が必要です。例えば、筋トレなど運動前のエネルギー補給として餅なしのものを少量摂る、といったタイミングを工夫することで、摂取した糖質が効率的にエネルギーとして消費され、脂肪になりにくくなります。
糖質制限(ローカーボ)ダイエット中なら原則NG
一方で、糖質の摂取量を厳しく制限する「糖質制限(ローカーボ)ダイエット」や「ケトジェニックダイエット」を行っている場合、おしるこは原則として避けるべき食べ物と考えられます。餅入りの場合、一杯で一日の糖質目標量を大幅に超えてしまう可能性が極めて高いためです。
どうしても食べたいのであれば、砂糖をラカントやエリスリトールのような血糖値に影響を与えない甘味料に置き換え、餅の代わりに糖質の少ない食材(例:おから餅など)を使って完全に自作するなど、特別な工夫が求められます。
いずれのダイエット法を実践しているにせよ、市販の甘いおしるこを無計画に食べるのは推奨されません。食べるのであれば、「量を半分にする」「餅や白玉は入れない」「甘さ控えめのものを選ぶ、または作る」といった自己管理が不可欠です。ストレス解消のための週に一度の「ご褒美」として、頻度と量をあらかじめ決めて上手に付き合っていくのが、ダイエットを長く続けるための現実的な方法と言えるでしょう。
太る食べ方・太りにくい食べ方とは
全く同じおしるこを食べたとしても、その前後の行動や食べ合わせ、食べ方一つで、体に与える影響、特に脂肪の蓄積しやすさは大きく変わってきます。ここでは、絶対に避けたい「太る食べ方」と、ぜひ実践してほしい「太りにくい食べ方」の具体的なポイントを詳しく解説します。
これは避けたい!太る食べ方の典型例
- 空腹時のドカ食い: 長い空腹状態の後に、いきなり糖質の塊であるおしるこを摂取するのは最も危険な食べ方です。血糖値が爆発的に上昇し、インスリンが過剰に分泌され、食べたものが脂肪としてダイレクトに蓄積されやすくなります。
- 餅や白玉を何個も入れる: 前述の通り、餅や白玉はカロリーと糖質を大幅にアップさせる最大の要因です。「お餅2個入り」などは、もはや食事レベルのカロリー摂取と認識すべきです。
- 甘みの強い市販品に頼る: 市販の缶詰やレトルトのおしるこは、長期保存や風味付けのために、想像以上の量の砂糖や異性化糖が使われていることが多くあります。これらを日常的に摂取するのは避けたいところです。
- 満腹後の「別腹」として食べる: 食事で既に十分なカロリーを摂取し満腹に近い状態にもかかわらず、「甘いものは別腹」としておしるこを追加すると、一日の総摂取カロリーが簡単にオーバーしてしまいます。
ぜひ実践したい!太りにくい食べ方のコツ
- 「ベジファースト」を徹底する: おしるこを食べる前に、野菜サラダ、きのこ、海藻など、食物繊維が豊富なものを食べておくのが非常に効果的です。食物繊維が糖の吸収を穏やかにし、血糖値の急上昇を見事に抑制してくれます。外食時など、それが難しい場合は、おしるこを食べる30分前くらいに無調整豆乳や野菜ジュース(無糖)を飲んでおくだけでも効果が期待できます。
- 餅の代わりに栄養価の高い食材を活用する: 餅の代わりに、蒸したかぼちゃやさつまいもを入れるのが非常におすすめです。これらは自然な甘みと満足感を与えてくれるだけでなく、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富で栄養価も高まります。
- 「つぶあん」を積極的に選ぶ: こしあんよりも、小豆の皮ごと使用しているつぶあんの方が、食物繊維やサポニン、ポリフェノールといった栄養素を効率的に摂取できます。噛み応えがあるため、満腹感も得やすいです。
- 温かい状態でゆっくりと味わう: 温かいものをゆっくりと時間をかけて食べることで、脳の満腹中枢が刺激され、少量でも満足感を得やすくなります。これにより、自然と食べ過ぎを防ぐことができます。
- 運動前のエネルギー補給として活用する: これから活動するというタイミングでエネルギー源として摂取すれば、糖質が効率良く消費され、脂肪として蓄積されるリスクを最小限に抑えられます。
これらのポイントを一つでも意識するだけで、おしるこをよりヘルシーに、そして罪悪感なく楽しむことが可能になります。



へぇ〜、食べる前に野菜ジュース飲むだけでもええんか。これならズボラでもできそうやし、めっちゃええこと聞いたわ!
夜寝る前に食べると太る?何時までOK?


夜、特にリラックスしている時間帯に無性に甘いものが食べたくなることは誰にでもある経験でしょう。しかし、夜、とりわけ寝る前におしるこを食べるのは、ダイエットの観点からは最も避けるべき行為であり、太るリスクが非常に高いと言わざるを得ません。その理由は、私たちの体に備わっている生理的なメカニズムと、夜間の活動量の低下にあります。
なぜ夜に食べると太りやすいのか
私たちの体の中には、体内時計を調整する遺伝子の一つとして**「BMAL1(ビーマルワン)」**という特殊なタンパク質が存在します。このBMAL1には、エネルギーを脂肪として細胞内に溜め込む働きを活性化させるという重要な役割があります。
問題なのは、このBMAL1が体内で作られる量は一日の中で常に変動しており、夜22時から深夜2時にかけてその量がピークに達することが研究で分かっている点です。つまり、この時間帯は「脂肪蓄積のゴールデンタイム」とも言え、同じものを同じ量だけ食べたとしても、日中に比べて圧倒的に脂肪として蓄積されやすくなるのです。
さらに、夜間は日中と比べて身体活動量が大幅に減少し、それに伴って体の基礎代謝も低下します。そのため、摂取したカロリーがエネルギーとして消費されにくく、余剰分がそのまま体脂肪になりやすいという不利な状況が重なります。加えて、就寝直前に食事を摂ると、睡眠中も胃腸が消化活動を続けなければならず、睡眠の質を低下させる要因にもなります。質の低い睡眠は、成長ホルモンの分泌を妨げ、代謝の低下をさらに招くという負のスパイラルに陥る可能性もあるのです。
食べるなら「就寝3時間前」が絶対のリミット
どうしても夜におしるこが食べたくなった場合でも、就寝する3時間前までには必ず食べ終えることを最低限のルールとしましょう。例えば、普段23時に寝る生活サイクルの人であれば、20時がリミットと考えられます。これにより、胃の中のものが完全に消化され、血糖値もある程度落ち着いた状態で眠りにつくことができ、睡眠への影響を最小限に抑えることができます。
しかし、ダイエットを真剣に考えるのであれば、おしるこを食べるのに最適な時間帯は、BMAL1の量が最も少なくなる14時〜15時頃のおやつの時間です。この時間帯は「食べても最も太りにくい時間」として知られており、賢く利用したいところです。
夜食としておしるこを選ぶのは、ポテトチップスやカップラーメンといった高脂質・高カロリーな食品よりは健康的かもしれませんが、それが習慣化するのは絶対に避けるべきです。もし夜に食べる場合は、餅や白玉は絶対に入れず、温かい汁だけを少量飲む程度に留めておくのが賢明な判断です。



夜中のBMAL1はん、働きすぎちゃいます?(笑)やっぱりおやつは午後3時が最強ってことやな。しっかり覚えとこ!
朝ごはんとして食べるメリット


夜食とは対照的に、おしるこを朝ごはんとして取り入れることには、いくつかの注目すべきメリットが考えられます。朝はこれから一日が始まる活動的な時間帯であり、摂取したエネルギーを効率良く消費しやすいという大きな利点があります。
脳と体を覚醒させる即効性のエネルギー源
私たちの体は、睡眠中に多くのエネルギーを消費しており、朝起きた時点ではエネルギーが枯渇し、一種の飢餓状態にあります。特に、脳が活動するための唯一のエネルギー源であるブドウ糖が不足している状態です。
ここでおしるこから糖質を補給することで、脳と体の両方に素早くエネルギーを供給することができます。これにより、午前中の集中力や思考力、そして身体的なパフォーマンスを高め、一日を活動的にスタートさせる上で大きな助けとなります。ボーッとしがちな朝の頭をシャキッと目覚めさせる効果が期待できるのです。
体温を上げて一日の代謝をオンにする
朝食を摂ることは、睡眠中に低下した体温を上昇させ、一日の代謝活動のスイッチを入れる重要な役割を果たします。特に、温かいおしるこは内臓から体を直接温め、血行を促進する効果も期待できます。これにより、冷え性の改善や、基礎代謝を効率的に高めるきっかけ作りにも役立ちます。
朝ごはんにする際の重要な注意点
ただし、もちろんメリットばかりではありません。おしるこだけで朝食を済ませてしまうと、栄養バランスが糖質に極端に偏ってしまうという大きなデメリットがあります。健康的な体を作る上で不可欠なタンパク質や、体の調子を整えるビタミン、ミネラルが決定的に不足しがちです。
そこで強く推奨したいのが、おしること一緒にタンパク質を必ず補給することです。例えば、おしること共に無糖のヨーグルトや牛乳、ゆで卵、プロテインドリンクなどを摂取することで、栄養バランスは劇的に改善されます。タンパク質は筋肉の材料となり、基礎代謝を維持するためにも不可欠な栄養素です。
また、朝に食べる場合であっても、餅の入れ過ぎや砂糖たっぷりの市販品に頼るのは避けましょう。甘さ控えめの手作りおしるこに、食物繊維やビタミンが豊富なフルーツや、良質な脂質とタンパク質を含むきなこ、すりごまなどをトッピングする工夫で、栄養価の高いバランスの取れた理想的な朝食にすることが可能です。
ヘルシーなダイエットレシピ
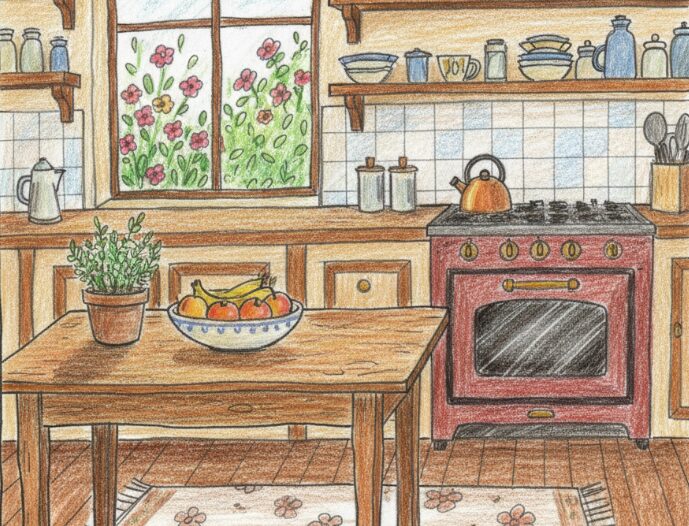
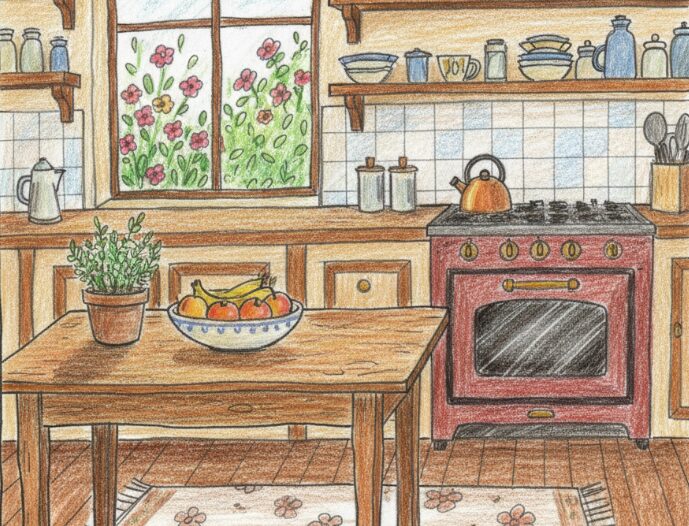
市販のおしるこは手軽で美味しいですが、どうしても糖質やカロリーが高くなりがちです。しかし、ご家庭でほんの少し材料や作り方を工夫するだけで、罪悪感なく心から楽しめる、驚くほどヘルシーなおしるこを作ることができます。ここでは、ダイエット中でも安心なアレンジレシピの具体的なポイントと、すぐに試せるレシピをご紹介します。
ポイント1:砂糖を「ゼロカロリー甘味料」に置き換える
最も簡単で効果的なのが、あんこを作る際の砂糖を、カロリーゼロ・糖質ゼロの天然由来甘味料に置き換える方法です。代表的なものに、羅漢果(ラカンカ)から作られる「ラカントS」や、トウモロコシなどを原料とする「エリスリトール」があります。これらは血糖値の上昇にほとんど影響を与えないため、インスリンの過剰分泌を抑えることができ、ダイエット中には非常に心強い味方です。
小豆を自分で煮る際に、従来の砂糖と同じ分量をこれらの甘味料に置き換えるだけで、あんこ自体のカロリーと糖質を劇的にカットできます。風味を損なうことなく、しっかりとした甘さを楽しめるヘルシーあんこが簡単に完成します。
ポイント2:餅や白玉の「賢い代用品」を活用する
高カロリー・高糖質の餅や白玉の代わりに、栄養価が高く満足感も得られる食材を活用しましょう。
- かぼちゃ・さつまいも: 蒸したり電子レンジで加熱したりしたものを一口大にカットして加えます。自然な甘みとホクホクとした食感が楽しめるだけでなく、食物繊維やβ-カロテン、ビタミンCなどが豊富で、栄養価が格段にアップします。
- 豆腐白玉: 白玉粉に水を加えて練る代わりに、同量の絹ごし豆腐を混ぜて練るだけで、驚くほどもちもちとした食感の白玉が作れます。豆腐のタンパク質がプラスされ、カロリーと糖質を大幅に抑えることができます。
- オートミール: ロールドオーツやクイックオーツといったオートミールを少量加えて煮込むと、自然なとろみがついて腹持ちが非常に良くなります。水溶性食物繊維が豊富で、腸内環境の改善にも役立ちます。
簡単ヘルシー!栄養満点かぼちゃぜんざい
ここでは、餅の代わりに栄養豊富な「かぼちゃ」を使い、甘味料で糖質を抑えた簡単レシピをご紹介します。
材料(2人分)
| 材料 | 分量 |
| ゆであずき(無糖または甘さ控えめ) | 200g |
| かぼちゃ | 100g(正味) |
| 水 | 200ml |
| 天然甘味料(ラカントなど) | 大さじ1〜2(お好みで調整) |
| 塩 | ひとつまみ |
作り方
- かぼちゃは種とワタを丁寧に取り除き、皮をところどころ剥いてから2cm角程度の食べやすい大きさに切ります。耐熱皿に乗せてふんわりとラップをし、電子レンジ(600W)で3分ほど、竹串がすっと抵抗なく通るまで加熱します。
- 小鍋にゆであずきと水を入れ、中火にかけます。木べらなどで混ぜながら、あずきをほぐします。
- 煮立ってきたら弱火にし、天然甘味料と塩を加えて混ぜ合わせ、味を調えます。甘味料の量はお好みで加減してください。塩をひとつまみ加えることで、甘みが引き締まり、より深い味わいになります。
- 器に温かい3を注ぎ、加熱したかぼちゃを彩りよく乗せたら完成です。
このレシピを基本として、お好みできなこをかけたり、すりごまを加えたりと、自分だけのヘルシーアレンジを見つけるのも楽しいでしょう。



かぼちゃとか豆腐で代用するなんて、天才的やん!これやったら罪悪感なく、むしろ体にええことしてる気分で食べられるわ〜。
【総まとめ】「おしるこで太る」は食べ方次第で防げる
この記事を通じて、おしるこが太るかどうかは、その食べ方、量、そしてタイミングに大きく左右されるということを詳しく解説してきました。最後に、おしるこを賢く楽しむための最も重要なポイントを以下にまとめます。
- おしるこが太る主な原因は砂糖と餅による高い糖質量
- 糖質の過剰摂取は血糖値を急上昇させ脂肪蓄積につながる
- おしるこは洋菓子に比べ脂質が圧倒的に低いのが特徴
- 餅なしの場合のカロリーは一杯200kcal前後が目安
- 餅を1個加えるだけでカロリーは約1.5倍に増加する
- おしるこ一杯分のカロリー消費には約50分のジョギングが必要
- 食べ過ぎは血糖値の乱高下や中性脂肪増加のリスクを高める
- ダイエット中でも工夫次第で楽しむことは可能
- 太りにくい食べ方の鍵は食物繊維と食べる順番にある
- 餅の代わりにかぼちゃやさつまいもを使うのがおすすめ
- 夜寝る前の摂取はBMAL1の影響で最も太りやすい
- 食べるなら脂肪が蓄積されにくい午後3時頃がベスト
- 朝ごはんにする際はタンパク質を一緒に摂り栄養バランスを整える
- 手作りする際は砂糖を天然甘味料に置き換えるとヘルシー
- おしるこは一方的に敵視するのではなく上手に付き合うべきスイーツ


・メンタルを整える本を紹介-1.png)



